『永続敗戦論 戦後日本の核心』、『日米戦争を起こしたのは誰か ルーズベルトの罪状・フーバー大統領回顧録を論ず』『英国が火をつけた「欧米の春」』の三題を読んで
「歴史認識」は観光案内をするガイドブックの役割を持つところから、最近研究を始めている。横浜市立大学論叢67巻3号にも「人流・観光論としての記憶・記録遺産(歴史認識)論議序論」を投稿し、抜き刷り送られてきた。このHPにもアップしてあるが、 http://doi.org/10.15015/00000456でもよむことができるはずである。
私が参加させてもらっている勉強会のメンバーから紹介された書籍『日米戦争を起こしたのは誰か ルーズベルトの罪状・フーバー大統領回顧録を論ず』を図書館で申し込んでおいたところ、ようやく順番が回ってきて、さっそく読んでみた。おりしも『永続敗戦論』を読んでいた後だけに、現状否定は共通するも、過去の認識が百八十度異なる両説に大いに興味を抱かされた。そこに英国のEU離脱国民投票をきっかけに書かれた田中宇氏の論評がメールされてきて、改めて歴史は後から解釈されるはずだということの思いを強くさせられた。
まず、わかりやすい『日米戦争を起こしたのは誰か ルーズベルトの罪状・フーバー大統領回顧録を論ず』を概観する。
キャッチコピーは「軍国主義国家の汚名、日本が名誉を回復するためには、日本国民自身が刷り込まれている自虐的な歴史観から脱却のためには必読の書」とあるから主題はすぐに理解でいる。
御多分に漏れず、まず「東京裁判の無効」の主張である。その根拠の一つが「不誠実な日米交渉」とする。宣戦布告には議会の承認が必要であるが、これを省略してハル・ノートを手交したのは国家的詐欺罪とする。高倉健主演の任侠映画に、さんざんいびられた結果相手のやくざの組に攻撃を仕掛けるストーリーがあるが、どういうわけか当時の左翼学生にも大いに受けたものだ。
東京裁判について何よりも重要な認識すべきことは天皇責任が問われなかったことである。この点の評価をしないで否定する立場は、国粋主義的思想の抱える最大の矛盾点である。
NHKのレンタルDVDにも、なぜ日本の指導者は敗戦がわかっている戦争回避の決心ができなかったをテーマにしたものがある。現在の最大公約数的解釈は、日本よりも各組織の立場を重視したとある。明治の元勲がいなくなり、政党政治も機能しなくなると、各組織がバラバラに政策を進めるようになっていったことが原因だとする。陸軍の暗号解読能力は世界有数であったようだが、外務省、海軍と情報共有できていなかった。交渉相手の外国政府は日本政府がバラバラで信用できないと判断していた。霞が関の官僚組織も似たようなところがありよく実感できる。組織間連絡がうまくいかないことは日本だけでなく外国も同じであるが、日本はそれだけひどかったということであろう。陸軍の中も、派兵生先の中国現地部隊の縮小は大物司令官たちが大反対をし、陸軍省の若手課長の縮小論を抑え込んでしまった。その結果がアメリカの経済制裁である。戦後の肉声では、シナ事変だけでも大変だったのにそのうえアメリカまで相手にできるはずがないと言っている。問題先送りの官僚の作文行政は今も昔も変わらない。変わらないのであれば、憲法は変えないほうが安全かもしれない。
NHKは次になぜ戦線を次から次へと拡大していったのかという問題を提起している。この最大公約数的解釈も、政府はバラバラであったからということになっている。海軍が補給の伸び切るにもかかわらず戦線を拡大し、陸軍も負けじとビルマまで拡大してしまった。父親がビルマに派遣されたのもその結果であった。サイパン陥落後の日本人犠牲者は戦争全体の8割であるから、戦争を中止しなかった指導者は国民に責任があるのであり、とてもアメリカの責任にすることはできないはずである。
「不必要な原爆投下」論は理解しやすいが、昭和39年に日本政府は、東京大空襲及び広島、長崎への原爆投下の指令官であるカーチス・ルメイに勲一等旭日大褒章を授与しているから、トータルでの後世の評価を気にした方がいい。少なくともルメイを天皇陛下の名前のもとに叙勲した判断はダブルスタンダードであり、原爆被害者に対しては恥ずかしいことである。
「恥ずべきヤルタ協定」「政権内部に巣くった赤いスパイたちの暗躍」論は、フーバーはヤルタ会談で世界をスターリンに差し出した秘密協定を悪魔の仕業と糾弾する。 スターリンの暗躍もよく伝わってくる話である。この種の話はユダヤ陰謀説もありにぎやかである。日本も中国や満州に傀儡政権を成立させているから、戦争は陰謀合戦でもある。
「米国はインデアン、スペイン人、メキシコ人、ハワイ人から北米大陸の大半を強奪してきた盗賊国家」のくだりも、盗賊かはともかくとして、事実である。しかしその前に、アメリカ大陸の東海岸の一部にしか過ぎなかったアメリカ合衆国の領土拡大のきっかけを作ったのは、19世紀初めのフランスの財政上の理由からのルイジアナ売却である。
人種的に優秀な白人が劣等民族を支配するのは当然であると考えた帝国主義は、アメリカ人より先に欧州人が実行した。名誉白人として最も遅れて日本が実行したころ、欧米の白人至上主義は建前上見直しがなされ始めていたのである。そのことが原因して、日本と韓国、中国の間に「歴史認識」問題が発生してしまうのであるが、重要な観光資源にもなっているのである。
役人時代ODAの仕事でインドネシア鉄道協力に出かけた時に、インドネシア人のマイナス面を現地日本人から聞かされ、素直に信じたことがある。(裏返しに日本人は優秀であると思ったのだが)しかし、今は日本の繁栄は人口ボーナスの所産であり、今度はインドネシアがその所産にあずかる番だと認識が変化した。観光でインバウンドが叫ばれる時代でもある。日本人が特殊なことはないのである。
結論として、この本の「戦後のGHQ占領とその後日本の学会とマスコミがアメリカに迎合して作り上げた虚構の歴史観から一刻も早く抜け出す必要がある」とする点には大いに賛同する。歴史は後から解釈されるからである。ただし戦前の日本の指導者の誤りは認めるべきであろう。
『永続敗戦論』が「1945年以来「敗戦」状態にある。「侮辱のなかに生きる」ことを拒絶せよ」と主張する点は前掲書と同じである。
「エリート層は、アメリカに対しては徹底的に媚びへつらう一方で中国、韓国、北朝鮮に対しては傲慢に振舞い続け、国民の快哉を得ることにより自らの正当性の確立を図る。右翼は現行憲法改正を叫ぶものの上述のアメリカに対する屈辱的事態には目をつぶり、逆に左翼は反米を叫ぶものの、自分達が当のアメリカの核の傘によって庇護されている現実には向き合おうとせず、しかしアメリカの都合により押し付けられた現行憲法だけは金科玉条のものとして奉る。」とする。
そして「敗戦、というアメリカに対する服従を受け入れる代わりに、支配層は国体という名の、天皇をはじめとする支配層の延命を手に入れた」とするのが永続敗戦論である。国民はアメリカ庇護を元にした経済的繁栄を享受したのであり今も継続する。
前掲書と異なる点は、「日本政府は大戦の謝罪を主にアジア諸国に向けている。帝国主義的「侵略」を反省しつつ、暗に欧米の植民地支配や大陸規模の民族抹殺を批判する姿勢(=大東亜戦争の理念)は戦後の日本外交にも残っている」とする点である。
日本の領土問題では、「ダレスの恫喝」や尖閣2島を訓練場として今も占有しながら「中立」という米国の対応を指摘しつつ、米国が国益を追求するのは当然として道義的非難は無意味とする。「日露提携、日中韓提携を絶対に許さない、という米国の強烈な意志と離間策は、知っておいて良い」と強調する。北方領土問題はロシアに分があるという認識であり、尖閣問題は、日本側にダブルスタンダードがあるとする。歴史問題になれば膨大な文書を保有する中国に分が出てくる(井上清京都大学教授)から、棚上げが大人の解決であった。
また、小沢一郎、鳩山由紀夫を戦前の非国民扱いの報道に近い扱いをする日本のマスコミは、未だにアメリカの陰謀であるとする説を信じたくもなる状況である。
強烈な陰謀説の印象を与えるのは『英国が火をつけた「欧米の春」』(2016年6月27日 田中宇)である。http://tanakanews.com/160627UK.htm
以前の大国英国の陰謀説が中心であるから、チャーチルを評価しない永続敗戦論と同じでもある。
「第2次大戦後、米国が世界的に覇権国となったが、その前の覇権国だった英国は、同盟国である米国に戦略を伝授すると言いつつ、ひそかに「軍産複合体」を作って米国の戦略立案過程を乗っ取り、米ソが鋭く対立しつつ仇敵ドイツを東西に恒久分断し、欧州大陸を米英の支配下に置く冷戦構造を作り上げた。その反動で、米国の中枢に、英国のくびきを逃れたいと考える勢力が出てきて、それが90年前後のレーガン政権による冷戦終結、東西ドイツ再統合、EU創設という、英国を困らせる流れにつながった。」と明快である。
しかし「米国が戦後、欧州国家統合を独仏に進めさせた時、英国は、米国の同盟国であるがゆえに、統合に正面切って反対するわけにいかなかった。英国は一応、70年代のEUの前身のEECから欧州統合に参加しているが、ユーロなど国家主権の剥奪を伴う部分への参加を拒否し続けている。英国は冷戦後、EUが統合を加速する中で、東欧やバルカン諸国のEU加盟を強く支援し続け、EUが不安定な周縁部を持つ脆弱な機関になるよう仕向けた。英国は、EUを弱体化するためにEUに入っていた。」とするところのくだりになるとやや牽強付会でもある。
「「EUの国家統合が成功すると、それを主導するのは欧州最大の経済大国であるドイツであり、事実上ドイツが全欧を支配する隠然ドイツ帝国の誕生となる。米国は、独仏にEUを作らせ、英国をドイツ傘下のEUに「恒久幽閉」して潰し、英国が米国の戦略を牛耳る事態を終わらせたかったと考えられる。英国がEUを好まないのは当然だ。EU離脱派の最大の懸念は、移民や難民の増加でなく、EUの統制力の増大によって英国の民主主義が抑圧されることだった。これに「EUなんかに頼らなくても経済発展してみせる」というナショナリズムが加わり、離脱派が増えた。」も同様であるが、歴史は後から解釈されるから、結論を急ぐことはない。
関連記事
-

-
伝統も歴史も後から作られる 『戦国と宗教』を読んで
横浜市立大学の観光振興論の講義ノート「観光資源論」を作成するため、大学図書館で岩波新書の「戦国と宗
-
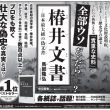
-
有名なピカソの贋作現象 椿井文書(日本最大級偽文書)青木栄一『鉄道忌避伝説の謎』ピルトダウン原人
下記写真は、英国イースト・サセックス州アックフィールド(Uckfield)近郊のピルトダウンにある
-

-
ここまで進化したのか 『ロボットの動き』動画
https://youtu.be/fn3KWM1kuAw
-
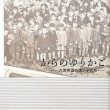
-
『からのゆりかご』マーガレット・ハンフリーズ 第2次世界大戦後英国の福祉施設から豪州に集団移住させられた子供たちの存在を記述。英国、豪州のもっと恥ずべき秘密
第2次世界大戦後英国の福祉施設から豪州に集団移住させられた子供たちの存在を記述。英国、豪州のもっ
-

-
DNAで語る日本人起源論 篠田謙一 をよんで(めも)
篠田氏は、義務教育の教科書で、人類の初期拡散の様子を重要事項として取り上げるべきとする。 私も大賛
-
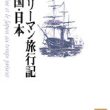
-
書評『シュリューマン旅行記 清国・日本』石井和子訳
日本人の簡素な和式の生活への洞察力は、ベルツと同じ。宗教観は、シュリューマンとは逆に伊藤博文等が
-

-
MaaSに欠けている発想「災害時のロジステックスを考える」対談 西成活裕・有馬朱美 公研2019.6
公研で珍しく物流を取り上げている。p.42では「自動車メーカーは自社の車がどこを走っているかという
-

-
横山宏章の『反日と反中』(集英社新書2005年)及び『中華民国』(中央公論1997年)を読んで「歴史認識と観光」を考える
歴史認識を巡り日本と中国の大衆が反目しがちになってきたが、私は歴史認識の違いを比較すればするほど、
-

-
シャマニズム ~モンゴル、韓国の宗教事情~プラス『易経』
シャーマン的呪術は筮竹による数字と占いのテキストを使った方法にかわった。このことにより特殊能力者でな
