QUORAにみる歴史認識 英国はなぜ世界の覇者になれたんでしょうか?
公開日:
:
最終更新日:2023/05/29
歴史認識
この話を解く鍵は実はイギリスにはないと思います。スペイン・ポルトガルはイギリスより前に覇権国家になりますがなぜか没落してしまいます。その鍵になったのがフェリペ二世です。一時はポルトガルを併合して世界の覇権を一手に手にしました。時期としては(日本の)戦国時代の末期にあたります。この頃にはスペイン領アメリカからの貴金属の着荷も最大になったが、軍事費増大による国庫の破綻は防げず、1596年に大規模なバンカロータを行わざるを得なかった。財源を中南米の金銀とネーデルラントの税収に頼って産業育成を怠ったつけも回っていた。
フェリペ二世は個人の才覚で国を拡大するのですが最終的に資金調達に失敗しました。パンカロータというのは今でいう「デフォルト」のことです。全部で4回行ったそうです。
フェリペ二世の時代はエリザベス一世の時代です。つまり清教徒革命の前なのですが、イギリスはもともと王権がそれほど強くなくさらに清教徒革命の時代に議会制民主主義の原則を確立させて行きます。これが結果的に国内を安定させました。
もう一つの覇権国であるオランダはフェリペ二世の圧政に耐えかねてスペインから独立した地域です。つまりオランダはスペインの植民地だったのです。スペインは覇権のために必要な支出をオランダ・ベルギー地域に依存していました。これを自分たちの繁栄のために使おうというのが独立の動機です。最終的にオランダはスペインから貿易通商ルートも奪取しています。紆余曲折を経て東南アジアをイギリスと分け合うことになりました。イギリスが占領した地域はマレーシアになりオランダが支配した地域はインドネシアになります。オランダは独立当時は都市貴族主体の共和国でした。
オランダよりイギリスの方が強い印象があるのはイギリスは中継地点としてインドを支配できたからだと思います。フランスはスペインの急速な拡大とその失敗から学び植民地を広げていったようです。うまくいっているように見えたのですが、実は内政上の問題を抱えていました。王権が強すぎたために対抗する国民議会ができませんでした。
最終的に財政が破綻寸前になり議会が作られますが、実際に重税に喘いでいた人たちはその議会に代表を送ることはできませんでした。この不満が爆発したのがフランス革命でした。混乱はナポレオン戦争まで続きフランスは一旦海外領土を失ってしまいます。
この質問は「イギリスの覇権」について聞いているのに、なぜ関係のないオランダやフランスの話を持ち出すのか?と思われる方も多いと思います。
それは
- 強いリーダーシップを持てば誰でも覇権を取ることができる可能性がある
- だが、覇権を維持するためには安定した社会制度が必要
ということを説明したかったからです。この仕組みにはだんだん名前がついて行きました。それが議会制民主主義・資本主義という国力を最大化する組み合わせです。つまり覇権も工業化も民主主義の結果という側面があるのです。この議会制民主主義・資本主義の組み合わせは第二次世界大戦でヨーロッパからアメリカに覇権が移っても続きました。アメリカで民主主義を擁護するためによく使われる理屈です。またアメリカは周辺から優秀な人材を集めてきていますが、これも自由野生児参加が前提になっています。
ですがアメリカの内部には徐々に格差ができ始めています。実際に起こっているのは移民排除と国内の貧困層の問題です。トランプ大統領に投票する「移民を排除したい人」の一部はマジョリティの準貧困層で、貧困層にはもともとのマイノリティが多いです。政治的にはアクセスできても実際には政治的意思決定に加われない層というのは三部会に参加できなかった層と似ています。
またこれとは違う形の中華人民共和国が覇権を取れるかも注目されています。ですが国内を富ませるためにはどこから奪取してくる必要があります。どこまで成長を維持できるかによって中国が成功できるかどうかが決まると思います。中国は周辺資源と比較的安価な労働力の確保維持に躍起になっているようです。国外の拡張主義と国内の細分化(都市戸籍と農村戸籍区分や地域指定など)が中国式の経済を支えています。いずれにせよ、今は大航海時代から続いてきたあるスキームが終わるのか続くのかという面白い時期になっていると思います。
資本主義は成長を前提としており、成長というのはすなわち周辺部にある富を中央に持ってくるということです。つまり周辺がなくなればそれ以上成長する余地がなくなり、資本主義そのものが立ち行かなくなる可能性があるわけです。
関連記事
-

-
Quora 物語などによくあるように、中世ヨーロッパの貴族たちは国民から搾取してすごく贅沢な暮らしをしていたのですか?
中世に今日と同じ意味での「国民」はまだ存在しません。領主が農民を支配し、領主同士に主従関係
-

-
歴史は後からの例「殖産興業」
武田晴人『日本経済史』p.68に紹介されている小岩信竹「政策用語としての「殖産興業」について」『社
-

-
三谷太一郎『日本の近代とは何であったか』なぜ日本に資本主義が形成されたか
ちしまのおくも、おきなわも、やしまのそとのまもりなり
-

-
Quoraに見る歴史認識 偉い人ほど責任をとらなくてよくなる、日本特有の謎システム、インパール作戦から続く日本伝統ですか?
元々は江戸時代に確立された風習ですね。 すなわち。 江戸幕府というのは、不思議
-

-
QUORAにみる歴史認識 伊藤博文を殺したのは安重根ではないという説を見ました。もし安重根以外が殺したとしたら誰が何の為に殺したのですか?回
伊藤博文を殺したのは安重根ではないという説を見ました。もし安重根以外が殺したとしたら誰が何の為に殺
-

-
QUORA 日本の歴代総理大臣ワースト1は誰ですか?
日本の歴代総理大臣ワースト1は誰ですか? 近衛文麿でしょう。彼は首相在任中に国運を左右する二
-

-
『国際報道を問いなおす』杉田弘毅著 筑摩書房2022年
ウクライナ戦争が始まって以来、日本のメディアもSNSもこの話題を数多く取り上げてきている。必ずし
-
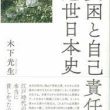
-
『貧困と自己責任の中世日本史』木下光夫著 なぜ、かほどまでに生活困窮者の公的救済に冷たい社会となり、異常なまでに「自己責任」を追及する社会となってしまったのか。それを、近世日本の村社会を基点として、歴史的に考察
江戸時代の農村は本当に貧しかったのか 奈良田原村に残る片岡家文書、その中に近世農村
-

-
『天皇と日本人』ケネス・ルオフ
P114 マイノリティグループへの関心 p.115 皇室と自衛隊 他の国の象徴君主制と大きく
-

-
「米中関係の行方と日本に及ぼす影響」高原明生 学士會会報No.939 pp26-37
金日成も金正日も金正恩も「朝鮮半島統一後も在韓米軍はいてもよい」と述べたこと 中国支配を恐れてい
