『官僚制としての日本陸軍』北岡伸一著 筑摩書房 を読んで、歴史認識と観光を考える
○ 政治と軍
「軍が政治に不関与」とは竹橋事件を契機に明治政府が作ったことである。そもそも明治国家は武士の国家からスタートしているのである。従って、明治期は健全で昭和期に劣化したという司馬史観が正しいかということを思わされた。建軍時から問題をはらんでいたのであろう。明治憲法ができたころは、王朝が普遍的であり天皇制が特殊ではなかった。アメリカがむしろ特殊であった。しかし第一次世界大戦頃に、ホーエンツオレルン家、ロマノフ家、ハプスブルグ家などが崩壊し、変化した。民族自決は欧州のことであったが、1920年代後半に入り中国ナショナリズムが台頭してきた。
○藩閥政治
「英米追随」勢力の元老が弱くなった。政権交代を制度化する、まとめるものとして政党政治に西園寺は理解を示していた。軍は政党に対して協調的であることが、中国の台頭で失われていった。統帥権は日本と欧州で逆であった。素人たる天皇が軍事大権をふるうことは危険と考えるから、政治介入に対する排除の姿勢になる。欧州は皇帝の理想は卓越した軍事指導者であった。皇帝の権力が議会により制約され、最後に残ったのが軍事と外交であった。藩閥主導の軍政関係が根底を支えていたが、下の実務レベルになると陸軍、海軍の対立などかなり深刻で日本の戦果よりも海軍の戦果を重視していた。陸軍中堅層もポーツマス会議が不成功に終わってもかまわないという立場であった(p.53)。現代の日本の役人生活を体験すると妙に納得できるから不思議である。若いころは日本のことなどわからないこともあり、各省各局の権益死守に励んだものである。そこを束ねたのが大蔵省と自民党政策先議のシステムであったのだろう。
○派閥
派閥は陸軍の官僚制を横断する機能を持っていた。セクショナリズムを克服する役割。226事件後、陸軍大臣の地位が重要でなくなった。陸軍権力の下方への移行を象徴するのは、皇族総長。責任政治が崩壊し、大きな力を持っているようで、陸軍の現役の将官は、1916年以来東条英機まで一人も首相になっていない。総力戦の時代、統帥権の独立は時代遅れであったが、統帥権の独立を克服する方法がなっかった。天皇に代わる最終的な国家意思の形成者はあってはならないというのが明治維新の理念。大政翼賛会も幕府的存在という批判に近衛は敏感であった。政党政治は明治憲法下、法的根拠はなかったが、これを打ち壊した結果、日本の政治を根本で束ねることができなくなった。
農水省の構造改善局は局長が事務官であったが、人事は農水土木技官の次長が行っていたのは有名であった。局長は飾りであったのだろう。北条政権下の鎌倉幕府の将軍システムも同じであった。
○支那官僚
軍の暴走や政治介入が、しばしば陸軍内部の分裂や対立の結果として起こった。軍が全体として文あるいは民と対峙するという事態は一般的ではなかった。日本における政軍関係の特質は中国政策の特質。
しな官僚が中央から中央政策を動かす可能性が乏しかったから、出先から動かす可能性が生まれたときの行動が注目される。その機会が到来したとき、しな官僚は各地で軍閥に食い込むが、一貫性を欠きかえって軍閥に利用された。
間接的な満州支配ではだめということを関東軍よりよく知っていたから、満州事変への道を開くこととなった。
○開戦回避の可能性
クラウゼヴィツは内閣に軍人を入れるときは最高の実力者を入れなければならないとしたが、東条英機は首相になってようやく大将になった政治経験の乏しい一軍官僚であった。東條ではなく宇垣であったら、陸軍の駐兵と三国同盟と仏印進駐の立場をより押さえつけたかもしれない。三か月ほど開戦が伸びた可能性がある。その場合は独ソ戦の行き詰まりが明らかになり、日米開戦が避けられたかもしれないと北岡先生はコメントしているが、妙に納得させられた。荻外荘を観光資源化する際に、宇垣コーナーと近衛コーナーを設けると面白いかもしれない。
関連記事
-

-
QUORA ゴルビーはソ連を潰したのにも関わらず、なぜ評価されているのか?
ゴルバチョフ書記長ってソ連邦を潰した人でもありますよね。人格的に優れた人だったのかもしれませんが
-

-
『サカナとヤクザ』鈴木智彦著 食と観光、フードツーリズム研究者に求められる視点
築地市場から密漁団まで、決死の潜入ルポ! アワビもウナギもカニも、日本人の口にしている大
-

-
『中国人のこころ』小野秀樹
本書を読んで、率直に感じたことは、自動翻訳やAIができる前に、日本型AI、中国型自動翻訳が登場す
-
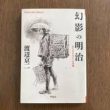
-
『幻影の明治』渡辺京二著 日本の兵士が戦場に屍をさらしたのは、国民の自覚よりも(農村)共同体への忠誠、村社会との認識で追い打ちをかけている。惣村意識である。水争いでの隣村との合戦
「第二章 旅順の城は落ちずとも-『坂の上の雲』と日露戦争」 著者は「司馬史観」に手
-
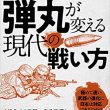
-
『弾丸が変える現代の戦い方』二見龍 照井資規 誠文堂新光社 2018年
本書は、今までほとんど語られてこなかった弾丸と弾道に焦点を当てた元陸上自衛隊幹部と軍事ジャーナリ
-

-
Transatlantic Sins お爺さんは奴隷商人だった ナイジェリア人小説家の話
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswg9n BBCの
-
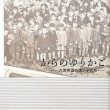
-
『からのゆりかご』マーガレット・ハンフリーズ 第2次世界大戦後英国の福祉施設から豪州に集団移住させられた子供たちの存在を記述。英国、豪州のもっと恥ずべき秘密
第2次世界大戦後英国の福祉施設から豪州に集団移住させられた子供たちの存在を記述。英国、豪州のもっ
-

-
ふるまいよしこ氏の尖閣報道と観光
ふるまいよしこさんの記事は長年読ませていただいている。 大手メディアの配信する記事より、信頼できる
-

-
Quora ヨーロッパ人による境界がなかった場合には、今日のアフリカには幾つくらいの国があったと思いますか? 欧州にはバスク語しか残らなかった
https://youtu.be/i28l-t4H1GM ヨーロッパ人による境界がなかっ
-
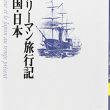
-
『シュリューマン旅行記』 清国・日本 日本人の宗教観
『シュリューマン旅行記 清国・日本』石井和子訳 シュリューマンは1865年世界漫遊の旅に出か

