字句「観光」と字句「tourist」の遭遇(日本観光学会2015年6月発表)
公開日:
:
最終更新日:2023/05/27
人流 観光 ツーリズム ツーリスト
1 ヒトの移動概念の発生と字句の収斂
定住社会における人の移動概念が、英語圏では字句「travel」、日本では字句「たび」、中国では字句「旅」を代表例として収斂していった。日本に漢字「旅」が入ってきたときに「たび」があてられたこと、「travel」の訳語が中国、日本において共通に「旅」があてられたことは理解し易い。
2 旅游と観光
「「楽しみ」のための「旅」」の概念を、中国では「旅行+游覧」からなる「旅游」を用いる。日本ではこの概念に「遊覧」等を用いていたが、概念の発生とは無関係な字句「観光」に収斂していった。しかし、その過程の解明がなされないまま風説が流布しており、その後進性が問われかねない状況である。
3 楽しみの旅を区別させる社会的必要性の発生
英語圏では富裕層の旅は能動的なものとしてtravelとよばれていたが、一般大衆向けの受動的になった旅が発生した。これをtravelerと区別してtouristとする概念が発生し、19世紀までには一般化したとされる。文学ではこの両者の旅の緊張関係をテーマとし、経済学では後者が最終消費財として分析対象とされるが、政策論では日常・非日常の相対化により、人流に収斂してきているとの仮説を立てている。
4 ジャパン・ツーリスト・ビューロー及び国際観光局の設立
「tourist」が日本に紹介される過程で1912年「Japan Tourist Bureau」が設立された。名称として国際旅客奨励会も検討されたが、最終的に字句「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」となった。しかしながら、当時の「tourist」概念に越境概念が含まれていたのかの確認がなされていない。1930年外貨獲得を目的とする政策の一環として国際観光局官制(勅令)が制定された。江木鉄道大臣の強い希望により「国際」をつけたものの、英訳は「Board of Tourist Industry」となっている。このとき易経「国の光りを観る」の解釈において、語源とは異なりインバウンドを強調することとなった。
5 概念「観光」の発生とその分析の限界
「楽しみのための旅」が特権階級の時代には、能動的なアウトバウンドが中心概念となる。その後大衆化により観光客を対象とした産業が成長し、インバウンドを中心とする概念が成立したと考える(仮説①)が、その解明には至っていない。日本においては字句「観光」を使用して外貨獲得政策が展開されたため、越境概念が強く意識されて使用されていたと考える(仮説②)。易経「国之光」の国は都市概念であり、今日的な国境概念は第一次世界大戦後確立した。この意識は、国際ではないものの「国」にこだわっている高尾保勝会及び津久井渓谷観光協会合作の「武相国境観光地図」(1938年発行)の例に見られる。仮説①②の科学的解明には、江戸期、明治期の使用字句の数量分析が必須であるものの、当時の和文の印刷物化が2%程度の状況では困難であり、文献分析は補足的なものとならざるを得ず、当面はデータベース化された新聞記事検索に頼らざるを得ない。今後のGoogle、Amazonに代表される文献検索システムの進展に期待するところである。
6 公的出版物等における字句「観光」等の使用方法
国際観光局及びジャパン・ツーリスト・ビューロー発行の観光案内書では、総じて遊覧が使用されているが、回遊、周遊、観光、視察等も使われており、用語使用に統一性がない。ただ、1930年代後半には地方観光協会を中心に日本人の国内向けにも字句「観光」を使用することが一般化する傾向がみられた。
内閣法制局参事官経験者の柳田国男は国内用の遊覧と外客用の観光の字句を使い分けている。その影響を受けている宇田正は「観光という言葉がこのときわが国鉄道業界で初めて用いられ、しかもそれは「国際」という限定をともなうもの」「昭和10年代に入ると、国内旅行でありながら観光の字句表現が用いられようになるのが興味ふかい」『鉄道日本文化史考』(思文閣出版2007年)と記述する。
7 新聞記事検索における字句の用例
朝日及び読売新聞記事検索結果では、発行当初は字句「遊覧」が主流であった。国際観光局設立とともに字句「観光」が増加し、しかも越境概念を前提とするものが大半であった。1930年代後半になると、国内旅行を意味するものも増加する傾向を見せたものの、建前にまで昇華しないうちに戦争期に突入し、観光概念の内外無差別使用は戦後の経済復興期を待たなければならなかった。この結果は仮説②をほぼ裏付けるものとなっているが、社会全体の数量分析としては完全なものとは言い切れない状態である。
朝日及び読売新聞における「ツーリズム」の用例は戦前期においては皆無であった。昭和戦後期の用例も、読売新聞は1962年「ソーシャル・ツーリズム」及び1964年「産業観光(テクニカル・ツーリズム)」の2件、朝日新聞は5件であった。増加するのは21世紀に入ってからであるが(読売4千件弱)「観光」のヒット数は2011年以降だけでも六万件(読売)を超えている。
8 「内主外従」の地域観光行政
大正末期から昭和初期にかけて地方観光協会が急増した。1897年に古社寺保存法が制定され、観光協会とは別に保勝会等も既に設立されていた。1915年に史蹟名勝天然記念物保存協会が設置され、「国光」を発揚する記述がみられる。1930年代半ば以降風致協会も全国に広まった。1935年には全国に設置された観光協会が400を超え、全日本観光連盟が設立された。建前としては外客誘致団体ではあるが、外客誘致の為の観光事業の整備は国内事業であり、事実上日本人の遊覧の用にも供されるものであった。東京府においても、建設局自然公園課において観光行政を所管するとともに、観光事業の振興を図ることを目的として1936年に東京府観光協会が設置された。設立趣意書には「観光事業はこれを外にしては国際修交に資し、これを内にしては国民の保健と強化に裨益する所大」となっている。同協会が発行した「観光の東京府」一号に掲載されている東京府知事の発刊の辞には「観光事業は国際親善の増進、国情文化の宣揚、国際貸借の改善、貿易の進展及び国家意識の確立等国際的重大使命を有するとともに、これを内にしては知見情操の涵養、体力の増進等に貢献する処大なるものあり」と記述されており、建前としての国際をもっぱらとする観光政策の実施機関としてのありかたを打ち出している。
9 字句「余暇」「レクリエーション」の登場と国内観光政策への影響
1940年予定のオリンピックとともに「国際レクリエーション大会」(当初は社会問題から発生した概念「余暇」を用いた「余暇善用大会」)が検討され、厚生省設置後は「レクリエーション」は「厚生」と訳された。地方観光協会においても、時局がら使用がはばかられる娯楽等の字句に変わって、字句「厚生」の衣のもとハイキング等を強調するように変化していった。
戦後、法令上は定義ができないとされた字句「観光」は、文部行政、厚生行政文書に登場することはなく、運輸省所管事務の「運輸に関する観光」と対比される形で、厚生行政においては国民宿舎等に具体化されるソーシャル・ツーリズム、文部行政においてはレクリエーション・スポーツ等が戦前を引きずる形で強調されることとなった。字句「観光」を使用した形での国内政策が進展しなかった事情として、自民党及び社会党の55年体制下においては「休日問題」が論議の対象外とされたこと、厚生省所管の旅館業法のもと、国際観光登録旅館制度が完全に形骸化したこと、総合的余暇政策としては初めての制度化であったリゾート法への観光政策研究者の制度的評価の深度化が進展しなかったこと等と相まって、戦前、戦中、戦後を連続してとらまえる観光政策研究が進展しなかったことが考えられる。
関連記事
-
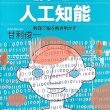
-
『脳・心・人工知能』甘利俊一著講談社BLUEBACKS メモ
AIの基本技術は深層学習とそれに付随して強化学習 そのあと出現した生成AI
-

-
観光で中国に追い抜かれる日 Space tourism not far off, rocket maker says
CHINADAILYの記事 2000万円払えばだれでも2028年に宇宙観光ができる予定 h
-

-
新疆ウィグル自治区をネタにするYoutuber old medea もYoutubeも変わらない
旅系YoutubeRも右翼嫌中派YoutubeRも、ウィグルをネタに再生数稼ぎをしている点では変わり
-

-
定住(観光の逆)と言語のことをわかりやすく説明した対談 (池谷裕二(脳科学者)×出口治明(ライフネット生命会長))
出口:動物行動学者の岡ノ谷一夫氏に、言語はコミュニケーションから始まったのではなく、考えるツールとし
-

-
英和対訳袖珍辞書と観光
先週は都立中央図書館が図書整理のため休館日が続き、ようやく土曜日(6月13日)に閲覧に行くことができ
-

-
二月五日チームネクスト総会講演「総合生活移動産業の今後の展望」(45分)趣旨 人流・観光研究所長 寺前秀一
二月五日チームネクスト総会講演「総合生活移動産業の今後の展望」(45分)趣旨 人流・観光研究所長
-

-
The basic viewpoint of discussing Human Logistics and Tourism
In the process of studying Tourism Studies, consid
-

-
動画で考える人流観光学講義(開志) 2023.11.27 将来の観光資源
◎ 科学技術の進展による観光資源の拡大 ◎ 宇宙旅行 自らの目で見た風景を表そうとすると、遠くを
-

-
ロシア人以外の人が北方領土を訪問する場合のロシア政府に対する手続きを教えてください。
国後島や択捉島、極東・沿海地方結ぶ“初のクルーズツアー”をロシア政府

