『近代京都研究』から見る「遊覧」と「観光」に関するメモ
公開日:
:
最終更新日:2016/11/25
人流 観光 ツーリズム ツーリスト
『近代京都研究』(2008年思文閣出版)において、観光に関する記述とともに「観光」「遊覧」の用例として参考になるものをメモしておいた。
(p.148)1873年第二回京都博覧会に発行された外国人向けガイドブック(The Guide to Celebrated Places in Kiyoto & the Surrounding Places for the Foreign Visitors)ではvisitorが使用されている。
(p.154)1881年に岩倉具視が中心になり、京都や近畿地方の名勝・古蹟を保存しようとする保勝会をつくった。
(p.159)おそらく第4回内国博覧会において、京都の社寺が拝観料をとって観光化する契機になった。
江戸で幕末に品種改良によりつくりだされたソメイヨシノは、いつ京都に植樹されたか 1895年の遷都千百年記念事業の鴨東開発以降、実際には20世紀になってからである。京都の桜も新しいのである。
明治6年の内務省設置により名所旧蹟は同省の所管となる。1919年史蹟名勝天然記念物保存法が制定。『明治14年創立 保勝会一覧』(1929年 保勝会編)には笠置保存会、安国寺保勝会、宮津保勝会。
高瀬川 史蹟名勝の指定は行われず、都市計画法との正面切った衝突は回避されている。史蹟名勝的価値をもった高瀬川が今日まで残されたことは京都にっとて幸いであったが、史蹟名勝天然記念物保存法の限界もそこにあった。高瀬川一之舟入は1934年史蹟指定された。
「御大典記念事業にみる観光振興主体の変遷」工藤泰子
近代における京都は、博覧会を通して「甦生京都を紹介宣伝し、我が国第一の観光都市」と京都博覧会協会が後に回顧
「世界的観光都市」が多用されるようになってゆく。
1913年京都市主催の大正大礼博開催が決定され、観光客(当時は「来遊客」)誘致を狙う。
大正末期から昭和初期にかけて全国の観光機関が急増 1933年その数328件(国際観光局「外客誘致の話」1932年)。しかしながらその多くが地元有志・会員からなる保勝会(保勝協会)や観光協会であり、地方自治体の行政組織の中に「観光課」として組み込まれていたものは京都市観光課の他には日光町観光課(1931年4月)熱海町観光課(1931年8月)宇治町観光課(1932年4月)奈良市観光課(1933年4月)のわずか5件であった。
(p.237)1934年「観光都市」の語は当時常套句となっていたが、それ以前には「日本ノ公園」「遊覧都市」という形容が一般的であった。
(p.240)二度目の御大典(1928年)を迎えるが、入込見込みと現実とに大きなギャップ。ジャパンツーリストビューロが斡旋した外国人奉拝者は、11月7日54人、26日38人。京都側の受け入れ態勢の不十分さによって旅行希望者が入洛を敬遠。鉄道省が売れる見込みで発行した50万枚の大礼記念回遊券が116枚しか売れなかった。
1930年市議会の発言 「遊覧都市トシテノ真価ヲ発揮スル為ニ観光課ヲ新設」
1935年 遊覧都市を観光都市に改める
遷都千百年記念祭、第4回内国勧業博覧会にはじまり、二度の御大典が観光課設置の引き金になったという解説。1930年国際観光局設置の影響の方が大きいのではないか?
関連記事
-

-
Analysis and Future Considerations on Increasing Chinese Travelers and International Travel & Human Logistics Market ⑩
Ⅸ Future direction of human flows and sightseeing
-

-
🌍🎒2024シニアバックパッカー地球一周の旅 2024.2.15 DLA カメルーン(トランジット)
昨年に引き続きDLAに。前回は空港で陰性検査を受け、2泊したが、今回はトランジットで空港内に滞在。カ
-
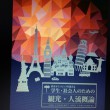
-
東京オリンピックを迎える学生・社会人のための観光・人流概論
新しい教科書を出版しました。私はこれまで観光政策論等を中心に出版してきま
-

-
孫建軍著『近代日本語の起源』に見る用語「国際」の誕生
用語「観光」を論じるにあたって、国際との関係をこれまで考察してきたが、考えてみると、日本人社会のなか
-

-
AIにきく イルクーツク、ヤクーツク、ウラジオストックの旅
東京から、イルクーツク、ヤクーツク、ウラン
-

-
上田卓爾「明治期を主とした「海外観光旅行」について」名古屋外国語大学現代国際学部 紀要第6号2010年3月を読んで
上田氏の資料に基づく考察には鋭いものがあり、観光とTOURISMの関係についての議論を発展させる意味
-
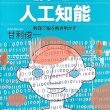
-
『脳・心・人工知能』甘利俊一著講談社BLUEBACKS メモ
AIの基本技術は深層学習とそれに付随して強化学習 そのあと出現した生成AI
-
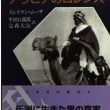
-
シリア、リビア旅行前によむ『アラブが見たアラビアのロレンス』
日本人の一般的な英国のイメージは、映画「アラビアのロレンス」に代表されるポジティヴなものであ
-

-
重慶旅行 重慶の大きさ
https://www.facebook.com/share/1G31QjFCF1/?mibexti


