2015年1月16日ジャパン・ナウ観光情報協会 観光立国セミナー 用語「観光」について
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
ジャパンナウ観光情報協会, 人流 観光 ツーリズム ツーリスト
本日は、観光とツーリズムをめぐって論議をさせてもらっている溝口周道氏の講演でした。
やはり期待通りの講演内容で、とくに江戸時代以前の日本における字句「観光」に関する知見は日本で第一人者でしょう。もちろん易経等に関する学識も、日本の観光学者の中では最高級ではないかと思われます。日本には易の専門家や中国古典の専門家もおられますが、字句「観光」に関する問題意識を持った方はあまりおられないでしょうから、是非出版物にして世に発表いただければと思います。原点にあたるという意味では、易経の原点は碑文かなにかだと思われますので、是非そのツアーも企画してみたいと思います。また、「観」の字句ついても掘り下げて、発音(四声だけではなくもっと多様な発音があったのかもしれません)も含めて研究が進むと面白いかもしれません。
さて、現代用語の「観光」との関係になりますが、我が国に「ツーリスト」概念が西洋から入ってきたとき、他の概念と異なり、しばらく「ツーリスト」が用いられていました。一方溝口氏の説明によれば1680年に「観光亭記」として普通名詞化した観光が使用されているとのことでした(勿論ツーリスト概念とは異なるでしょうが)。いずれにしろ普通名詞としての字句「観光」が字句「ツーリスト」到来前に日本に存在し、時間を経て概念も変化させることにより相互に訳語となっていったということになるわけです(ツーリズムではないことに注意してください)(注1)。溝口氏の解説では薄田泣菫や山田寅之助が今日的な意味での字句「観光」を使用している例を示されています。また、観光の使用例から、特定の対象を見ることではないとされる点は、「旅程と費用概算」を見る限りは「観光場所」の欄に具体的な場所が示されていますから、溝口氏の説明では矛盾する点もありますから、数量分析等さらなる調査が必要でしょう。なお「観光のための移動は必然として生じるもの」という理解は、現代ではヴァーチャルもあり得るように、当時も絵画等であり得たのではと思われ、そのような使用例が皆無なのか気になるところでした。
1930年代、視察と観光を区別するようになったという説明も大変興味深いものでした。聞蔵やヨミダスで真偽を確認してみたいと思います(注2)が、現代でも視察と観光が区別できるのか疑問もあり、私は人流を提唱しているのです。つまり何のために観光を論じるのかということを考えると、当時も現代もさほど変わらないと思っているのです。
注1)1930年時点では京都市における用例では「遊覧客」でありましたが、1935年時点では「観光客」に変化しています(『近代京都研究』)。この時期あたりから先進地域京都では日本人の国内移動にも字句「観光」を明確に意識して用い始めたといえるかもしれませんが、残念ながらその後の厚生省の設立や戦時体制への移行により、観光概念が完全に国内を含むものと認識されるようになったのは戦後の復興期を待たなければならなかったのではないかと思われます。
注2)視察及び観光が同じ記事の中で同時に使用されている用例の聞蔵検索では、平成前の用例では120件ヒットしました。うち戦後のものは18件でほとんどが戦前の国際に関わるものでした。初出の1897年4月16日東京朝日新聞朝刊では見出しが「外人観光」、本文は「わが帝国の軍事視察」とあり、区別はしていないようです。1902年7月23日では外国人に「観光」日本人に「視察」と使い分けています。1906年9月12日ろせつた丸巡遊所感では「満韓視察」「観光漫遊」「利源調査」と使い分けています。同年9月26日「我が国経済界の実情視察かたがた観光の為」1909年8月16日見出しは逆に視察団、本文は観光団、1910年4月16日等の「清国観光団の視察」と区別されていないものが多く散見されます。最後の用例は1983年10月26日「観光先進地が視察攻め 清里高原」と区別しているようで区別されていない例でした。ヨミダスでの検索においては、ヨミダスのキーワード整理が不徹底であり、観光と視察の分類が不明確であることから分析には利用できないレベルのものでありました。しかしその中でも、1902年7月10日の東京読売朝刊のラマ教貫主が「視察し観光もなされ」と記述されているものは区別をしている数少ない例でありました。逆に1909年6月28日の記事は「大阪商船会社の催しにかかる瀬戸内海観光団、視察する」と区別されていない用例も存在しました。
溝口氏の講演の中で、戦前期、日本人の国内移動にも字句「観光」が使用された例が示されましたが、この点は、用語概念が確立していない時期における言葉の使用頻度と概念の確立に関わることですから、数量分析も必要でしょう。国際にしか使用されない例、国内にしか使用されない例、両者に渡って使用される例を総合的に分析して判断するべきでしょう。従って論点は、もともと内外無差別であったのか、途中で意味が拡大していったのか、拡大していったとしてその時点はいつごろかという問題になるのでしょう。日本にはもともと現代流の観光概念がない(私は今でもないのではと思っているくらいです)のですが、ツーリスト概念が入り込んで、いつの間にか遊覧ではなく観光が主流になっていったと思っていますから、どうしても外客概念と結びついて発生しているはずだと思っています。とくに政策面では間違いないと思っています。そしてその完全な確立時点は、戦後の占領時期ではないかという仮説を聞蔵、ヨミダス等の分析により立てています。溝口氏の用例の指摘は大変参考になります。私が思っているよりも早くに国内が含まれるように一般化したのかもしれませんが、戦争により実態がなくなり、あるいは建前として存在を否定せざるを得なくなり、戦後に復活したのかもしれません。現代字句「携帯」がすごいスピードで字句「スマホ」にとってかわられています。そのうちに両者の定義が問題になるでしょう。言葉は生き物ですから面白いのですが、何のために論じるのかという視点をわすれないにしたいものです。
関連記事
-

-
概念「「楽しみ」のための旅」と字句「観光」の遭遇 Encounter of the concept “Travel for pleasure” and the Japanese word “KANKO(観光)”(日本観光研究学会 2016年度秋期大会論文掲載予定原稿)
「「楽しみ」のための旅」概念を表現する字句が、いつごろから発生し、どのように変化していったかを、「「
-

-
奢侈禁止令とGOTOキャンペーン (ジャパンナウ原稿)
個性を重視するはずのものである観光は、本来権力とは無縁であり、権力を前提とする政策と結びついた観
-
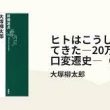
-
『ヒトはこうして増えてきた』大塚龍太郎 新潮社
p.85 定住と農耕 1万2千年前 500万人 祭祀に農耕が始まった西アジアの発掘調査で明らかにさ
-

-
ジャパンナウ第百号原稿 中国を中心とした観光社会の予感
ジャパンナウ観光情報協会の情報誌も今回で百号になります。私も「NPOから提言しま
-

-
箱根について 藤田観光元会長の森本昌憲氏の話を聞いた結果のメモ書き ジャパンナウセミナー
2017年10月13日ジャパンナウ観光情報協会の観光立国セミナーで森本氏の話を聞く。日本ホテル・レス
-

-
読売新聞、朝日新聞記事に見る字句「ツーリズム」「観光」の用例
読売新聞の記事データベース「ヨミダス」及び朝日新聞の記事データベース「聞蔵Ⅱ」を活用して「ツーリスト
-

-
観光概論にみる字句「観光」の説明
有栖川図書館で観光の書籍を読む。大橋昭一氏の関係する書籍が開架式の棚に何冊かあり読む。 大橋著『
-

-
動画で考える人流観光学講義(開志) 2023.11.27 将来の観光資源
◎ 科学技術の進展による観光資源の拡大 ◎ 宇宙旅行 自らの目で見た風景を表そうとすると、遠くを
-

-
「衣食足りて礼節」をあらためて知る(2014年5月)
クールJapan戦略のため日本社会のCOOLな部分が取り上げられる機会が多くなりました。中国製品との
-

-
🌍👜台湾のこと(高寛氏の講演)
台湾協会の理事高寛氏の話を聞いた。元三井物産台湾支店長を務めた方である。若い頃、中国語を教えてもらっ


