総理所信表明演説に登場した「人流」と旅主概念への期待 JN10月号原稿
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
ジャパンナウ観光情報協会, 人流 観光 ツーリズム ツーリスト
岸田総理は「人流」規制を行う法改正を趣旨とする所信表明演説を行った。前世紀末橋本内閣時の閣議決定「物流施策大綱」を想起させる。物流が無駄な動きや在庫を減少させる概念であり、利用者(荷主)の利益にかなうものであることは前回既述した。これに対して人流概念がこれまで未発達だったのは、荷主に該当する旅主(利用者)が主体的な力を持ちえなかったからである。辛うじて大手旅行業が、運送業者や宿泊(滞在)業者に対して利用者の代理者として存在したが、各種運送事業法の規制を合法的に弾力化できる旅行業法の活用(企画旅行や利用運送、利用宿泊)の不徹底もあり、社会的、経済的な旅主機能が発揮されてこなかった。これに対して、欧米や中国等では、ITを駆使した、Uber、滴々(DiDi)、Airbnb、Trip.com等が急激に発達し、旅主ニーズを先取りしたビジネスをグローバルに展開し、自家用と営業用の相対化を反映した、家交換型の旅行仲介サービスを運営するHome Exchangeや不動産仲介業のサイトも成長している。
岸田総理は「新たなビジネス、産業の創出」を唱えている。日本の世界GDPに占める割合は1994年18%が2020年6%にまで落ちた。アベノミクスの目標は2020年度GDP600兆円であったが、2007年度レベルの536兆円に留まっている。日本経済の基盤産業力を落とした人流関連の実例として、国産ワクチンが作れなかったこと、MRJ旅客機が頓挫したことが象徴的に挙げられる。7~9月期のGDP速報は年率換算で22・9%増と回復堅調だが、平均給与が最も低い宿泊業・飲食サービス業は前年260万円が251万円に落ち込み、賞与は20万円→13万円であった。「観光立国復活に向けた観光業支援」も演説されているが、コロナ禍でも物流は発展している。物流では、荷主(利用者)は無駄な運送や在庫を嫌い、代替効果がビルトインされているが、人流では、運送会社や宿泊(滞在)業者が発想する限り代替効果を狙うことは期待できない。観光概念から脱却し、無駄な動きや滞在を抑制する人流概念への意識の転換が必要である。
人口減少は年間百万人を超えることから、観光・レクリエーション目的の国内宿泊旅行延べ人数は2013年の1.76億人から、2040年には1.49億人程度まで減少すると見られている。同時に就労環境も変化し、外国人労働者の年増加10万人程度では追い付かず、従業員離職は不補充が原則となり、テレワークやロボット化による効率化が必須となる。生産性の低い「紙とハンコ」「対面コミュニケーション」に依存した事務仕事、つまり日本式オフィスワークは、国際比較においてコストを発生させるだけで、経済の足を引っ張っているとみられている。セミナー産業が提供する社会人向けのものはオンラインで十分である。限られた人生時間の元気で有効な活用を希望する旅主のため、無駄な移動や滞在を回避した効率的なサービスを提供することが人流産業の使命であり、付加価値を高める王道であろう。
関連記事
-

-
Human Logisticsの提唱
中国東北財形大学準教崔衛華さんが、私の博士論文がベースになっている『観光政策学』(イープシロ
-

-
2022年8月ジャパンナウ観光情報協会原稿 アフターコロナという名の観光論 原稿資料
◎ジャパンナウ原稿案 2020年冬から始まった新型感染症は日本の人流・観光業界に
-

-
早川書房の「誰が音楽をタダにした」の概要を教えてください
早川書房の「誰が音楽をタダにした」の概要を教えてください
-
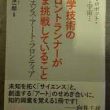
-
冒険遺伝子(移動しようとする遺伝子) 『科学技術のフロントランナーがいま挑戦していること』川口淳一郎監修
P.192 高井研 ドーパミンD4受容体7Rという遺伝子 一時期「冒険遺伝子」として注目された
-
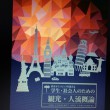
-
東京オリンピックを迎える学生・社会人のための観光・人流概論
新しい教科書を出版しました。私はこれまで観光政策論等を中心に出版してきま
-

-
シニアバックパッカーの旅 ジャパンナウ原稿2019年11月 太平洋島嶼国等の観光政策
ラグビーのワールドカップ戦を偶然サモアでむかえた。現地は日本時間より五時間早く、開始時間は深夜。
-

-
ジャパンナウ予定原稿 感情と観光行動
観光資源に対して観光客に移動という行動をおこさせるものが感情である。言葉を換えれば刺激であ

