中国語の中の日本語(Chinese Borrowings from the Japanese Language) 陳 生保(Chen Sheng Bao) 上海外国語大学教授
公開日:
:
最終更新日:2023/05/29
出版・講義資料
中国語の中の日本語(Chinese Borrowings from the Japanese Language)
陳 生保(Chen Sheng Bao) 上海外国語大学教授
はじめに
「共産党 幹部 指導 社会主義 市場 経済」 という文は、すべて日本製漢語語彙でできているといったら、こ れらの語彙をさかんに使っている普通の中国人は信じかねるだろうし、これらの語彙の原産地の日本人も、たぶん半信半疑だろうが、しかし、それは事実である。私が十年前にこれまでの先行研究をふまえてまとめた「中国語の中の日本語」 は、その間の消息を伝えている。
現在、日本語は毎年一万語(その多くは音訳による外来語だろうが) のペースで新語が増えているそうである。ところが、二千年の長きにわたって中国語の中に入った外来語は、たったの一万語にすぎない。そして、そのほぼ一割に当たる千語の外来語は、日本製漢語語彙なのである。
千語ぐらいといえば、多くはないと思われるかもしれないが、しかし、ほかの九割には 「仏陀」 など、仏教からの外来語が多く、死語に近いものがかなりあるし、日本語来源の語彙のほとんどは現代生活に欠かせない基本的概念であり、使用頻度の高いものであり、しかも造語力のあるものが多い、ということを考えると、現代中国語における日本来源語の影響が非常に大きいといわねばならない。
、日本留学ブーム
日本語のなかに古代の中国語から来た語彙がいっぱいある。それと同じように、現代中国語にも日本語がたくさん入って住みついている。これらの日本語は十九世紀の末ごろから中国語のなかに入ったのである。
清の末期、中国の国勢が急速に衰えた。特に鴉片(あへん)戦争以後、中国は各列強の侵略の対象となり、次第に半ば殖民地化していった。中国人は亡国の危機感に襲われ、愛国の志士たちは、痛ましい現実に目ざめて、国を救う道をさがし求めていた。隣国の日本が明治維新後まもなく資本主義の軌道に乗るようになったのを見て、康有為・梁啓超を代表とする中国の一部のインテリが、中国も日本に倣って維新することを主張し出した。一八九八年に起こった戊戌変法(ぼじゅつへんぽう)は、ほかでもなく日本の明治維新の影響によるものだったのである。戊戌変法は結局失敗に終ったが、その指導者の一人である梁啓超が日本に亡命し、横浜で新聞 『清議報』 と雑誌 『新民叢報』 を出版し
、続けて中国の維新を鼓吹した。そして、彼の新聞、雑誌には日本の事が盛んに紹介され、日本語の語彙がたくさん使われていた。梁氏はまた 『日本語を学ぶ利益を論ず』 という文章をしたためて、中国人に日本語を学び、日本の本を読むように呼びかけたのである。
第一陣の中国留学生が日本入りしたのは、一八九六年のことで、十三名だった。それが年とともに増えた。
例えば 一九〇一年 二八〇名
一九〇四年 一三〇〇名以上
一九〇五年 八〇〇〇名
統計によると、八千名は最高記録だったがこうした日本留学ブームは一九三七年の、中国に対する日本帝国主義の全面的な侵略戦争の爆発まで続いた。
一九三六年六月一日当時の在日中国留学生は五八三四人だったが、戦争開始後、みな中国に引き揚げた。一八九六年から一九三七年までの足かけ四十二年の間における中国人の日本留学生の数は、合わせて六一二三〇名に達している。そのなかで学校を卒業したものは一一八一七名である。
中国で最初に出版された『共産党宣言』は、日本語版から翻訳されたのである。訳者は、今は亡き元上海復旦大学学長・陳望道氏である。
おびただしい日本の本が中国語に訳され、出版される一方、他方では留学生たちが日本書を読んだ影響で自分の文章にたくさんの日本語を引用した。そのほかに当時の日本は中国、とくに上海で多くの新聞・雑誌を刊行していた。こうして大量の日本語が中国語のなかにどっと入りこんだ。もちろん日本語といっても日本語の語彙が主で、表現法も少々入った。
はじめのころは、日本の訳語と厳復らがつくった訳語が共存した。例をあげてみよう。
「Economics」 という英語は日本語で 「経済学」 と訳されているが、それにはとても抵抗を感じたようである。なぜなら 「経済」 ということばはもともと中国の古語であり、「経世済民」 の意である。「経世済民」 とは世の 中を治め、人民の苦しみを救うことである。現代語におきかえるならば大体 「政治」 という語に相当するからである。現に竹下登前首相の 「経世会」 は 「経世済民」 という言葉をふまえたように思われる。いうまでもなく、それは政治家のグループであって、経済の組織ではない。そのため厳復は 「計学」 と訳し、梁啓超は 「資生学」 または 「富国学」 「平準学」 という訳語を使った。ちなみに 「平準」 は 『史記』 に出ている言葉で、物の安いときに官が買い入れ、高いときにそれを売り出して物価を調節する制度で、前漢の武帝に始まる。そのほか 「哲学」 (Philosophy) は 「理学」 「智学」 と共存し、「社会学」 (Sociologie) (仏語) は 「群学」 と共存した。
日本来源の語に対する研究
清の末期、日本留学ブームがでてから、日本語の語彙集、辞書類、教科書などが数多く出版されたとはいえ、中国語の中の日本語に対する研究が本格的に行われるようになったのは、新中国になってからである。つまり中国語の規範化と文字改革を進めるために、中国語の中の外来語を今後どうするかという問題に直面したのである。そのためにはまず中国語の中の外国語の状況を明らかにする必要があった。一九五八年、中国の有名な言語学者高名凱・劉正王炎の 『現代漢語の中の外来語研究』、王立達の『現代漢語中日本語から借りて来た語彙』 を皮切りに、中国語の中の外来語が研究され、一九八四年には『漢語外来語辞典』 が出版された。
「現代漢語の語彙に対する日本語の影響はたいへん大きい。現代漢語における外来語の主要なるものは日本語から来ている。日本語は漢語外来語の最大の源だといっても過言ではないだろう。おびただしい数にのぼる西洋語のほとんどは、日本語を通じて現代漢語の中に導入されたのである」。その影響を具体的にいうと、次の三点が挙げられる。
(一)、中国語の語彙の複音化のテンポを早めた。
中国の古代語 (日本でいう漢文) にも、二つまたは二つ以上の文字でできた語彙も少々あることはあるが、非常に少ない。ほとんどは一つの文字が一つの語彙になるのである。語彙の複音化、つまり二つまたは二つ以上の文字で一つの語をつくることは、中国語が古代語から現代語へ脱皮する過程での趨勢だが、日本語をはじめとする外来語の進出によってその脱皮のテンポが早められたといえる。
(二)、語の複音化によって語義が細くなり、表現がいっそう緻密になり、正確になった。
例えば、「行」 という語は古語では 「行く」 「走る」 「行為」 「行動」 「行進」 などの意を有する多義語だったが、現代漢語では複音化によって、いくつかの語ができ、表現がもっと的確になった。
(三)、西洋的な表現がたくさん入り、中国語のセンテンスが長くなった。
新語の大量導入、語の複音化と表現の緻密化、長文の活用など、これらはいずれも古代漢語から現代漢語への脱皮であり、中国語の進歩である。こうした中国語の進歩は、世界各国の進んだ文化の吸収、はては中国の現代化実現に役立つものであろう。
日本語の場合も同じようなことがある。辞書によって多少差はあるが、日本語の語彙は、今でも半分ぐらいは 漢語語彙だそうである。その大部分は古代中国語から来たものであり、その一部分は日本でつくられたものである。しかし、日本人は中国来源の漢語語彙を外来語だと、まったく見なしていないし、それが中国からのことば だと意識する人も、非常に限られているだろう。これはなんと不思議な現象だろう。
もう一つおもしろいことがある。同じ書き方のことばでも、その読み方は中国人と日本人でぜんぜん違う。例えば 「哲学」 ということば-これはギリシャ語 「Philosophia」 の意訳語だが、中国人は 「zheque」 と読み、日本人は 「Tetugaku」 (てつがく) と読む。読み方がそれぞれ違っていても、同じ意味で理解する。そして中国人も日本人も、それを外来語と見なさない。こういう現象は、たぶん漢字文化圏内、とくに中日両国間にしかないものであろう。
以上述べたことは、中日両国間の文化交流の歴史の長いことと影響の深いことを、あますところなく立証していると思う。
関連記事
-

-
ヨーロッパを見る視角 阿部謹也 岩波 1996 日本にキリスト教が普及しなかった理由の解説もある。
キリスト教の信仰では現世の富を以て暮らす死後の世界はあ
-

-
2016年7月29日「ファイナンスの哲学」多摩大学特任教授堀内勉氏の講演を聞いて
資本主義の教養学公開講座が国際文化会館で開催、場所が近くなので参加してみた。 1 資本主義研究
-

-
塩野七生著『ルネサンスとは何であったのか』
後にキリスト教が一神教であることを明確にした段階で、他は邪教 犯した罪ごとに罰則を定める 一
-
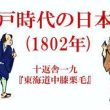
-
『日本語スタンダードの歴史』野村剛士は、「日本の話しことばについて」『現代国語三』所収 木下順二著1963年を否定
私の自説に、日常と非日常が相対化しており、観光資源もあいまいになってきているというアイデアがある
-
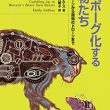
-
『サイボーグ化する動物たち 生命の操作は人類に何をもたらすか』作者:エミリー・アンテス 翻訳:西田美緒子 白揚社
DNAの塩基配列が読破されても、その配列の持つ意味が分からなければ解読したことにはならない。本書の冒
-

-
『外国人労働者をどう受け入れるか』NHK取材班を読んで
日本とアジアの賃金格差は年々縮まり上海などの大都市は日本の田舎を凌駕している。そうした時代を読み違え
-

-
『一人暮らしの戦後史』 岩波新書 を読んで
港図書館で『一人暮らしの戦後史』を借りて読んでみた。最近の本かと思いきや1975年発行であった。
-

-
明治維新の評価 『経済改革としての明治維新』武田知弘著
明治時代の日本は世界史的に見て非常に稀有な存在である。19世紀後半、日本だけが欧米列強に対抗し
-
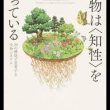
-
保護中: 『植物は知性を持っている』ステファノ・マンクーゾ 動物と植物は5億年前に進化の枝を分かち、動物は他の動植物を探して食べることで栄養を摂取する「移動」、植物は与えられた環境から栄養を引き出す「定住」、を選択した。このことが体構造の違いまでもたらしたらしい。「目で見る能力」ではなく、「光を知覚する能力」と考えれば、植物は視覚を持つ
植物は「動く」 著者は、イタリア人の植物生理学者ステファノ・マンクーゾである。フィレンツェ大学国際
-
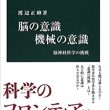
-
『脳の意識 機械の意識』渡辺正峰著 人間は右脳と左脳の2つを持ち,その一方のみでも意識をもつことは確かなので,意識を持っていることが確実である自分自身の一方の脳を機械で作った脳に置き換えて,両脳がある場合と同じように統一された意識が再生されれば,機械は意識を持ちうると結論できる.
Amazon 物質と電気的・化学的反応の集合体にすぎない脳から、なぜ意識は生まれるのか―。多くの

