『新・韓国現代史』 文京洙著 岩波書店 を読んで、日韓観光を考える。
東アジアの伝統的秩序は、中国中心の華夷理念のもとに、東アジアの近隣諸国が朝貢・冊封の関係において秩序付けられた世界であることは通説化しているから日韓双方が理解しやすい。
面白いのは、日本も朝鮮も小中華思想であったとすることである。司馬遼太郎の「街道をゆく」では朝鮮の小中華思想が近代化の妨げになったことが記述されているが、
どうも日本も日本型華夷思想であったから、すべてが小中華思想ということでもなさそうである。日本型小中華思想とは、日本を中心に琉球、アイヌ、中国、オランダ等を夷としてとらえる体制であると著者はいう。
日本型の工夫がみられるところは、朝鮮国王と徳川将軍は対等とし、将軍の上に天皇を置くことにより、、日本は朝鮮を一等下とみなすということである。意識的にそうなったのかまではわからないが、著者は主張している。
一方、朝鮮側も小中華思想であり、明の滅亡後中華文明の伝統は朝鮮が維持という文化的優越意識を強化し、羈縻政策の対象として日本を一等下においたとするから、著者は公平に見ているように思える。
さて、帝国主義の時代であるが、日本は、イギリスと日英同盟締結でイギリスのインド権益、日本の朝鮮権益を相互に認めあった。アメリカとはフィリピンをみとめ、日仏協定を結び、列強承認のもと朝鮮の植民地化を断行したと認識されている。この点もバランス感覚があると認識される。
人口流出の最も激しかったのは済州島であった。1930年代半ばには四分の一が日本にわたったようである。「四・三事件」では48年当時の済州島人口28万人の一割近くが犠牲になったとあるからすさまじい。沖縄と比較されることがあることも理解できる。朝鮮戦争の犠牲者を考えれば、韓国国民の意識が日本人とは異なることくらいは理解しておかなければならないであろう。また日本人の朝鮮観は在日を念頭においてものである(鄭大均)。また、左翼や革新を含め日本人の大半が李承晩独裁体制への反発からの朝鮮人感が形成された。
日韓条約が締結され、韓国経済のテイクオフがはじまった。アメリカ外資が半分、日本は四分の一の11億ドルであるから、アメリカが中心であったことは認識しておかなければならないであろう。
植民地支配の評価は当然対立する。今でも日本の植民地時代の投資を評価する見解が時折日本人からなされるが、その原点は「久保田発言」であり、5年間の中断が引き起こされたようだ。
太陽政策は鄭周水の金剛山観光を引き起こしたことは日本でも知られている。ハングル世代は『克日。』支配国たる日本以上に強い国にということである。光州事件の衝撃は反米色の強い国へと変化させた。日本はアメリカの従属的同盟者とになされ、妓生観光への反発から、経済侵略、文化侵略が意識された。
1994年に出版された『日本はある』の著者徐氏は日本大使館勤務時代に一緒に旅行したことがある人で懐かしい。
島根県議会が「竹島の日」えを制定し、扶桑社の歴史教科書問題が親日真相糾明法案を成立させてしまった。対日批判の社会的気運が盛り上がった。
韓国のニューライトは日本からほぼ十年遅れで発生。韓国版歴史修正主義や自虐史観などの非難用語も借り物が多いとのこと。
断片的にめもったが、歴史認識を観光資源にする際の参考にしたい。
関連記事
-

-
太平洋戦争で日本が使用した総費用がQuoraにでていた
太平洋戦争で、日本が使った総費用はいくらでしょうか?Matsuoka Daichi, 九州大学で経
-

-
「米中関係の行方と日本に及ぼす影響」高原明生 学士會会報No.939 pp26-37
金日成も金正日も金正恩も「朝鮮半島統一後も在韓米軍はいてもよい」と述べたこと 中国支配を恐れてい
-

-
遠くない未来、学問は人間が理解するものではなくなる(かも)【ゆっくり科学】
https://www.youtube.com/watch?v=yCIxsaLg
-
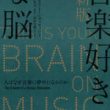
-
『音楽好きな脳』レヴィティン 『変化の旋律』エリザベス・タターン
キューバをはじめ駆け足でカリブ海の一部を回ってきて、音楽と観光について改めて認識を深めることができた
-

-
ドナルド・トランプが大統領になる5つの理由を教えよう
https://www.huffingtonpost.jp/michael-moore/5-rea
-

-
Quora6に見る歴史認識 イギリスが中国にアヘンを売ったのは有名です。あるイギリス人の言い訳が、アヘンを売り始めた頃中国には麻薬の売買を禁止する法律が無かったから問題ない。これ真実ですか?それにしても犯罪者の理屈ですよね?
アヘン戦争に対する一般的なイメージ。それは以下の様なモノです。 「大英帝国が清国を麻
-

-
ここまで進化したのか 『ロボットの動き』動画
https://youtu.be/fn3KWM1kuAw
-

-
「キャピタリズム マネーは踊る」マイケル・ムーア
https://youtu.be/aguUZ7PGd2A https://youtu.be/a
-

-
幸田露伴『一国の首都』明治32年 都議会議員和田宗春氏の現代語訳と岩波文庫の原書で読む。港区図書館にある。
幸田露伴は私の世代の受験生ならだれでも知っている文学者。でも理系の人でもあり、首都論を展開してい
-

-
Quora 日本が西洋諸国の植民地にならなかったのは何故だと思いますか?
https://jp.quora.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%8C%

