『旅行契約の実務』 鈴木尉久著2021年 民事法研究会発行
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
旅行業法の解釈について、弁護士でもある鈴木教授がどのような見解を持っておられるかと本書を図書館で借りて読んでみた。やはり、契約実務の解釈が中心である。旅行業法という行政法規の解釈についての記述はなく、残念であった。現実に発生していている現象を元に記述しているので仕方がない。
日常的ではないことは想定しないと(2ページ)とある。観光とは非日常体験なのであるが、消費者相手には旅行業者は如何に日常的な商品しか扱っていないかということが垣間見える表現である。標準約款をはみ出た商品開発がおこなわれず、従って独自の約款に基づくものを販売していないことがわかってしまう。私が知る限りでも標準約款以外のものはJTBのJERONタクシーだけであり、この約款認可に観光庁の担当者が対応できず時間ばかりがかかっていたことを思いだす。ましてや、「利用運送」や「利用宿泊」といった形態は、旅行業法は想定しているものの、中国のCtripが生み出したもの以外は、日本では発生していないから、日本の弱小宿泊業者が大騒ぎをし、内容が理解できないコメンテーターが、ワイドショウで解説していたことを思いだしてしまう。
タクシー運賃規制が主催旅行商品に適されるか否かという問題についても、本書の解説は、旅行業者と旅行者の間の標準約款に終始し、仕入れ取引は契約当事者外の法律関係に過ぎないとして何も解説していない。運送業者、宿泊業者と旅行会社の間での訴訟が一般的ではないことから、仕方がないのであるが、MaaSなどコロナ後の人流論の展開には論議が不可欠である。
関連記事
-
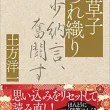
-
『枕草子つづれ織り 清少納言奮闘す』土方洋一 紙が貴重な時代は、日記ではなく公文書
団塊の世代が義務教育時代に学修したことの一部が、その後の研究により覆されている。シジュウカラが言
-
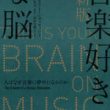
-
『音楽好きな脳』レヴィティン 『変化の旋律』エリザベス・タターン
キューバをはじめ駆け足でカリブ海の一部を回ってきて、音楽と観光について改めて認識を深めることができた
-

-
安易なフードツーリズム、食育、和食神話への批判 コメに無期ヒ素が含まれているのはものすごく都合が悪い。大手メーカーが「ただの水です」といって水素水を売っている
公研2016年6月号に「食の安全とリスクを考える」畝山智香子(国立医療品食品研究所安全情報部第三室長
-

-
ここまで進化したのか 『ロボットの動き』動画
https://youtu.be/fn3KWM1kuAw
-

-
筒井清忠『戦前のポピュリズム』中公新書
p.108 田中内閣の倒壊とは、天皇・宮中・貴族院と新聞世論が合体した力が政党内閣を倒した。しかし、
-

-
「第3章 流入する他所者と飯盛女」武林弘恵著『旅と交流に見る近世社会』清文堂
旅と交流にみる近世社会 高橋陽一 編著
-

-
2023/7/18 【未来予測】地球の課題を解決するのは「人流ビッグデータ」だ ジオテクノロジーズ | NewsPicks Studios
https://newspicks.com/news/8641407/body/ 若い人達も人
-
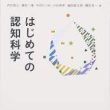
-
『はじめての認知科学』新曜社 人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は双子
人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は
-

-
『婚姻の話』 柳田國男
日本は見合い結婚の国、それが日本の伝統文化である、という説に、柳田ははっきりノーを突き付ける。
