『日本語スタンダードの歴史』野村剛士は、「日本の話しことばについて」『現代国語三』所収 木下順二著1963年を否定
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
出版・講義資料, 動画で考える人流観光学
私の自説に、日常と非日常が相対化しており、観光資源もあいまいになってきているというアイデアがある。それは、国土交通省等在職時に全国津々浦々を何度も回る機会があり、女子高校生が口にする言葉を聞いて、ほとんどその違いがなくなってきていることに気が付いたからである。テレビ向きにお国訛りを強調する場面には何度も出くわしたが、ハレの場面では、みな見事なくらいにNHKの言葉になっていた。
言葉に関する戯曲家の井上ひさしの言説も有名であるが、木下順二の言説に出くわしたので書き留めておく。
木下順二の記述した教科書の中の文章に、九州の侍と東北の侍が江戸で謡をもって相談事の用を足したという逸話が出ているが、野村剛士はまずありえないという(『日本語スタンダードの歴史』110ページ)。キチンと練習してから出て行ったからであるとするが、幕末になると、いきなり動員され、大混乱をしたようである。江戸のきつい方言文化はそのまま明治期になだれ込んだ。従って、野村は、この江戸後期はきつい方言文化と共通語の広がりが共存する時代になっていったと思われるとする
◎参考動画
関連記事
-
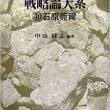
-
「世界最終戦論」石原莞爾
石原莞爾の『世界最終戦論』が含まれている『戦略論体系⑩石原莞爾』を港区図書館で借りて読んだ。同書の
-

-
学士会報926号特集 「混迷の中東・欧州をトルコから読み解く」「EUはどこに向かうのか」読後メモ
「混迷の中東」内藤正典 化学兵器の使用はアサド政権の犯行。フセインと違い一切証拠を残さないが、イス
-

-
『「日本の伝統」の正体』
現在、「伝統」と呼ばれている習慣の多くが明治時代以降に定着したと聞いたら驚く人も多いかもしれない
-

-
QUORA 李鴻章(リー・ホンチャン=President Lee)。
学校では教えてくれない大事なことや歴史的な事実は何ですか? 李鴻章(リー・ホンチャン=Pre
-

-
『諳厄利亜大成』に見る、観光関連字句
諳厄利亜大成はわが国初の英語辞典 1827年のものであり、tour、tourism、hotelは現
-
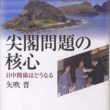
-
『尖閣諸島の核心』矢吹晋 鳩山由紀夫、野中務氏、田中角栄も尖閣問題棚上げ論を発言
屋島が源平の合戦の舞台にならなければ観光客は誰も関心を持たない。尖閣諸島も血を流してまで得るもの
-

-
「若者の海外旅行離れ」という 業界人、研究者の思い込み
『「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書
-
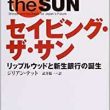
-
『セイヴィング・ザ・サン』 ジリアン・テッド
バブル期に関する書籍は数多く出版され、高杉良が長銀をモデルに書いた『小説・ザ・外資』はア
-
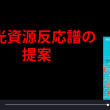
-
AIに聞く、甘利俊一博士の「脳・心・人工知能」を参考にした、『観光資源反応譜』の提案
人流・観光に関する学生用の教科書として、amazonのkindleで『人流・観光学概論』を出版してい
- PREV
- 「人流」概念 2021新語流行語大賞トップテン
- NEXT
- 『ニッポンを蝕む全体主義』適菜収
