『近世社寺参詣の研究』原淳一郎
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
facebook投稿文章
「原淳一郎教授の博士論文「近世社寺参詣の研究」を港区図書館で借りて読む。近世には観光概念が存在したか否かという問題意識があれば面白い書物である。 近世後期から、現世利益が宗教史の表舞台に登場し、現在の日本人の信仰形態に近いものが誕生したとする。来世への希望を持たなくても、現今の生活に基本的には満足していたかである。日常生活において、どうしようもない事態が生じたときに信仰に向かったのである。共同体的祈願という側面を併存させつつも、より「個」による祈願が可能となったのである。団体旅行から、個人旅行へと変化した現代に通じるところがある。 社寺参詣を啓発するものとして、社寺側からの働きかけ(開帳、富くじ、相撲興行等)は必要不可欠のものであったようだ。幕府直営による社寺造営・修復は徳川綱吉の時期を境に影を潜め、間接的幕府助成策(被下金銀、御免勧化、開帳差許等)が打ち出されたが、宣伝活動を趨向する社寺は、こうした幕府の社寺助成の枠から漏れたものが多く、成田山新勝寺が代表例であると紹介する。国立大学中心から、文科省助成私立大学にウェイトが移行しても、完全独立在野の教育機関が、啓発活動の中心になったということであろう。この点では近世後期の方が先進的である。 江戸時代の明和・安永期は、各参詣地ごとに異なる参詣者を抱えていたそれまでの状況を一変させ、双方向に参詣者がいきかい、近世社寺参詣特有の参詣地の複合化が生み出されたとする。この動きを先導したのは宗教側ではなく豊富な読書量を持つ都市知識人層である。現代流にいえば、テレビ新聞インターネットで活躍する博士号を保有する文化人が、海外旅行の名所をシリーズで一般大衆に紹介していることとにている。 文化・文政期が、社寺参詣の大衆化最盛期である。農村部でも在村医療が浸透しつつある時期である。医療が信仰を凌駕した。その結果医療では手に負えない「病」を明確化することになり、より一層病気治癒の現世利益を求めて都市内外を徘徊する人々を生んだのであるとする。従って、現代の観光研究者の一部が主張するように、建前は参詣の形式をとりながら、実は楽しみのための旅が一般化したという理解はしていないのである。 私の観光概念の解釈では、そもそも「楽しみ」というあいまいな概念で論ずることに無理があり、人が移動する動機ごとに分類するのであれば、脳の分析にまで踏み込まなければ実証的科学的なものは得られないとおもっている。近世後期以上に日常と非日常が相対化している現代では、苦しみも楽しみも相対的であり、人流という概念で整理した方が理解しやすいと思っている。 人流現象ではないものの本書では、どういうわけか幕末期には全国的に参詣者が減少していくことを紹介している。その実態、理由等研究課題であるが、神々のラッシュアワーと評されるほど新宗教の生々不断なる状態が待ち受けていたのであるとする。」
原稿材料文章
慶応大学提出博士論文をもとにした書籍であるから読みごたえがある。まず、一般民衆と呼べる江戸中下層民の参詣行動、参詣意識を分析するには、上層町民が残した史料を用い、それを一般化するのは危険とする。諸文芸作品の書き手はあくまでも都市知識人層であり、問題となるのは中下層民の行動であるからである。(津田左右吉によれば、儒教は民衆の生活レベルでは根付かなかったとされる。)
中世後期より日本の文明化の進展と連動して現世利益が宗教史の表舞台に登場してきた。現在の日本人の信仰形態に近いものが誕生したとするのである。来世への希望を持たずとも、現今の生活に基本的には満足していることの表れである。日常生活において、抗しえない事態が生じたときにその速やかな解決を求めて信仰に向かうという図式が構築された。共同体的祈願という側面を併存させつつも、より個による祈願が可能となったのである。60年代まで支配的な思想に影響された考えによる、被支配者的立場というよりも、日常置かれた社会的立場、社会的諸関係からの一時の脱却という程度が実態に即していると考えるとする。
人々の社寺参詣を啓発するものとして、社寺側からの働きかけは必要不可欠のものであった。社寺の勧化活動や開帳、富くじ、相撲興行など多彩なる宣伝活動である。幕府直営による社寺造営・修復は綱吉期を境に影を潜め、被下金銀、御免勧化、開帳差許などの他力本願的助成策が打ち出された。宣伝活動を趨向する社寺は、こうした幕府の社寺助成の枠から漏れたものが多い。成田山新勝寺が代表例である。
明和安永期は、各参詣地ごとに異なる参詣者を抱えていたそれまでの状況を一変させ、双方向に参詣者がいきかい、近世社寺参詣特有の参詣地の複合化が生み出された。この動きを先導したのは宗教側ではなく豊富な読書量を持つ都市知識人層である。
文化文政期、社寺参詣の大衆化最盛期である。農村部でも在村医療が浸透しつつある時期である。医療が信仰を凌駕した。その結果医療では手に負えない「病」を明確化することになり、より一層病気治癒の現世利益を求めて都市内外を徘徊する人々を生んだのである。宮田登氏のいう「流行神」現象である。封建社会からの脱却というようなものではないとする。これがどういうわけか幕末期には全国的に参詣者が減少していく。その実態、理由等研究課題であるが、神々のラッシュアワーと評されるほど新宗教の生々不断なる状態が待ち受けていたのである。祈祷社寺でさえも民衆の希求にこたえるものではなくなりつつあったのである。
関連記事
-

-
保護中: 学士会報No.946 全卓樹「シミュレーション仮説と無限連鎖世界」
海外旅行に行けないものだから、ヴァーチャル旅行を楽しんでいる。リアルとヴァーチャルの違いは分かっ
-

-
『天皇と日本人』ケネス・ルオフ
P114 マイノリティグループへの関心 p.115 皇室と自衛隊 他の国の象徴君主制と大きく
-
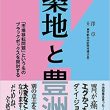
-
『築地と豊洲』澤章 都政新報社
Amazonの紹介では「平成が終わろうとしていたあの頃、東京のみならず日本中を巻き込んだ築地市場の
-

-
『休校は感染を抑えたか』朝日新聞記事
https://www.asahi.com/articles/ASP6J51TNP6CULEI0
-

-
公研2019年2月号 記事二題 貧富の格差、言葉の発生
●「貧富の格差と世界の行方」津上俊哉 〇トーマスピケティ「21世紀の資本」
-
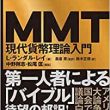
-
『MMT現代貨幣理論入門』
現代貨幣理論( Modern Monetary Theory, Modern Money The
-
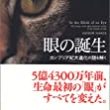
-
『眼の誕生』アンドリュー・パーカー 感覚器官の進化はおそらく脳よりも前だった。脳は処理すべき情報をもたらす感覚器より前には存在する必要がなかった
眼の発達に関して新しい役割を獲得する前には、異なった機能を持っていたはず しエダア
-
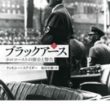
-
「ブラックアース~ホロコーストの歴史と警告」ティモシー・スナイダー著池田年穂訳 を読んで
ホロコーストについても、観光学で歴史や伝統は後から作られると説明してきたが、この本を読んでさらにその
-
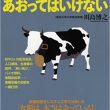
-
『「食糧危機」をあおってはいけない』2009年 川島博之著 文芸春秋社 穀物価格の高騰は金融現象
コロナで飲食店が苦境に陥っているが、平時には、財政措置を引き出すためもあり、時折食糧危機論が繰り返
- PREV
- 『フクシマ戦記 上・下』船橋洋一 菅直人の再評価
- NEXT
- 『江戸の旅と出版文化』原淳一郎
