日本社会党・総評の軌跡と内実 (20人のオーラル・ヒストリー) 単行本 – 2019/4/8 五十嵐 仁 (著), 木下 真志 (著), 法政大学大原社会問題研究所 (著)
公開日:
:
最終更新日:2023/05/21
出版・講義資料
港区図書館の蔵書にあり、閲覧。国鉄再建に関し、「公共企業体(国鉄)職員にスト権を与えるか否か」の政府の対応方針を見誤ったか、裏切られたかはわからないが、本書では、国鉄労組側からの見方が富塚氏が語られていて面白い。スト権ストに関して自民党のタカ派の声がハト派の声を押しつぶしたからであろうが、その結果民営化に行き着くことになったことの歴史の評価はまだ先かもしれない。その時私は運輸省鉄道監督局に勤務しており、偶然局内の課長の最寄り駅での通勤風景が朝刊一面にでており、職員がそれを発見し話題になったことを思い出す。ご本人もうつされていたことに気が付かなったようだった。
臨調委員の加藤寛慶応大教授は、民営化の旗振り役のようにもてはやされ、運輸省職員も海外調査で最重要人物としてアテンドをしたことは身近で見分していた。実は加藤先生は国鉄組合側からは、最もスト権につき理解のある学者だと思われていたから、臨調についても楽観視していたようだが、ふたを開けてみれば全く逆だったこともこの書物に記述されている。真相は他のオーラルヒストリーが開示されるまではわからないが、私にとっては、加藤先生の話は初耳であったから、驚きであった。
当時私が聞かされていた社会党に関しては、国鉄副総裁が国鉄職員出身の社会党政治家の選挙の面倒を見ており、総裁以下の当局幹部が自民党の面倒を見ていたということぐらいであった。そう考えれば、国鉄という組織はすごい組織であり、残念ながらこの時点の運輸省鉄道監督局は国鉄の霞が関出張所的であった。
飛鳥田さんが、委員長になった時、運輸省職員の西村さんという方が秘書官になられた。西村さんは、自動車局保障課で一緒だったかたで、寡黙な人望のある方だった。後に運輸省労働組合の専従になられたから、その縁で飛鳥田氏の秘書になられたのであろう。運輸省にとってはいいパイプ役であったと思う。
本書に登場する伊藤茂さんは、運輸大臣になられたとき、私は広報室長をしていたので、週二回の記者会見でお仕えした。大臣になることは前の週に細川総理から言われたといっておられた。山形在住の母親が、せがれが大臣になったということを方言で嬉しそうに話されていたのが印象的。官房長が安心して記者会見を聞いておれると話されていたように、記者さんからは面白くなかったかもしれない。二階俊博政務次官の方に取材陣があつまっていたように思う。伊藤大臣は退任時、優秀な官房長がサポートしてくれたとかたっていた。成田空港の一坪地主に関連して、運輸大臣として成田にどう対応するかいやな質問も受けていた。答えが間違っていた時は、すぐに自分の非を認めて謝罪されていたことも印象深い。運輸行政が困らないようにされたのであろう。大臣の最後の仕事は名古屋で発生した中華航空機事故。すでに退任は決まっていたが、きちんとされていた。選挙のため、歳費の一年分は貯金をして、残りで活動していたともはなされていた。社会党だから質素だったのだろう。陸軍士官学校では、偶然私の父親が共感をしていた時代に在学されていたようだ。
アマゾン書評1
今はなき「社会党-総評ブロック」に関わった20人からの聞き取り。
社会党でいえば、構造改革論争・安保・市民運動・反戦青年委員会・成田三原則・飛鳥田横浜市政・社会主義協会(規制)・新宣言・土井ブーム・社会党の防衛政策・非自民連立政権・村山政権・・・、総評でいえば、高野総評・ぐるみ闘争、春闘・太田-岩井ライン・三池・安保・構造改革・労戦・スト権スト・国民春闘・社会保障(中央社保協)・総評解散・・・、あわせて日本共産党の労働組合部(労働局)の活動。などのトピックスが余すことなく当事者から語られる。
証言者は、伊藤茂、曽我祐次、加藤宣幸、高見圭司、前田哲男、塚田義彦、公文昭夫、富塚三夫・・・など。
聞き取りの対象を「裏方として実際上の活動を担った『スタッフ(非議員専従など)』を重視して選考」(本書より)したので、時々のトピックス・選択の「裏舞台」がよくわかる。例えば、「構造改革論がなぜ、受け入れられなかったのか」「協会規制について、当の社会主義協会はどう受け止めていたのか」など。村山政権時代の政策立案過程も興味深く読んだ。証言者の方が出会った方の人物評(太田薫や飛鳥田一雄など)も面白く読んだ。前田哲男が指摘する、オルタナティブな安全保障の在り方を政策として提示できなかったという指摘は、今の現状を鑑みて重い。
それぞれの証言を読むたびに、「もう少し何とかならなかったのか」「あの時こういう選択していれば、今よりましな状況をつくることができたのではないか」、そういう思いがずっとつきまとう。総評解散から3分の1世紀。社会党がなくなって4分の1世紀。過ぎ去った時はあまりにも長い
関連記事
-

-
ゆっくり解説】突然変異5選:新遺伝子はどうやって生まれるのか?【 進化 / 遺伝 子 / 科学 】
https://youtu.be/bGthe_Aw1gQ ミトコンドリアと真核生物の起源:生物進化
-
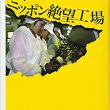
-
『ルポ ニッポン絶望工場』井出康博著
日本で働く外国人労働者の質は、年を追うごとに劣化している。 すべては、日本という国の魅力が根本のと
-
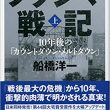
-
『フクシマ戦記 上・下』船橋洋一 菅直人の再評価
書評1 2021年4月10日に日本でレビュー済み国民の誰もがリアルタイムで経験した
-

-
DNAで語る日本人起源論 篠田謙一 をよんで(めも)
篠田氏は、義務教育の教科書で、人類の初期拡散の様子を重要事項として取り上げるべきとする。 私も大賛
-

-
ヒマラヤ登山とアクサイチン
〇ヒマラヤ登山 機内で読んだ中国の新聞記事。14日に、両足義足の、私と同年六十九歳の中国人登山
-

-
保護中: 蓮池透『拉致被害者たちを見殺しにした安倍晋三と冷血な面々』
アマゾン書評 本書を読むに連れ安倍晋三とその取巻き政治家・官僚の身勝手さと自分たちの利権・宣伝
-

-
『鉄道が変えた社寺参詣』初詣は鉄道とともに生まれ育った 平山昇著 交通新聞社
初詣が新しいことは大学の講義でも取り上げておいた。アマゾンの書評が参考になるので載せておく。なお、
-

-
電力、情報、金融の融合
「ブロックチェーンとエネルギーの将来」阿部力也 公研2019No673 電気の値段は下がって
-

-
旅資料 安田純平『ルポ 戦場出稼ぎ労働者』集英社新書
p.254「戦火のイラクに滞在し、現地の人々の置かれた状況を考えれば自分の拘束などどういうことでも
-

-
「北朝鮮の話」 平岩俊二 21世紀を考える会 10月13日 での講演
平岩氏の話である。 日本で語られる金ジョンウンのイメージは韓国発のイメージが強い。そのことは私も北

