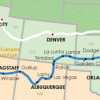有名なピカソの贋作現象 椿井文書(日本最大級偽文書)青木栄一『鉄道忌避伝説の謎』ピルトダウン原人
下記写真は、英国イースト・サセックス州アックフィールド(Uckfield)近郊のピルトダウンにある、ピルトダウン人化石の「発見」の地に残る記念碑である。ピルトダウン人(Piltdown Man)は、考古学者のチャールズ・ドーソンによって捏造(?)された化石人類。20世紀初頭のイギリスはイースト・サセックス州アックフィールド(Uckfield)近郊のピルトダウンにて発見されたとされ、20世紀の前半期の古人類学研究に多大な悪影響を与え、迷走させた。門外漢の私でも英国の田舎町ピルトダウンの名前を記憶し、Wikiでも紹介されるから、大変な観光資源である。
観光資源としての価値は、一万点にも及ぶピカソの作品の無名なものよりも、話題になった偽ピカソの作品の方が、高い。集客力があるからである。ましてや真偽のほどが知れないダビンチの作品においておやである。
偽史に関する著作が紹介されているが、鉄道忌避伝説も有名であるものの紹介されておらず、物足りない。いずれにしろ、町おこしがモチベーションになっている場合には、観光資源として「偽歴史」を逆手に取るくらいのものでもいいのであろう。話題先行である。歌舞伎のテーマになっている史実など、偽歴史の宝庫である。

Yahoo!ニュース「嘘でつくられた歴史で町おこし 200年前のフェイク「椿井文書」に困惑する人たち」が記述されていたが、古くて新しいテーマである。
2020年3月、椿井政隆の偽文書に関する本『椿井文書──日本最大級の偽文書』(中公新書)が出版され、話題を呼んだ。“江戸時代のフェイクニュース”と新聞でも取り上げられた。「問題なのは、各地の自治体が自治体史の編纂や郷土史の根拠にするなど、現在にも影響が強く残っていることです」と語る。歴史学者からするとそういうコメントになるのであろう。偽文書は、何らかの目的をもって偽作された古文書のことだと著者は言い「「たとえば、ある村や地主がその地域の価値を高めたいと考える。そのときに、著名な寺社と過去に深い関わりがあったという“歴史”が古文書に示されていれば、効果的な説得材料になります。そんな権威づけのために事実を偽って制作された古文書は多く、椿井文書もその一つです」数百点の史料を検証していくと、椿井政隆の偽文書は依頼者の求めに応じて制作したケースが多いという。「それでも、実際にはない日付を用いたのは、偽作の痕跡をわざと残すためでしょう。偽文書だと見破られたときに、『遊びでつくったもの』と言い訳できるからです。実際にない日付を記すのは椿井がよく用いた手法なのです」
解説によれば、中世史が専門である馬部さんが、近世の椿井文書にこだわったのは、自治体の非常勤職員として苦い思いを何度も経験したからだとする。「地域の歴史は観光資源であり、町おこしや経済振興にも生かされます。史実としての正しさより、利用価値が優先されることは少なくない。そのため歴史学者の意見は無視されるのです」椿井文書が偽文書として郷土の史料から排除されれば、偽の歴史は時間の経過とともに忘れ去られる可能性はある。しかし自治体が史料として扱い、記念碑などを建造すれば、椿井のつくった偽の歴史は生きつづける。馬部さんはその点に警鐘を鳴らしてきた。
Amazon書評1
椿井文書研究の一般向け新書である。
椿井政隆(通称が権之輔)は山城国相楽郡椿井村(京都府木津川市)出身、興福寺の侍で国学者?。1770年(明和7年)生まれで、1837年(天保8年)に死去。江戸時代中後期に生きた人である。
椿井文書は、椿井政隆が依頼者の求めに応じて偽作した文書の総称。中世の年号が記された文書を近世に写したという体裁をとることが多く、内容が中世のものと信じ込まされてしまう。近畿一円に数百点も分布し、現代に至っても活用されている。
なお、古文書学上は、古文書とは差出人と宛先が記載されたものであり、差出人の署名、印鑑を偽造しているのが偽文書(刑法上の有形偽造?)である。内容が虚偽、虚飾である系図、寺の由緒書等(刑法上の無形偽造?)は古文書ではなく、古記録なので、厳密には偽文書にはならない。
しかし、椿井政隆は虚偽虚飾の系図、由緒書等もたくさん作っており、本書ではこれらも椿井文書に含められている。
概略
終章に第一章から第六章までの内容が要約されている。これの一部をまとめてみる。
第一章椿井文書とは何か・・偽文書の分析に時間を費やすのは多くの研究者にとって無意味なため、研究者が椿井文書の存在に気づいても黙殺する。そのために椿井文書の情報が共有されず、椿井文書を活用した研究が続発する。
第二章どのように作成されたか・・椿井政隆は特定の地域で系図をいくつか作り上げると、人名を連ねた連名帳(たとえば合戦の到達者)を作成し、系図と連名帳の人名と符合させる。寺の縁起などを作成すると、寺、史蹟、系図の家等を載せた絵図を作成する。こうやって文書の信用度を高めておいて、椿井文書である『興福寺官務牒疏』(興福寺末寺リスト)(見かけは1441年作成)にその寺を入れてしまう。これで、椿井正隆の作成した偽地域史が興福寺の古文書(?)の保証を得ることになる。また、椿井正隆は村と村が対立している場面に現れ、村の主張の根拠となるような偽文書を作成した。
第三章どのように流布したか・・椿井政隆は、椿井家に伝わった中世文書の模写を、自分が模写したと主張するものを模写年代(近世後期)を付して領付した(最新コピーなので、絵の具も紙も新しくてよいことになる)。椿井家の没落後に、残っていた椿井文書が、興福寺旧蔵書の触れ込みで、今井家に質入れされ、その後今井家所蔵となって、明治二十年代になり、爆発的に流布した。
第四章受け入れられた思想的背景・・椿井文書はよく知られた基本文献と内容を一致させることで、信憑性を高めている。また、地誌の『五畿内志』を踏まえて文書を作成している。『五畿内志』には擁護と批判があったが、名所づくりのためには、『五畿内志』の内容を利用したほうが有利なので、擁護の意見が強くなっていった。それとともに、『五畿内志』を踏まえた椿井文書の信頼度も上昇していった。
第五章椿井文書がもたらした影響・・略。大変面白いので、ぜひ本文を読まれたい。
第六章椿井文書に対する研究者の視線・・略。同上。終章偽史との向き合いかた。・・略。同上。
私的感想
〇実証的なので、難しい所(たとえば古文書の原文と解説)もあるが、全体としては、まれに見る面白い、刺激的な新書である。
〇第五章にあるように、椿井文書は神社の石碑に取り入れられるだけでなく、諸自治体史に中世史料として収録され、一部は日韓交流事業の原点ともなっている。絵画の一部は文化財指定を受け、巨大な観光案内説明板ともなっている。また、椿井の作った七夕伝説が地元の伝説として語り継がれている。また、椿井文書を活用した歴史研究、展示等も多い。この先、これらはどうなっていくのだろうか。
〇戦後の著名な偽書騒動である「東日流外三郡志」事件とは性格が違うが、共通点も多いように思う。
共通点は、①偽書が大衆化した原因は村おこし、町おこしにあった。②偽作の分量が巨大である。③偽作者の動機ははっきりしないが、金銭のみではなかった。④地域の人々が信じたくなるような話を作り上げている。④それが真実であれば、観光源となる。⑤歴史研究者の間に信憑性をめぐる対立がある。⑥すでに文書に基づく成果ができあがっており、偽書とされると、少なからぬ損害が生じる。
違う点は、①偽作の内容が、「東日流」は新たな東北史の創出で、はるかに規模が大きい。②東北人の歴史的心情に訴えた。③「東日流」は巨大な嘘だが、椿井文書は真実とされていたこと+創作、改変である。
〇椿井文書が偽書であることが一般人にも通説となり、椿井文書を中世史史料として活用しないことが研究者のモラルになっていくまでにはまだ相当の時間がかかりそうだ。「東日流」の場合も、偽書という社会的審判が下るまでに相当の時間がかかった。研究者の意地があり、地元の利益もある。142頁~155頁に出てくる三浦蘭阪は『五畿内志』の内容を徹底して批判し続けた医師兼地方史家だが、『五畿内志』に基づいて、神社が造築され、石碑が作られることは黙認した。「名所づくり」という地元の利益を侵害したくなかったからだ。
〇著者は椿井文書を中世史の史料として使うことを強く非難するが、近世史の史料としてはその重要性を認め、保存活用を訴える。面白い。ここで著者のいう近世史とは一つは「近世偽作史」であり、大量の文書が残り、作者も特定できる椿井文書は絶好の素材であるとする、もう一つは、「近世精神世界研究」で、椿井の思想とそれが受け入れられやすかった近世精神世界の分析である。なるほど。
〇となると、「椿井文書」紛争の落としどころは、偽文書であることを地元に認めてもらった上で、自治体史や説明板や文化財指定はちょっと訂正して、近世史史料として転用活用してもらう・・あたりかな。うーん、若者への説明が難しそうだ。
〇ちょっと気になる事がある。中世史史料としては無価値であるはずの椿井文書が、近世史史料として、高値になっていくことである。228頁、234頁では著者がそれを煽っている感もある。何か理不尽
鉄道忌避伝説のアマゾン書評1「著者の論旨を要約すれば「日本における草創期の鉄道敷設に関して最優先する要素は、決して沿線住民の利害や都合などではなく、当時の建設技術や地形的制約である」となるだろう。しかし、それらを無視したいい加減な鉄道忌避伝説がまことしやかに一般人に敷衍したのはなぜか。 第一には、著名な歴史・地理学者らの鉄道史学軽視の態度である。著者は、きちんとした考証を全く欠いた数多い忌避伝説を「事実無根」として看破する。第二として、地方史誌の執筆者が、地域の鉄道に関する目分量で測ったようないい加減で非科学的な創作を行い、さらにそれらに対する盲目的で都合のいい追認と再生産、それを教科書化のうえ事実として学校で教え込む(それを教える先生方がむしろ率先して「伝説」を信じこんでいるから始末に悪い)ことが原因だと主張した。」
関連記事
-

-
日本銀行「失敗の本質」原真人
黒田日銀はなぜ「誤算」の連続なのか?「異次元緩和」は真珠湾攻撃、「マイナス金利」はインパール作戦
-

-
伝統も歴史も後から作られる 『戦国と宗教』を読んで
横浜市立大学の観光振興論の講義ノート「観光資源論」を作成するため、大学図書館で岩波新書の「戦国と宗
-

-
南米「棄民」政策の実像 遠藤十亜希著 岩波現代全書 最も南米移民を排出したのが最貧困地帯たる東北ではなく北部九州~山陽ラインだったのは何故か?
19世紀末から20世紀半ばまで、約31万人の日本人が、新天地を求めて未知の地ラテンアメリカに移住
-
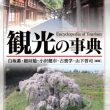
-
『観光の事典』朝倉書店
「観光の事典」に「観光政策と行政組織」等8項目の解説文を出筆させてもらっている。原稿を提出してか
-

-
『知の逆転』吉成真由美 NHK出版新書
本書はジャレド・ダイアモンド、ノ―ム・チョムスキー、オリバー・サックス、マービン・ミンスキー、ト
-

-
QUORA 北方四島問題でソ連は日ソ不可侵条約が有るも拘わらず、終戦直後参戦し北方四島を強奪しましたが、国と国の条約は形式だけで何の意味も持たないのですか?
https://qr.ae/py4JmS 北方領土問題の発端は、大東亜戦争(太
-

-
保護中: 書評『脳は空より広いか』エーデルマン著 冬樹純子訳 草思社
エデルマンは、Bright Air、Brilliant Fire、Wider than the
-
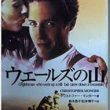
-
観光資源創作と『ウェールズの山』
観光政策が注目されている。そのことはありがたいのであるが、マスコミ、コンサルが寄ってたかって財政資金
-

-
2002年『言語の脳科学』酒井邦嘉著 東大教養学部の講義(認知脳科学概論)をもとにした本 生成文法( generative grammar)
メモ p.135「最近の言語学の入門書は、最後の一章に脳科学との関連性が解説されている」私の観光教
-
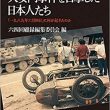
-
『天安門事件を目撃した日本人たち』
天安門事件に関する「藪の中」の一部。日本人だけの見方。中国人や米国人等が作成した同じような書籍があ
- PREV
- Quora 英語は文字通り発音しない単語が多い理由は、ペストの流行が原因?
- NEXT
- メンタル統合