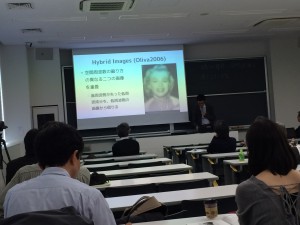2016年3月8日錯覚研究会
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
脳科学と観光
錯覚研究会におよびいただき、観光の話をさせていただいた。発表資料はHPの講演資料集に掲載してある。http://www.jinryu.jp/category/study/treatise
主催者の杉原厚吉先生は、国土交通省時代に夢工学という勉強会に参加して知り合いにならせていただいた。東大の先生の研究室にお邪魔したこともあった。べ兵連を立ち上げたという伝説的な同世代の知人が主催していたが、その知人もなくなった。杉原先生には偶然地下鉄の中で再開したが、定年で明治大学に再就職されておられ、場所が中野ということで偶然が重なってしまった。杉原先生は『大学教授という仕事』というわかりやすい本を出版されており、私が高崎経済大学に就職した折にも、参考にさせていただいた。一般的には『工学部平野教授』や『文学部唯野教授』が世の中に出回っており、面白おかしく話題になっているが、『大学教授という仕事』は杉原先生の人柄が現れているので信頼がおける著書である。なお、私自身は教師という仕事は向いていないと自覚している。幼児教育や中高生教育はさらにむいておらず、大学でそれを行うことは更に厳しいものである。
「錯覚科学への心理学的アプローチと現象数理学的アプローチ」(第10回錯覚ワークショップ)というテーマでの研究会の発表結果は、いずれ「計算錯覚学」のHP(http://compillusion.mims.meiji.ac.jp/)にアップされるだろうから、観光研究者も読まれることを期待する。私自身が仕事の関係上ほかの発表を聞く時間がなく残念であった。
以下、当日配布されたアブストラクトに基づき、観光とのかかわりに関する感想をまとめてみた。
さすがは専門家集団の発表だけあって、素人の私が薄らぼんやり感じていた問題を的確に記述されていた。
わかりやすい具体例は、杉原先生の錯覚博物館でも豊富に紹介されているが、ワークショップでは「身体の制約と錯視」(田谷修一郎)において「蛙の手錯視」が紹介されていた。

指先を奥に向けた手の甲を逆さに見る状況は通常の社会生活で発生することがまれであり、我々の頭の中での距離の見積もりに失敗してしまう結果、指がいびつな手の形(蛙の手)に見えるという錯視を紹介している。博物館や書籍の中だけではなく、屋外において「蛙の手」的な錯視体験を豊富にできる施設が出現すれば、孫のためにしか行かないディズニーランドとことなり、団塊の世代も積極的に出かけてゆくであろう。新しい観光資源が出現するかもしれない。
「錯覚される感情」(山田祐樹)は「感情の無謬性は錯覚である」とする。感情を読み取る顔認証も危うくなるのであるが、観光ガイドブックによりもたらされる情報も危ういことは間違いがないが、観光ビジネスはその錯覚を活用する面があるから面白い。私の演題は「偽物のピカソの絵は本物を超えれるか」とさせていただいた。
「立体情報と時空間の錯誤」(一川誠)を私なりに翻訳すると、観光客が観光資源をみるということは、頭の中でその空間的処理を行う際、二次元的な網膜像処理から三次元的表象を構築する過程であり、時間的処理に関しては、一時限的に進行する時間軸上に諸事情を位置づけする過程であり、どちらも観光客の視覚系が得る情報の中には、時間や空間に関する不良設定問題の一義的な解が存在していないとされているのであろう。
現段階では、錯覚が引き起こす社会的な不都合を除去するためにその原因を解明するに役立つように研究が進めらているのであろうと思っていたが、社会が豊かになれば、不都合を除去するのではなく活用するのであろう。
「錯覚と『叙事詩的』インタラクション」(福地健太郎)は、鑑賞の対象となるコンテンツが動的には全く変化せず、鑑賞者の立ち位置の変化や眼鏡の着脱によって「見え方」が変化する仕掛けを応用したインタラクションについての在り方についての研究を紹介している。
福地氏の話の中で、研究過程で広告会社とのこコラバレーションが出てきていたから、いずれ旅行会社ともコラバレーションが始まるかもしれないと感じた。今の若者にはマリリンモンローもアインシュタインも知らないものがいるから、最終的には「歴史認識」と一緒で、ガイドブックの影響が避けられないという意味で、膨大な量の中から特定の記憶を引っ張り出してくる頭の中の構造が解明されると、さらに面白いのであろう。
「知覚時間のゆがみを利用した時間知覚メカニズムの研究」(四本裕子)は人の脳に「時間近く皮質」は存在しないところから、ある条件下では視覚では時間延長、聴覚では時間縮小を観察できる場合があり、脳の異なる領域間の連絡は各皮質領域の神経活動周期の周波数に依存しているということを示され、ヒトの大脳皮質の各領域が協調して時間をコーティングするメカニズムの一端が解明されたと紹介されている。
研究会に参加して、脳の中のことを解明しようとしている研究がそれぞれ進展してることを思い知らされた。観光研究はいずれ脳科学に収れんしていくであろうから、若い研究者が観光資源にも目を向けてもらえるとありがたいと感じた。
関連記事
-

-
gコンテンツ協議会「ウェアラブル観光委員会」最終会議 3月4日
言い出したはいいが、どうなることやらと思って始めた会議であったが、とりあえず「終わりよければすべてよ
-

-
動画で考える人流観光学 観光情報論 意識 【脳科学の達人2016】 金井 良太 “人工意識のみらい:機械は心をもてるのか?”【日 本神経科学会 市民公開講座】
https://youtu.be/V-eW8u5i9FA 第21回AI美芸研 (2/4)
-
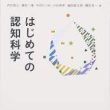
-
『はじめての認知科学』新曜社 人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は双子
人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は
-
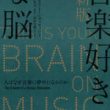
-
『音楽好きな脳』レヴィティン 『変化の旋律』エリザベス・タターン
キューバをはじめ駆け足でカリブ海の一部を回ってきて、音楽と観光について改めて認識を深めることができた
-

-
観光学研究の将来 音譜、味譜、匂譜、触譜、観譜
ベートベンの作曲した交響曲が現在でも再現できるのは音譜があるからである。これと同じように、ポール
-
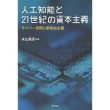
-
本山美彦著『人工知能と21世紀の資本主義』 + 人流アプリCONCURの登場
第6章(pp149-151)にナチスとイスラエルのことが記述されていた。ヤコブ・ラブキンの講演を基に
-

-
『脳の誕生』大隅典子 Amazon書評
http:// www.pnas.org/content/supp1/2004/05/13/040
-
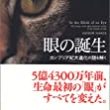
-
『眼の誕生』アンドリュー・パーカー 感覚器官の進化はおそらく脳よりも前だった。脳は処理すべき情報をもたらす感覚器より前には存在する必要がなかった
眼の発達に関して新しい役割を獲得する前には、異なった機能を持っていたはず しエダア
-

-
保護中: 観光研究におけるマインドリーディングの活用の必要性
関係学会における発表で、マインドリーディングを活用した論文がみられない。観光行動等は、楽しみの旅に関
-

-
書評 AIの進化が新たな局面を迎えた:GTP-3の衝撃
米国コロナ最前線と合衆国の本質(10)~AIの劇的な進展と政治利用の恐怖~ https://