『シベリア出兵』広岩近広
知られざるシベリア出兵の謎
1918年、ロシア革命への干渉戦争として行われたシベリア出兵。
実際に起こったのは、極限状態の日本軍兵士によるロシアの村落焼き討ちと、
赤軍パルチザンによる日本の居留民への虐殺だった――
シベリア抑留生存者が出会った〈戦争〉の実態
重複する加害と被害
アマゾンのコメント
今から100年前、日本はシベリアに出兵している。ロシア(出兵時点ではソ連は成立していない)の反革命派を支援するためであり、明らかに内政干渉である。
本書は、そのシベリア出兵で起きたイワノフカ事件、尼港(ニコラエフスク)事件といった日ロの住民虐殺事件、シベリア出兵の概略などに触れながら、“出兵”という名のもとに隠された実態に迫っている。
巻末の「おわりに」に書いてあるように、「戦争は殺人事件」という著者の視点が全編を貫いている。だから、ロシア人が殺されたイワノフカ事件や日本人が殺された尼港事件に加え、ある意味ではシベリア抑留も、戦争が起こした“悲劇”としては同一線上に扱われている。
ただ、シベリア出兵の背景にある「傀儡国家」建国のもくろみ、尼港事件についての日本政府の対応の甘さ、シベリア抑留の背景にある日本の侵略行為、さらには関東軍によるソ連に対する兵士の労務提供に関する「陳情」など、当時の日本の政策に関する問題点を厳しく指摘している。
「シベリア出兵」という名で呼ばれているが、同じように出兵した欧米諸国が撤退するなか、日本のみが7年という長期にわたって出兵(第二次世界大戦でも6年で終わっている)を続けていたことを含め、その実態が「侵略戦争」であったという著者の指摘は充分に納得できる。
救いは、シベリア抑留者だった人々と現在のイワノフカ村の人々との交流だろう。
関連記事
-

-
書評『ペストの記憶』デフォー著
ロビンソン・クルーソーの作者ダニエル・デフォーは、17世紀のペストの流行に関し、ロンドン市長及び
-
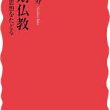
-
『初期仏教』 馬場紀寿著
初期仏教は全能の神を否定 神々も迷える存在であるので、祈りの対象とならない
-

-
戦陣訓 世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例
世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例である。「もはや戦後ではない」は私の
-

-
The best passports to hold in 2021 are: 1. Japan (193 destinations)
https://www.passportindex.org/comparebyPassport.p
-

-
Quora ヨーロッパ人による境界がなかった場合には、今日のアフリカには幾つくらいの国があったと思いますか? 欧州にはバスク語しか残らなかった
https://youtu.be/i28l-t4H1GM ヨーロッパ人による境界がなかっ
-
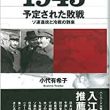
-
歴史認識と書評『1945 予定された敗戦: ソ連進攻と冷戦の到来』小代有希子
「ユーラシア太平洋戦争」の末期、日本では敗戦を見込んで、帝国崩壊後の世界情勢をめぐる様々な分析が行
-

-
Quora に見る歴史認識 知られていない歴史上の出来事の中には、知る価値のあるものがあるのでしょうか? 第二次世界大戦後に行われた米兵による日本の民間人への大量レイプである。
以前にもこれについて書いたことがあるが、その程度や実際に如何程酷かったのかを理解している人は少ない
-
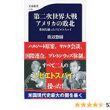
-
渡辺惣樹著『第二次世界大戦 アメリカの敗北』
対独戦争をあくまで回避するべきと主張したチェンバレンら英国保守層 対独戦争は膨大な国力を消費し、アメ
-

-
QUORAにみる歴史認識 不平等条約答えは長州藩と明治政府のせいです。今回に限って言えば、長州藩と明治政府が不平等になるように改悪した原因なのです。
日本人があまり知らない、日本の歴史といえば何が思いつきますか? 日米和親条約と日米修好通商条
-

-
歴史は後からの例「殖産興業」
武田晴人『日本経済史』p.68に紹介されている小岩信竹「政策用語としての「殖産興業」について」『社
- PREV
- 消費と観光のナショナリズム 『紀元二千六百年』ケネスルオフ著
- NEXT
- 安重根の話
