「中国は国際秩序の守護者になるのか?」『公研』2017年3月号No.643鈴木一人
公開日:
:
最終更新日:2023/05/30
歴史認識
偶然二編の論文を読み、日本のマスコミでは認識できない記述を見つけた。
嫌中ムードを煽り立てる記事が多い中、むしろ力をつけてきた中国を冷静に認識しなければならないと感じさせる記事である。
『公研』2017年3月号No.643鈴木一人「中国は国際秩序の守護者になるのか?」
p.13「これは筆者が国連で勤務していた時も感じていたことであった。中国は拒否権を持つ安保理常任理事国であるが、拒否権の行使は2000年以降7回に限られ、常にロシアとともに行使している。そのうち5回はシリアのアサド政権を非難する決議であり、2回はミャンマー・ジンバブエの人権問題である。・・・ちなみに同じ時期に米国は11回、ロシアは13回の拒否権行使を行っている。中国の国連での交渉スタイルは、最初に自国の立場を主張し、その主張と矛盾したり、対立するものでなければ一切口を出さないというものである。・・・・中国の官僚制や政策決定の仕組みのを考えると、柔軟に交渉を展開するよりは、原理原則を前面に出し、それが守られる限り何が起きても構わないという姿勢であるとも考えられる。日本からみると中国は南シナ海、東シナ海で力による現状変更をもくろみ、国際仲裁裁判所の判決も受け入れない、傍若無人なふるまいをする国とみられがちである。しかし国際社会での中国の評価はかなり違う。途上国は援助の提供国としてみており、また欧州はビジネスパートナーとして中国を見ており、グローバルな秩序に従い、その秩序を維持する立場であるとみている」
関連記事
-

-
QUORAに見る歴史認識の一意見 東条英機と昭和天皇の関係に関する一意見
東条英機氏は几帳面で小心、そして子煩悩なな男だった伝えられている。石原莞爾氏などは、東条氏の小物
-

-
「北朝鮮の話」 平岩俊二 21世紀を考える会 10月13日 での講演
平岩氏の話である。 日本で語られる金ジョンウンのイメージは韓国発のイメージが強い。そのことは私も北
-

-
書評『山形有朋』岡義武 岩波文庫
p.208- 晩年とその死 世界戦争に関し、米国の対日態度は懸念される。ドイツの敗戦が必ず
-

-
Quora カンボジャ虐殺の原因は米軍という解釈
Osamu Takimoto·金10年ほど海外で生活していました最も誤解されている歴史上の人物は誰
-

-
QUORAにみる歴史認識 日中戦争において1937年の南京陥落の時点で陸軍参謀本部は戦争終結を主張したそうですが、なぜ日中戦争はその後も続き泥沼化したのでしょうか?
回答するフォロー·3回答依頼4件の回答Furukawa Yutaka, 素人軍事・歴史批評家回答
-

-
三谷太一郎『日本の近代とは何であったか』なぜ日本に政党政治が成立したのか
1 なぜ日本に政党政治が成立したのか (これまではなぜ政党政治は短命に終わったかを論じてきた)
-

-
QUORAに見る歴史認識 世界で日本人だけできていないと思われることは何ですか?
世界で日本人だけできていないと思われることは何ですか? そもそも、日本が世界的に優れているも
-

-
横山宏章の『反日と反中』(集英社新書2005年)及び『中華民国』(中央公論1997年)を読んで「歴史認識と観光」を考える
歴史認識を巡り日本と中国の大衆が反目しがちになってきたが、私は歴史認識の違いを比較すればするほど、
-
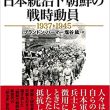
-
コロニアル・ツーリズム序説 永淵康之著『バリ島』 ブランドン・パーマー著『日本統治下朝鮮の戦時動員』
「植民地観光」というタイトルでは、歴史認識で揺れる東アジアでは冷静な論述ができないので、とりあえずコ
-

-
平野聡著『大清帝国と中華の混迷』を読んで
ヴァーチャル旅行韓国中国東北編を記述する際の参考に読んでみた。大変参考になったが、筆が走りすぎてい
