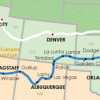戦時下の民生のイメージ:『戦時下の日本映画』古川隆久 吉川弘文堂 2003年
公開日:
:
最終更新日:2016/11/25
戦跡観光
観光も戦時下において隆盛になった。満州観光や神社巡りが奨励された。戦争の勃発と同時に大人の映画観客が増加した。盧溝橋事件は最初ニュース映画で話題になったが、一段落するとニュース映画も下火になった。国策映画は大衆に受け入れられなかったが、その中で例外的にヒットしたものに「ハワイマレー沖海戦」「かくて神風は吹く」があるが、特撮が見事であったことがその理由である。むしろナチスドイツの方が娯楽が中心に[映画を作成していた。ナチスは映画に限らず、民生への気配りは怠らなかったといわれている点が、戦時体制の日本と異なる。
「カサブランカ」(1943年)もアメリカの国策映画であった。
「愛染かつら」は催涙映画と呼ばれて蔑視された。
1939年に映画法が制定されたが、「支那の夜」も 国策映画ではない。 日本中国双方から批判するものもいたが大ヒットとなった。
東條から小磯内閣にかわり、言論指導方針を率直に再検討し始めた。
関連記事
-

-
保護中: 日清関係(メモ)
日清関係の展開 日本は西洋の衝撃に敏感に反応し、クローズド・システムの効率性を活かして大きくかわっ
-

-
保護中: ○日米関係史「開戦に至る10年」2陸海軍と経済官僚(メモ)
明治憲法(67条)は、予算は行政機関に対する天皇の訓令という考え方であり、統治者自身は予算に拘束され
-

-
ダークツーリズムの一例
ハンフォード・サイト(英語: the Hanford Site)は米国ワシントン州東南部にある核施設
-

-
福間良明著『「戦跡」の戦後史』岩波現代全書2015年を読んで
観光資源論をまとめるにあたって、改めて戦跡観光を考えていたが、偶然麻布図書館で福間良明氏の『戦跡の戦
-

-
QUORAにみる観光資源 フランスには第一次世界大戦がきっかけで未だに住むことのできない地域があるって本当ですか
この回答は次の質問に対するQuora英語版でのRichard Sampleさんの回答です (ご本人
-

-
◎◎2脳への刺激(脳波信号解析)と観光~「ダーク・ツーリズム」批判~
脳波信号解析研究の結果、人間の脳波の周波数はほぼ0~30ヘルツの領域に収まり、その周波数の組み合わ
-

-
グアム・沖縄の戦跡観光論:『グアムと日本人』山口誠 岩波新書2007年を読んで考えること
沖縄にしろ、グアム・サイパンにしろ、その地理的関係から軍事拠点としての重要性が現代社会においては認め
-

-
動画で考える人流観光学 資料 インパール
https://www.nhk.or.jp/archives/shogenarc
-

-
◎◎5 戦争裁判の観光資源化~東京裁判とニュルンベルグ裁判比較~
ニュルンベルク・フュルト地方裁判所600号陪審法廷は、ニュルンベルグ裁判が開催された法廷として資料も