歴史認識
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
歴史認識
歴史認識も時代により変化する。日本人の徳川時代の認識は、明治政府によりつくられたものを学校で学んだせいなのか、「薩長史観」的であった。徳川家18代のご頭首は、冗談交じりに、子供の頃学校で歴史を学び、とんでもない家に生まれてきたと語られたものである。一世紀以上を経た近年ではその認識が見直されつつあり、士農工商のような身分制は存在しなかったという学説が主流となっている。しかしこれも政治的にはその過程を経なければおさまらなかったものなのであろう。
日本の朝鮮植民地政策に関する、韓国人の歴史認識はいわゆる「民族史観」以外はタブーとなっている。この民族史観に感情的に反応する日本人がヘイトスピーチを行うものだから、冷静な歴史認識論議など期待するほうが無理なのである。我々日本人もついこの前まで、薩長史観に基づく歴史認識に基づき、士農工商は「親の敵」と思っていたのだから、他国の歴史認識がそのうちに変化するかもしれないということぐらいは理解をし、余裕をもって接することができなければ先進国とは言えないのであろう。韓国は北朝鮮とともに、日本の敗戦直後、自国民の政府が樹立できなかった歴史(韓国の場合は沖縄同様にアメリカ軍の直接統治)の中で、内戦を経験し、今なお継続しているから、権力者が正統性を主張するためには、民族史観にならざるを得ないのである。これを否定することは、日本においては天皇制を否定するに等しいのかもしれない。中国共産党についても同じことが言える。
今EUがユーロをめぐって揺れている。ギリシャの経済危機の取扱であり、イギリスの離脱問題である。イギリスは王室を抱く国家であるが、超国家的なEU加盟国でもある。EUの元首はイギリスの元首より上席になるのであろう。東アジアも欧州並みに成熟し、日本が近隣諸国と超国家的組織に加わるとしたら、日本の天皇制に対する国民の感情も変化しているかもしれないし、韓国の民族史観や中国共産党の歴史認識も変化しているのであろう。
関連記事
-

-
『元寇』という言葉は江戸時代になって使われ始めた
Wikiでは、「「元寇」という呼称は江戸時代に徳川光圀が編纂を開始した『大日本史』が最初の用例で
-

-
『総選挙はこのようにして始まった』稲田雅洋著 天皇制の下での議会は一部の金持ちや地主が議員になっていたという通説が実証的に覆されている。いわば「勝手連」のような庶民が、志ある有能な人物(国税15円を納める資力のない者)をどのような工夫で議員に押し立てたかを資料に基づいて丹念にドキュメンタリー風に解説
学校で教えられた事と大分違っていた。1890(明治23)年の第一回総選挙で当選して衆議院議員にな
-

-
QUORAにみる歴史認識 第二次世界大戦時、なぜ戦況は悪化したのに、(日本は)戦争は辞められなかったのですか?
第二次世界大戦時、なぜ戦況は悪化したのに、戦争は辞められなかったのですか? 日本では、開戦時
-

-
ふるまいよしこ氏の尖閣報道と観光
ふるまいよしこさんの記事は長年読ませていただいている。 大手メディアの配信する記事より、信頼できる
-

-
QUORAに見る歴史認識 あなたが「この人誤解されてるな」と思う歴史上の人物は誰ですか?
あなたが「この人誤解されてるな」と思う歴史上の人物は誰ですか? ネルソン・マンデラさん。
-

-
塩野七生著『ルネサンスとは何であったのか』
後にキリスト教が一神教であることを明確にした段階で、他は邪教 犯した罪ごとに罰則を定める 一
-
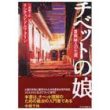
-
『チベットの娘』リンチェン・ドルマ・タリン著三浦順子訳
河口慧海のチベット旅行記だけではなく、やはりチベット人の書物も読まないとバランスが取れないと思い、標
-

-
『シベリア出兵』広岩近広
知られざるシベリア出兵の謎1918年、ロシア革命への干渉戦争として行われたシベリア出兵。実際に起
-

-
書評 三谷太一郎『日本の近代とは何であったか』日本の近代化にとって天皇制とは何であったか
日本の近代とは明確な意図と計画をもって行われた前例のない歴史形成の結果 前近代の日本にはこれ
-

-
Quora 徳川秀康は、関ヶ原の戦いに、真田家の妨害で遅刻しましたが、将軍になれました。関ヶ原の大失敗の後に汚名を返上するような仕事をしたのでしょうか?
のちの徳川二代将軍秀忠はいわゆる「関ヶ原の戦い」に参加していませんが、これは「遅刻」なのでしょうか
- PREV
- 世界遺産を巡る日韓問題(軍艦島)
- NEXT
- イサベラバードを通して日韓関係を考える


