QUORAにみる歴史認識 不平等条約答えは長州藩と明治政府のせいです。今回に限って言えば、長州藩と明治政府が不平等になるように改悪した原因なのです。
公開日:
:
最終更新日:2020/12/01
歴史認識
日本人があまり知らない、日本の歴史といえば何が思いつきますか?
日米和親条約と日米修好通商条約です。どちらも日本の歴史を転換点とも言える大きな条約にも関わらず、日本人が知っているのは開港した港と関税自主権の撤廃、領事裁判権を認める程度しか知られてません。この2つの背景を知ると、もっと重要なことが起きたことがわかります。
まずは日米和親条約から。
日米和親条約は1854年に日本とアメリカの間で結ばれた条約で、ペリーが黒船に乗って脅してきたというのは有名ですよね。アメリカの全権大使はペリーですが、日本側の全権大使は誰なのでしょうか?正解は林復斎(大学頭)です。この人のおかげでだいぶ温い条件になったにも関わらず一切知られていないのは残念です。まず、日米和親条約の原案では、1漂流民の保護 2食料、薪水の供給 3アメリカとの交易の開始でした。
アメリカ側の建前は人命保護つまり1、2をしっかりすることでしたが、本音は交易の開始でした。林は1、2は即座にのみます。1は特に問題なく、2もそもそも幕府は以前に薪水給与令を出しているので問題なし。ただ3はすぐこの前にアヘン戦争のこともあり、幕府側は絶対にのめない話でした。のめない旨をペリーに伝えますがそんな簡単にすごすごとは引き下がらないです。ブラフとして戦艦がまだまだ大量にいることを伝えて、ラゴタ号事件を盾に戦争も辞さないという態度を取ります。しかし、林はその脅しにも屈せずラゴタ号事件は殺し合いが起きていた状況であり、管理が罪人と同等になったと言って、ペリーを黙らせます。
そして、林は交易は国内の法で禁止されているのと、人命保護には関係のない話だからと、なかったことにしました。林無双はまだまだ続きます。ペリーは少しでも自分たちの有利になる条件を飲ませたいという思いもあり、長崎だけでは不便だから長崎以外も5、6港を開港しろと言ってきます。そこで、林はそもそも最初の案になかった話なのだから、本来はのめないが不便って言っているし、お情けで2港開港してあげると言います。ペリーもお情けで開けてもらっている以上は数に関しては文句が言えませんでしたが、かわりに今すぐそこの2港を言えと迫りますが、これも最初の案にないのにいきなりは言えないという理由で7日ほど保留し、幕府と要相談して決定します。そして、最後に開かれた港からどの程度を行動範囲とするかが話し合われます。アメリカ側は14里ほどを行動範囲とすることを求めますが、林は薪水、食料を供給するだけなのだからという理由でその半分の7里だけを行動可能な領域にします。この様に、日米和親条約は本来は圧倒的に強国のはずのアメリカ側の意図を全て挫き、日本も以前にやっていた法律を利用すれば可能な範囲の条約を結ぶことに成功した素晴らしい条約だったのです。
そして、次は日米修好通商条約です。実は日米修好通商条約を結ぼうとしていた時期は中国でアロー戦争などが起きて、英仏が日本に攻めてくる可能性がいよいよ現実化してきており、日本の植民地化まで秒読みの段階まで来てました。そのため、幕府は多少強引にでもアメリカと条約を結び、アメリカの保護下に入ることで戦争を回避しようと画策します。現にアメリカの総領事であったハリスは着任した頃から通商条約の締結を求めていましたが、それを幕府がずっと拒否し続けていたのに、いきなり態度を変えて締結に応じています。そこで、問題になるのが条約内容です。幕府は多少の不平等なら致し方なしというのが大勢でした。英仏にボコボコにされて植民地に成り下がるよりかははるかにマシです。そこで、アメリカに守ってもらうかわりに領事裁判権と関税自主権の撤廃をのみます。ただ、これも正直、日本にとってそこまで不利であり不平等なのかと言われるとそうでもないのです。
まず領事裁判権ですが、修好通商条約が結ばれた当初は開港されたところからおおむね10里以内しか外国人は移動できなかったので、日本人が開港地の10里以内に近づかなければ(そもそも禁止されていたが)、外国人は日本人に接触できません。治外法権でもそこまで問題なかったのです。関税自主権も関税を変えるときに両国間の合意が必要なだけで、結ばれた当初の税率を見れば一般的な税率であり(酒類にいたっては30%以上もの関税が!)、変更の必要は特に見当たらず、そこまで不平等といった内容ではありませんでした。
では、なぜここまで不平等と叫ばれたのでしょうか?答えは長州藩と明治政府のせいです。今回に限って言えば、長州藩と明治政府が不平等になるように改悪した原因なのです。
関税自主権は長州藩は攘夷を掲げて下関砲台からイギリス船を攻撃します。このことによって下関戦争が勃発し、長州藩があっけなく敗戦。幕府はその責任をを取る形で関税が概ね20%であったものを5%まで引き下げます。この下げられた関税を元に戻せなくなったのが問題であり、長州藩が無駄なことをしなければ問題ありませんでした。領事裁判権も一般の日本人と外国人との接触を禁止していた法律を撤廃したのは明治政府であり、江戸時代には不平等と言われるほどの不平等ではありませんでした。どちらかというと、ヨーロッパと日本が対立したときはアメリカが仲裁するという義務を負っていたので、不平等感で言えばどっこいどっこいです。
今では江戸時代にアメリカからの圧力に屈して結んだ不平等条約を明治政府がすごい努力をして撤廃させることに成功するといったように教えられていますが、調べれば調べるほど、どちらかというと明治政府と長州藩の身勝手で改悪されたできてしまった不平等を外国のお情けで無くしてもらったといった印象が強い話なのです。
関連記事
-

-
『二・二六帝都兵乱』アマゾンの書評
著者は軍制、軍事面からアプローチしていると言っているが、それだけではない。当時の社会の通念、雰囲
-
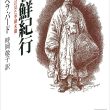
-
イサベラバードを通して日韓関係を考える
Facebook投稿文(2023年5月21日) 徳川時代を悪く評価する「薩
-
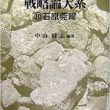
-
戦略論体系⑩石原莞爾(facebook2021年5月23日投稿文)「極限まで行くと、戦争はなくなるが、闘争心はなくならないので、国家単位の対立がなくなるという。」
石原莞爾の『世界最終戦論』が含まれている『戦略論体系⑩石原莞爾』を港区図書館で借りて読んだ。同書の存
-

-
『永続敗戦論 戦後日本の核心』、『日米戦争を起こしたのは誰か ルーズベルトの罪状・フーバー大統領回顧録を論ず』『英国が火をつけた「欧米の春」』の三題を読んで
「歴史認識」は観光案内をするガイドブックの役割を持つところから、最近研究を始めている。横浜市立大学論
-

-
「中国は国際秩序の守護者になるのか?」『公研』2017年3月号No.643鈴木一人
偶然二編の論文を読み、日本のマスコミでは認識できない記述を見つけた。 嫌中ムードを煽り立てる記事が
-

-
『日本軍閥暗闘史』田中隆吉 昭和22年 陸軍大臣と総理大臣の兼務の意味
人事局補任課長 武藤章 貿易省設置を主張 満州事変 ヤール河越境は 神田正種中佐の独断
-

-
You-Tube「Cruise to Japan in 1932」に流れる「シナの夜」
1932年は鉄道省に国際観光局が設置されて2年目、インバウンドが叫ばれる現代と同じような時代である
-
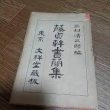
-
中国文明受入以前は、藤貞幹は日本に韓風文化があったとする。賀茂真淵は自然状態、本居宣長は日本文化があったとする。
中国文明受入以前は自然状態であったとする賀茂真淵、日本文化があったとする本居宣長に対して、藤貞幹
-

-
🌍🎒シニアバックパッカーの旅 黒竜江省ハルピン(承前)文化大革命 安重根記念館
NHK 文化大革命.40年后的证言 全片 https://youtu.be/N00RTaA72g4
-

-
Quoraに見る歴史認識 終戦後に当時のソ連は、どうして北海道に侵攻しなかったのですか?
終戦後に当時のソ連は、どうして北海道に侵攻しなかったのですか? 回答を先に書けば、米国との間


