QUORAに見る歴史認識 戦前の財閥ってどれくらいお金持ちだったんでしょうか?具体的に分かるように説明していただけませんか?
公開日:
:
最終更新日:2020/12/01
歴史認識
そのジニ係数は――あえて国際比較を行うと――大土地所有者と彼ら以外の間に大きな所得格差があることに知られるブラジルや、少数の人びとが豊富な地下資源を握っている、世界で最も貧富の格差の大きい国 ナミビアに匹敵する高さでした。
当時もこうした大きな格差――むろんジニ係数が分かっていたわけではないので当時の人びとの「体感的な格差」ですが――には社会的関心が強かったようで、実際、「富者と貧者がどれくらいいるのか」「どれくらいの世帯所得があると標準的なのか」などについて、ラフな推計が行われていました*****。これに、昭和戦前期のサラリーマンの夢であった「月給百円」という事実を組み合わせて******、屋上屋を重ねる推計をおこなった結果を、ご参考程度にしかならないのですが、以下にお示しします。
これによると、推計がラフなものなので、かなり限定的にならざるをえませんが、おおよそ以下の点は指摘できるでしょう。
- 最も上級ランクの「上流階級の富者」の世帯年収は2万円以上ですが、この層は、当時の東京市(現在の23区にほぼ相当)には400世帯ほどしかいませんでした(1930年の東京市の全世帯は41万4000世帯ほどです)。比率だと0.1%にすぎません。
- つぎに、これくらいはほしいという夢というか「当時の標準的」とみなされていた日本標準にある世帯ですら、5500世帯(1.3%)しかいませんでした。そして、もう少しで1200円に届く層が4500世帯(1.1%)ほどいますから、標準的およびややその下の階層にいた世帯は合計でもやっと1万世帯(2.4%)ほどにすぎませんでした。
- 一方、下流階級に属する世帯年収400円未満世帯は東京市の全世帯の97%を占めるほどぶ厚い層を形成していました。
確かに、こうした所得階層分布だと、最下層の人びとから見れば、「最上級富者」である財閥家族の富の大きさはまさに「殿上人」のそれであったことになりますね。昭和戦前期の社会が、近現代史の中でも、とくに不安定化したのも無理からぬところです。
●財閥家族の富の蓄積の到達点
彼らの富の蓄積は戦前にどれほどのレベルに達していたのでしょうか? それが分かる数値があります。
ご存じのように、終戦後、財閥解体が行われました。それに際して事前調査が行われて、その数値が残っているので、彼らの富の蓄積の到達点が分かるのです。
財閥解体の際、財閥家族として指定された人は56名でした。彼らが差配する財閥本社が所有していた株式数はおよそ1億6700万株でしたが、これは当時の国内の総株式のほぼ40%に相当しました。
「わずか数十人で日本の発行済株式の40%を握る」。これが戦前の財閥の富の蓄積の到達点だったわけです*******。
●峻烈に行われた財閥解体
ご存じのとおり、財閥は解体されました。
その結果、彼らの持株数は、1億6700万株から200万株へとほぼ完全に没収され、売却されました。
それにくわえて彼らを待っていたのは公職追放であり、事実上の財産没収税の適用でした。
Ⅲ 戦後日本は大幅に平等な社会になった
財閥解体と、今回の投稿では触れませんが、農地改革と労働民主化で、日本にいた「最上級富者」は姿を消しました。その結果、戦後の日本に訪れたのは、大きく所得格差の縮小した社会でした。戦前と戦後のジニ係数を繋ぐと以下のようなグラフになります。
ジニ係数はやっかいな数値で、依拠する資料によって大きく数値が異なるという困った性質があります。
近年においては「格差拡大が進んでいる」という認識が広がり、そういった研究もありますが、それは短期で見た場合のことです。近年の動向も重要であることは、私も十分に認識しております。ただし、近年の格差の動向については、別途ご質問が提示されていますので[1] 、そちらに回答させていただきたいと思います。
私が今回お示ししたのは、100年ほどの期間でみると、戦後日本は大きく所得配分の平等化した社会になったという事実です。
現代日本は戦前に比べて大きく平等化しており、これが大衆消費社会の招来しました。「一億総中流化」などと否定的な意味合いで語られる事態は、実は世界的に見れば稀有な例です。中国や韓国の例を持ち出すまでもなく、中間層が薄く(つまり内需が小さく)、それが経済発展の足枷になっている国も多いのに。
いつもながらの長文におつきあいくださいまして、ありがとうございました。
* なお、現在では、日本において、グループ系企業というものは存在しますが、財閥自体は、財閥本社にあたる持株会社が存在しないため、消滅していますし、制度的に復活もできません。
財閥は過度経済力集中排除法によって解体が行われ、また、独占禁止法によって持株会社の設立や既存会社の持株会社化が禁止されました。それゆえ、実質的に、現在は、戦前の財閥に相当するものはありませんし、復活もできません。
ただし、その後、金融ビッグバンの一環でとして、1997年に、企業連合体の安定化を図る目的で、純粋持株会社が解禁されましたが、これとても戦前の財閥復活の手段になるわけではありません。
** 地図は明治40年ごろの実測地図を復元したものです。『江戸明治東京重ね地図』(エーピーピーカンパニー、2009年)より抜粋。以下同様の地図についても同じ出典です。
*** Google Earth の航空図に、投稿者が、おおまかに旧三井邸のあった場所に水色で線を引いています。
**** 南亮進『日本の経済発展と所得分布』(岩波書店、1996年);ここに採録されているジニ係数は、戸数割という地方税のデータを長年にわたって丹念に集めて計算したものです。
***** 森本厚吉『生存より生活へ』(文化生活研究会出版部、1923年)がその代表例でしょう。
****** 岩瀬 彰『「月給百円」のサラリーマン――戦前日本の「平和」な生活――』(講談社現代新書、2006年)を参照しました。
******* 日本の財閥には「総有」という概念があって、持ってはいても好き勝手に個人が使えるという類いの富ではありませんでした。この点については、財閥研究の泰斗である安岡重明教授の『財閥形成史の研究 増補版』(ミネルバ書房、1998年)を参照しました。
脚注
関連記事
-

-
書評 渡辺信一郎『中華の成立』岩波新書
ヒトゲノム分析によれば、山東省臨̪淄の遺跡 2500年前の人類集団は現代欧州と現代トルコ集団の中間
-

-
Quoraに見る歴史認識 なぜ、日本はアメリカの属国と言われるのですか?
北原 俊史·6月22日映像制作者なぜ、日本はアメリカの属国と言われるのですか? 1960年の
-

-
QUORAにみる歴史認識 不平等条約答えは長州藩と明治政府のせいです。今回に限って言えば、長州藩と明治政府が不平等になるように改悪した原因なのです。
日本人があまり知らない、日本の歴史といえば何が思いつきますか? 日米和親条約と日米修好通商条
-

-
QUORA 李鴻章(リー・ホンチャン=President Lee)。
学校では教えてくれない大事なことや歴史的な事実は何ですか? 李鴻章(リー・ホンチャン=Pre
-

-
QUORAにみる歴史認識 日中戦争において1937年の南京陥落の時点で陸軍参謀本部は戦争終結を主張したそうですが、なぜ日中戦争はその後も続き泥沼化したのでしょうか?
回答するフォロー·3回答依頼4件の回答Furukawa Yutaka, 素人軍事・歴史批評家回答
-

-
DVD版 NHKスペシャル『日本人は何故戦争へと向かっていたっか』第3回「熱狂はこうして作られた」(2011年2月27日放映)を見て 麻布図書館で借りて
メディアが戦争をあおり立てたというおなじみの話がテーマ。 日本の観光政策が樹立されていく1930年
-
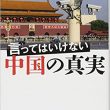
-
『言ってはいけない中国の真実』橘玲2018年 新潮文庫
コロナ禍で海外旅行に行けないので、ブログにヴァーチャルを書いている。その一つである中国旅行記を
-

-
ヨーロッパを見る視角 阿部謹也 岩波 1996 日本にキリスト教が普及しなかった理由の解説もある。
キリスト教の信仰では現世の富を以て暮らす死後の世界はあ
-

-
横山宏章の『反日と反中』(集英社新書2005年)及び『中華民国』(中央公論1997年)を読んで「歴史認識と観光」を考える
歴史認識を巡り日本と中国の大衆が反目しがちになってきたが、私は歴史認識の違いを比較すればするほど、
-
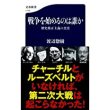
-
渡辺惣樹『戦争を始めるのは誰か』修正資本主義の真実 メモ
要旨 第一次世界大戦の英国の戦争動機は不純 レイプオブベルギー チャーチルの強硬姿勢 第二次


