公研2019年2月号 記事二題 貧富の格差、言葉の発生
公開日:
:
最終更新日:2023/05/21
出版・講義資料
●「貧富の格差と世界の行方」津上俊哉
〇トーマスピケティ「21世紀の資本」
世界経済は長期的に見れば年平均1%を下回る経済成長しかしていない。資産の収益率はいつの時代にあっても5%前後はあった。賃金は経済成長見合いでしか伸びないとすれば、貧富の格差は拡大する
ところが20世紀は例外的に貧富の格差が縮小。二度の大戦で欧州の富が失われた
20世紀も終わり世界経済は貧富の格差が拡大する常態に回帰
〇ウォルター・シャイデルスタンフォード大教授「ザ・グレイト・レヴェラー」
例外的に格差が縮小する場合として、戦争に加え、人口激減する大飢饉、疫病、革命
●言葉の起源を探る 対話 岡ノ谷一夫 香田啓貴
サルは声を自由に変えられなくて学習が制限されている
社会の要請で何か特殊な能力がうまくつじつまが合うように進化したというよりも、生活環境や身体の作りの変化が発声にも影響したという考え方の方が好き
霊長類は220種いるが、発声の可塑性が非常に強いのは人だけ
産声仮説
サルと「会話」できる機械はできる。数年内ではないか
関連記事
-

-
保阪正康氏の講演録と西浦進氏の著作物等を読んで
日中韓の観光政策研究を進める上で、現在問題になっている「歴史認識」問題を調べざるを得ない。従って、戦
-

-
世界の運営を米国でなく中露に任せる 2023年6月7日 田中 宇
https://tanakanews.com/230607armenia.htm 5月25日、
-

-
幸田露伴『一国の首都』明治32年 都議会議員和田宗春氏の現代語訳と岩波文庫の原書で読む。港区図書館にある。
幸田露伴は私の世代の受験生ならだれでも知っている文学者。でも理系の人でもあり、首都論を展開してい
-

-
『永続敗戦論 戦後日本の核心』、『日米戦争を起こしたのは誰か ルーズベルトの罪状・フーバー大統領回顧録を論ず』『英国が火をつけた「欧米の春」』の三題を読んで
「歴史認識」は観光案内をするガイドブックの役割を持つところから、最近研究を始めている。横浜市立大学論
-

-
国際観光局ができた1930年代の状勢 『戦前日本の「グローバリズム」』
大東亜共栄圏の虚構を指摘 「バダヴィアに派遣された小林一三商相」国内世論の啓発に努める小林は
-
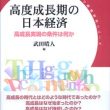
-
『高度経済成長期の日本経済』武田晴人編 有斐閣 訪日外客数の急増の分析に参考
キーワード 繰延需要の発現(家計ストック水準の回復) 家電モデル(世帯数の増加)自動車(見せびら
-

-
QUORAにみる歴史認識 アルメニア虐殺
アルメニア虐殺の歴史的背景はあまり知らてないように思いますが、20世紀の悲惨な虐殺の一ページとし
-

-
『コンゴ共和国 マルミミゾウとホタルの行き交う森から 』西原智昭 現代書館
西原智昭氏の著書を読んだ。氏の経歴のHP http://www.arsvi.com/w/nt10.h
-

-
ドナルド・トランプが大統領になる5つの理由を教えよう
https://www.huffingtonpost.jp/michael-moore/5-rea
-
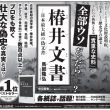
-
有名なピカソの贋作現象 椿井文書(日本最大級偽文書)青木栄一『鉄道忌避伝説の謎』ピルトダウン原人
下記写真は、英国イースト・サセックス州アックフィールド(Uckfield)近郊のピルトダウンにある


