八鍬友広著『闘いを記憶する百姓たち』
公開日:
:
最終更新日:2018/01/17
観光資源
自力救済の時代は悲惨であった。権力が確立すると訴訟によることとなり、平和が確立される。
江戸時代は平和であったのだ。白戸三平の劇画は間違っているのかもしれない。
百姓一揆の訴状が読み書き教材として広く普及していた。この前提として、日本の農村の多くの人が読み書きは出来るということが不可欠。
このような力量を身につけた民衆は、もはや「もの言わぬ民」などではなく、武士に対してさえ強情に「もの言う」百姓たちであった。
時代劇で描かれる「悲惨な民」とは異なり、近世の百姓は、自らの利益のために積極的に訴訟を起こし、武士に対しても堂々と自己主張する存在だった。
17世紀前半に起きた百姓一揆や地域間紛争のなかで作成された訴状が読み書きのための教科書になっていた。
これを目安往来物(めやすおうらいもの)という。
「目安」とは、箇条書きされた訴状のこと。
「往来物」とは、読み書き学習用のテキストブックのこと。「往来物」の最盛期は、じつは明治初期だった。学校制度が始まったけれど、まだ新しい教科書はなかったからだ。
寛永白岩一揆で作成された訴状を白岩目安といった。寛永10年(1633年)、出羽国村山郡白岩郷(山形県西村山郡西川町から寒河江市にかけて・・・)の百姓たちが領主の悲法を幕府へ訴えた。直訴である。租税の負担増、年貢率の上昇に不満をもった百姓たちは、保科家に騙され、36名ものリーダーが磔刑(たっけい)に処された。ただし、領主であった酒井長門守忠重も白岩郷から排除されている。
この寛永・白岩一揆は違法性が強いものであったはずなのに、その訴状は広く東北一円に流布している。
関連記事
-

-
原田信男著『義経伝説と為朝伝説』
伝説においては、歴史学の大原則ともいうべきテキストクリティック(史料批判)は必要とされない。資料の一
-

-
観光資源としての吉田松陰の作られ方、横浜市立大学後期試験問題回答の例
今年も一題は、歴史は後から作られ、伝統は新しい例を取り上げ、観光資源として活用されているものを提示
-
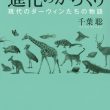
-
進化論 宗教と進化論 『進化のからくり』千葉聡 ガラパゴス島が観光資源になる過程の材料として面白い
イスラム教と進化論、初期キリスト教と進化論 https://youtu.be/i_lrAKC3
-

-
欧米メディアの負の本質 ナイラ証言(Nayirah testimony)
ナイラ証言とは、「ナイラ」なる女性(当時15歳)が1990年10月10日に非政府組織トム・ラントス
-

-
天児慧著『中国政治の社会態制』岩波書店2018を読んで
中国民族は概念としては梁啓超以来使われていたが実体のないものであった。 それを一挙に内実化し実体を
-

-
歴史は後から作られるの例 「テロと陰謀の昭和史」を読んで
井上日召の「文芸春秋臨時増刊 昭和29.7 p.160「血盟団」の名称は、木内検事がそう呼んだので
-

-
『サカナとヤクザ』鈴木智彦著 食と観光、フードツーリズム研究者に求められる視点
築地市場から密漁団まで、決死の潜入ルポ! アワビもウナギもカニも、日本人の口にしている大
-
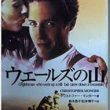
-
観光資源創作と『ウェールズの山』
観光政策が注目されている。そのことはありがたいのであるが、マスコミ、コンサルが寄ってたかって財政資金
-

-
偽物が本物を上回る例 コスモスの「ロッチビックリマンシール
https://www.youtube.com/watch?v=vwBlC73ZmuE
-
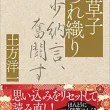
-
『枕草子つづれ織り 清少納言奮闘す』土方洋一 紙が貴重な時代は、日記ではなく公文書
団塊の世代が義務教育時代に学修したことの一部が、その後の研究により覆されている。シジュウカラが言
