『動物の解放』ピーターシンガー著、戸田清訳
工場式畜産 と殺工場
https://www.nicovideo.jp/watch/sm11088087
シンガーの基本的な主張は単純明快だ。シンガー曰く、たとえヒト以外の動物であっても、苦痛を感じる能力をもつものに対しては、不必要に苦痛を与えてはならない。もし、ヒトでないという理由だけで、ある動物に苦痛を与えてもよいというのなら、それは「種差別(speciesism)」以外の何物でもないだろう。しかし種差別は、人種差別や性差別と同様、とうてい擁護しうるものではない。こう主張してシンガーは、ヒト以外の動物に対しても「平等の配慮」を求めていくのである(第1章)。
続けてシンガーは、とくに動物実験(第2章)と工場畜産(第3章)に焦点を当てながら、現代の動物虐待を告発する。当該箇所はまさに初版刊行時に広く注目を集めた部分であり、150ページにも渡って積み重ねられていくそのレポートは、さすがに鬼気迫るものがあるといえるだろう。
さらにシンガーは、第4章でベジタリアニズムのすすめを説いている。じつは、平等の配慮(のみ)を求めるシンガーの立場からは、肉食の否定は厳密には帰結しない(動物に苦痛を与えずに屠殺すればよいからだ)。しかし、前章で論じられたように、食用家畜が現に酷い扱いを受けている以上、われわれはボイコットの意味も込めて食肉を拒否すべきだという。つまり、「不必要に動物を殺すことに反対する人びと」と、「苦しみを与えることだけに反対する人びと」は、ここで共同歩調をとるべきだ(203頁)というのである。
関連記事
-

-
仏フォアグラ生産者が米加州の禁止措置に反発、人道的飼育を主張 「観光資源フォアグラと動物愛護」の教材
世界のこぼれ話2019年1月18日 / 11:26 / 3日前 [モ
-

-
「太平洋戦争末期の娯楽政策 興行取締りの緩和を中心に」 史学雑誌/125 巻 (2016) 12 号 金子 龍司
本稿は、太平洋戦争末期の娯楽政策について考察する。具体的にはサイパンが陥落した一九四四年七月に発
-

-
南米「棄民」政策の実像 遠藤十亜希著 岩波現代全書 最も南米移民を排出したのが最貧困地帯たる東北ではなく北部九州~山陽ラインだったのは何故か?
19世紀末から20世紀半ばまで、約31万人の日本人が、新天地を求めて未知の地ラテンアメリカに移住
-

-
『素顔の孫文―国父になった大ぼら吹き』 横山宏章著 を読んで、歴史認識を観光資源する材料を考える
岩波書店にしては珍しいタイトル。著者は「後記」で、「正直な話、中国や日本で、革命の偉人として、孫文が
-
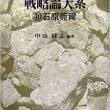
-
「世界最終戦論」石原莞爾
石原莞爾の『世界最終戦論』が含まれている『戦略論体系⑩石原莞爾』を港区図書館で借りて読んだ。同書の
-
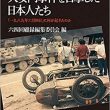
-
『天安門事件を目撃した日本人たち』
天安門事件に関する「藪の中」の一部。日本人だけの見方。中国人や米国人等が作成した同じような書籍があ
-
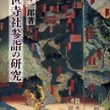
-
『近世社寺参詣の研究』原淳一郎
facebook投稿文章 「原淳一郎教授の博士論文「近世社寺参詣の研究」を港区図書館で借りて
-

-
宇田川幸大「考証 東京裁判」メモ
政治論ではなく、裁判のプロセスを論じている点に独自性がある 太平洋戦争時のジュネー
-

-
『知られざるキューバ』渡邉優著 2018年
4年前のキューバ旅行のときにこの本が出版されていれば、また違った認識ができたとの思う。 カリ
-

-
『訓読と漢語の歴史』福島直恭著 観光とツーリズム
「歴史として記述」と「歴史を記述」するの違い なぜ昔の日本人は、中国語の文章や詩を翻訳する
