『聖書、コーラン、仏典』 中村圭志著 中公新書 メモ書き
公開日:
:
観光資源
福音書の示すイエスの生涯はほとんどの部分が死の前の2,3年前の出来事 降誕劇は神話
ムハンマドの活動について、中年になってアッラーの啓示が下る以前については細かいことはわからない
釈迦の最晩年だけまとまった記録が残っている
昔の社会は識字率が低かった。だからほとんどの信者は教典に直接接することができなかった。昔の人は信心深かったから、みな聖なるテキストを読んでいたと思うのは、現代人の抱きがちな誤解である。
日本仏教は漢訳仏典を典拠としており、明治になるまでインドの原典まで遡って論じることは基本的に無かった。
昔の宗教で重視されたのは、儀礼であり、社会生活上の戒律であり、集団で行う修行であった。教典はそうした共同体的な営みを運営するための指導員向けツールのような性格を持っていた。”
https://www.youtube.com/watch?v=z6r47L-8uf8
https://www.youtube.com/watch?v=NyV01zXuW-A
女性の遺産相続、英国でも女性の遺産相続は100年くらい前から。イスラムは千年前から認めている。ただし、男子の半分。
古代インドの方言であるパーリー語で書かれた仏典(漢訳では阿含経) 上座部
方言の一つサンスクリットで書かれた仏典 大乗仏教
日本仏教は明治まで漢訳仏典を日本語訳せず用いてきた。
宗教というのは人生哲学のようなものであるが、本質的なところにマジックと儀礼がある。
関連記事
-

-
本当に日本は職人を尊ぶ国であったのか?
司馬遼太郎氏は、韓国、中国との比較においてなのか、『この国のかたち』のなかで、「職人。実に響きがよ
-

-
畑中三応子著『ファッションフードあります』日本食は変化が激しい。フードツーリズムに法則があるのか?
ティラミス、もつ鍋、B級グルメ……激しくはやりすたりを繰り返す食べ物から日本社会の一断面を切り
-

-
🌍🎒シニアバックパッカーの旅 動画で見る世界人流観光施策風土記 モンゴル紀行 メモ書き シャーマン動画 トナカイ解体動画
ツァータン族の居住地の4泊分は、通訳代、移動費を別にして、180万ツグルであった。 ツァーマン
-

-
戦陣訓 世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例
世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例である。「もはや戦後ではない」は私の
-

-
🌍🎒シニアバックパッカーの旅 資料 ハルハ川戦争 戦跡観光資源
https://youtu.be/RijLPLzz5oU 中国とロシア
-

-
小川剛生著『兼好法師』中公新書 安藤雄一郎著『幕末維新消された歴史』日本経済新聞社
『兼好法師』 現在広く知られている兼好法師の出自や経歴は、没後に捏造されたもの。 一世紀を経
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源論 フィリピンセブ島刑務所の囚人ダンス
フィリピンセブ島観光・旅行【決定版】絶対にするべき39スポット&アクティビティ http://ce
-
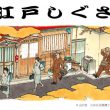
-
伝統は後から創られる 『江戸しぐさの正体』 原田実著
本書の紹介は次のとおりである。 「「江戸しぐさ」とは、現実逃避から生まれた架空の伝統である。本書は
-

-
○『公研』2015年9月号「世界のパワーバランスの変化と日本の安全保障」(細谷雄一)を読んで
市販はされていないが、毎月送られてくる雑誌に公益産業研究調査会が発行する『公研』という雑誌がある。読
-

-
シャマンに通じる杉浦日向子の江戸の死生観
モンゴルのシャマン等の観光資源調査を8月に予定しており、シャマンのにわか勉強をしているところに、ダイ


