タクシー「車庫待ち営業」の規制緩和の必要性
公開日:
:
最終更新日:2017/09/11
人口、地域、, 通訳案内と翻訳導游員
通訳案内業が、これまでのように自家用車を使用できれば、車と運転手の提供を一体的には行っていない(つまり有償運送をしていない)という「非一体性」に配慮しなくて済んだが、新「解釈事務連絡」が出され、これまでも禁止されていた(有償運送行為)とした。
通訳案業に自家用車の使用を認めると、際限なく無償運送行為が拡大すると考えたからであろう。しかし、教育機関が授業料の中からスクールバス経費を支出するのと、通訳案内業が通訳代金から自家用車の経費を支出するのは、本質的違いはないから、法的に道路運送法に規定する運送の概念の立法的解決をすべきであったと思う。この点の国会での議論がなされなかったことは、国土交通省事務局の落ち度であるとされる可能性はかなり高い。通訳案内業関係者が優しすぎるのであろう。
といって、現実は中国人旅行者の増大による事故の可能性が高く、無償運送が際限なく拡大すると、大きな社会問題に発生するであろう。盛んに白タクの違法行為がマスコミに取り上げられるようになったのも、行政からの意図的リークがある可能性がある。
さて、運送業の管理は、集客管理、施設(車両)管理、職員(運転手)管理から構成され、伝統的運輸行政は、これをトータルに数量規制していたと、これまでも何度もブログで紹介して来た。情報化の進展と規制緩和により、この三機能が分化してからも久しい。
タクシーは「流し行為」が中心であることもあり、歩合制賃金体系の下、この運送機能の分化が最も遅れている分野である。
旅行者にとって、レンタカーとドラーバーの提供が手軽にできるようになると、タクシーには脅威である。だから、行政当局は、HISのジャス旅の実施の時にしつこいまでもこの非一体性を強調した解釈を示している(グレーゾーン解消制度での見解提示)。このこともブログで紹介している。
日本は「車庫待ち営業」と「流し営業」が法律上は同等に扱われている。英米法では「車庫待ち営業」はコモンキャリアー(公共交通)として扱っていないから、スマホの登場により、UberやMinicabといったライドシェアが実現したのである。日本は「車庫待ち営業」を「流し営業」並みに扱っているから、ライドシェアを「白タク」だといって非難できるのである。「車庫待ち営業」に類似するレンタカーとドライバーの同時提供も「白タク」だといって厳しく制限するのである。日本Uberの日本における戦略はこの点の認識が完全にかけていたから、成功できなかったのである。この点は日本Uberの経営者の戦略性のなさであろう。
レンタカーとドライバーの一体的提供が有償運送に該当するという解釈は、現時点ではそれなりに正当性はある。しかし、利用者が、自主的に車とドライバーを選択すれば全く問題はないから、その自主性を効率的に促進する情報化が進展すればこの解釈のおかしさが露呈するのも時間の問題である。しかも、ドライバー派遣は厚生労働省所管であり、そのマッチングシステムも、レンタカー利用時のものであることは間違いはないが、利用者とドライバーのマッチング方法についてまで運輸当局が口を出すのは越権であり違法であろう。レンタカーとドライバーのマッチングについてのもの限定すべきであったと思われる。
今私は、来年の調査に備えて、航空券の予約をするためLCCを中心にネットで調べている。調べる片端から、ホテルやレンタカー、ランドのお誘いの案内がHP等に飛び込んでくる。欧米系のものは勿論のこと、中国のCTRIPからも飛び込んでくる。来週からマニラ、麗江等を回るからである。いずれ、レンタカーを予約すれば、こんなドライバーがいますよという案内も飛び込んでくるであろう。日本人の私には、日本語の流暢なドライバー情報が飛び込んでくるのである。私は位置情報を開示しているから、現地に到着すれば、さらに頻度が高くなるのである。観光政策、情報政策は国際競争に生き残るための、日本国の最重要課題である。「非一体」とはいったい何のために考えた概念なのであろう。ロンドン交通局はMinicabの拡大期に、ブラックキャブ業界からのスマホによる運賃計算はタクシーメータに該当するという苦情をはねつけている。該当するという解釈にも正当性はあったと思われるが、そうはしなかった。時代錯誤を自覚していたのであろう。この情報は、2015年にチームネクストで行ったロンドン調査の大きな成果であった。
交通事故の問題は警察の問題である。運転免許行政の問題であり、一定の条件のもと他人のためにレンタカーを運転するドライバーは二種免許が必要であると制度を定めればいいのである、通訳案内業もしかりである(以前の通訳案内士協会のHPには二種免許保有と書いてあったが現在は削除)。運転代行業(自家用車)は当初一種免許でも可能であったが、法改正により現在は二種免許になっている。関係業界は意地悪のつもりであったのかもしれないが、当時私は自家用、営業用の垣根がこれで取り払われた第一号事案だと思った。長時間の連続運転も、その対策に当たっては、営業、自家用に変わりはない。社会全体で決めるべきことである。物流での営業用、自家用が大型トラックに関してほとんど社会問題にならなくなったのが、その先行事例である。
日本社会は、申請者もおとなしい。なまじグレーゾーン解消制度があるばかりに、「非一体」原則の社会的認知を促進してしまった。自信があるなら裁判闘争も辞さない覚悟をするべきであった。そうすれば陸運当局も慎重になり、内閣法制局の見解から、法務省の訟務検事の意見まできいたであろう。政治家はタクシー業界も組合も大事だが、利用者も大事である。すべて有権者であるから。
関連記事
-

-
国際人流・観光状況の考察と訪日旅行者急増要因の分析(2)
1 国際「観光」客到着数 『UNWTO Tourism Highlights 2016 E
-
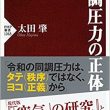
-
地域観光が個性を失う理由ー太田肇著『同調圧力の正体』を読んでわかったこと
本書で、社会学者G・ジンメルの言説を知った。「集団は小さければ小さいほど個性的になるが、その集団
-
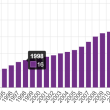
-
Is it true only 10% of Americans have passports?
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42586638
-

-
🌍🎒2023夏 シニアバックパッカーの旅 2023年8月26日 マシュハド 年間2千万人のムスリムが訪問
FACEBOOK 投稿文 2023.8.26マシュハド マシュハド空港からメトロに
-

-
『日本経済の歴史』第2巻第1章労働と人口 移動の自由と技能の形成 を読んで メモ
面白いと思ったところを箇条書きする p.33 「幕府が鎖国政策によって欧米列強の干渉を回避した
-

-
外国人の就労(特に通訳案内士サービス)
外国人の就労は、厚生労働省のHPでは次の通りです。 http://www2.mhlw.go.jp/
-

-
『支那四億のお客様』カール・クロ―著
毎朝散歩コースになっている一か所に商業会館ビルというのがある。この本を出版したのが倉本長治氏のよう
-

-
生産性向上特別措置法(規制のサンドボックス)を必要としない旅行業法の活用
参加者や期限を限定すること等により、例えば道路運送法の規制を外して、自家用自動車の有償運送の実証実験
-

-
欧米メディアの力を示す一例 レイプ率各国比較(⓵南ア⓶ボツワナ⑥スウェーデン⑪豪州⑬ベルギー⑭米国⑮ニュージーランド)
このスクリーンショットをみて、来月旅行予定の南ア諸国が上位4位を占めていた。そのことは承知してい


