Google戦略から見るこれからの人流・観光(東京交通新聞2014年6月23日)
公開日:
:
最終更新日:2023/05/27
旅館、ホテル、宿泊、民泊、不動産賃貸、ルームシェア、引受義務, 東京交通新聞投稿原稿, 随筆など
『モバイル交通革命』の出版から11年がたちます。スマホに代表されるように『位置情報研究会』での論議以上のことが実現しています。時刻表・停車場システムに頼る公共交通が前提にした「不特定多数」概念は、技術進歩で「特定多数」に深化すると予言したのですが、まさに今日の「オンデマンド」「ビックデータ」となって現実化しています。
人類の進化は二足歩行から「手」が自由になり、「目」を使って作業することから「意識」が生まれ、「言語」「文字」を生み出しました。人類の進化をさかのぼるように、Googleは「文字」「言語」による検索システムを進化させています。いずれ非言語検索をも可能とする「知能ロボット」を実用化させるでしょう。他方「目」と「手(足)」にも進出しています。目はGoogle glassを世の中に出し、足はUber(旅行業)どころか自動運転車にまで事業展開してきています。
物流では競争激化からモノを「お届けする」ことが常識ですが、人流もいよいよ「お迎えに行く」時代に入ります。ビッグデータをマーケティングに活用すれば、顧客の意向を予測して先回りすることが可能となります。呼ばれる前にお迎えに行く、まさに木下藤吉郎の「草履取り作戦」をGoogleは考えているでしょう。
モバイル交通革命出版時のドッグイヤー論は、技術の進歩に人間の制度が追いついてゆかないことを論点としていました。航空では既に運賃規制は行われておらず、全日空は定額乗り放題運賃を実施しました。京王電鉄は、渋谷駅でも新宿駅でも利用できるマルチチョイスの定期券(定額乗り放題運賃)を発売しています。これからは時刻表・停車場だけではなく、スマホ・アプリに対応した交通制度を模索することになるでしょう。
政治制度も10年間で変化がありました。地方分権改革は確実に前進しています。地方のことは基礎自治体が行うという原理が確立しました。旅館業法と食品衛生法の管轄が国から都道府県に移管されて生まれた代表例が大分県安心院町の農村民泊だとされています。俗に言うグリーンツーリズムです。今度は自家用自動車有償運送の権限を基礎自治体に移すことが可能となりました。首長をした経験から判断すると、地方議会も自治体も、これまで運送事業行政は「運輸局さん」のお仕事という感覚でした。その「運輸局さん」は地元住民との日々の接触も少なく、人の移動に関する全体像がわからない状態でした。その点選挙で選ばれた人たちは、地域の声には敏感です。権限が移管されれば、運輸局さんの仕事といって逃げられないのですから、必死で『足の確保』を考えざるを得なくなります。
考え方次第ですが、高齢化社会の到来は交通事業者にとっては大きなビジネスチャンスの到来でもあります。我々はマイカーがなければ生活ができない社会を築き上げました。従ってマイカーの運転ができない人達に対する足の確保について、何事も家族の責任だとする伝統的な保守主義者のいうことに、従うわけにはゆかなくなってきます。高齢者の足の確保は、地域社会つまり行政の責任だと判断せざるを得なくなってきます。その足の提供は市場に任せていても供給されません。人口が減少するからです。従って市場に任せない、つまり消防や教育と同じ発想をしなければならなくなります。マイカー社会では車の保有者は自動車関係諸税を負担していますから、その財源のほんの一部を回せば足の確保はできるのです。基礎自治体は、国の機関のように縦割りではなく、道路行政の立場も有していますから、議会が納得すれば可能です。足の確保事業は自治体直営よりも、プロの業者に委託するほうが現実的でしょう。これからの高齢者は、スマホくらいは使えるでしょうから、位置情報把握による効率的配車も可能となります。定額乗り放題運賃や無償制度を組み合わせれば、マイカー並みに便利さを感じていただけるようになるでしょう。
関連記事
-

-
民泊×助成金セミナー「助成金活用型民泊オールインパック」に参加して 2016年7月26日 渋谷クロスタワー32階
24日お昼にFACEBOOKの広告に表記の案内がアップされ、偶然に目に留まった。さっそくFACEBO
-

-
Oneida Community Mansion House
https://www.bbc.com/reel/playlist/hidden-historie
-

-
2016年3月1日朝日新聞8面民泊関連記事でのコメント
東京都大田区が、国の特区制度を活用して自宅の空き部屋などを旅行者に有料で貸し出す「民泊」を解禁
-

-
旅行業法の不思議① 旅行業と運送業、宿泊業、不動産賃貸業の境界
総合旅行業務取扱管理者試験という資格試験がある。その中に、旅行業法の登録を必要とするものはどれかとい
-

-
観光とタクシー論議 (執筆時 高崎経済大学地域政策学部教授)
最も濃密なCRM(Customer Relationship Management)が可能なはずのタ
-
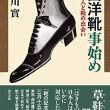
-
ホテルと旅館『西洋靴事始め』稲川實 現代書館
観光学でホテルと旅館の違いを説明するときに、私は芦原義信氏が西洋建築と日本家屋の違いを述べられた
-

-
動画で考える人流観光学 従と宿の相対化
https://youtu.be/-_Z9TeVxNtc https://youtu.be/X
-

-
一見さんお断りの超一流旅館のコンプライアンス
インバウンドブームがまだ本格的に始まる前、大連にある大学の観光学の教授から、中国の富裕層を数人日本
-

-
生産性向上特別措置法(規制のサンドボックス)を必要としない旅行業法の活用
参加者や期限を限定すること等により、例えば道路運送法の規制を外して、自家用自動車の有償運送の実証実験
- PREV
- 用語としての「人流」の発生
- NEXT
- 「衣食足りて礼節」をあらためて知る(2014年5月)

