広田照幸著『陸軍将校の教育社会史』1997年発行をよんで
公開日:
:
最終更新日:2019/07/07
軍隊、戦争
同氏の博士論文であり19回サントリー学芸賞受賞作である。原則、博士論文は条件として出版を義務付けられており、私も高崎経済大学の補助を得てイプシロン企画出版から発行させてもらったが、今ならインバウンドブームなので表現に工夫を加え、学芸賞にチャレンジできたかもしれない。
昨年亡くなった父親が陸士陸大であり、母親方の祖父は陸士27期であったから、どのような気持ちで道を選択したのか考えながら読んでみた。結論からすると時期により大きく異なり、家内の父親の時期は、都会の裕福な家庭の子弟は陸士より高等学校・大学を選択したようだ。浪速高等学校から東大法科に進学している。祖父の時代は軍縮期にかかっており、陸士は地方の中学校からの進学者が多かったようである。父親は1919年生まれであり、1935年頃といえば満州事変後、日中戦争直前の時代であるから陸士志願者が多かったのであろう。それでも本書では、東京府立一中の学生は一高東大が主流であったと本書は既述している。戦争経験者の運輸省先輩にはこのような人が少なからずいたことを思い出す。確か父親も東京に出てきたとき、一高の学生は違ったといっていたことを思い出す。
さて本書の備忘録である。
明治期に陸軍幼年学校、陸士に採用された者は、自ら資産を持たず「学歴エリート」への転身を余儀なくされた士族層であったが、西洋諸国と異なり、特権階級出身者のの優位は急速に失われ、間もなく平民層からの採用者が大半を占めるようになったとある。
軍人志願者の拡大は、将校のリクルート基盤を農業層へと拡大したが、最上層に位置する社会階層の子弟にとっては軍人は必ずしも望ましい進路ではなくなっていった。要するに日本の将校のリクルートの構造は、まもなく開発途上国型のモデルに近い、社会の中層部分と結びついたパターンとなっていった。
日清戦争前後からの将校生徒の大量採用は、エリート意識の強い陸士出身者の将校を過剰なほど作り出してしまった。軍人の子弟が軍人になるという再生産の割合が高かったが、貯蓄や資産形成に関心の薄い資産の少ない層として世代を繰り返した。
1920年代当初、陸軍中将佐藤鋼次郎は欧州将校に貴族や富裕層出身者が多いことの長所をとなえ、日本の将校のみじめさは富裕層の子弟を採用しなかったことにあり、学力試験のみを基準として将校生徒を採用してきた選抜方式に問題があった主張していた。
陸台に合格しないまま受験資格を失った者は「目の前が真っ暗になった気がする」ほどであったとある。
このようななか、昭和初年の陸軍将校は満州事変の勃発を聞いた。前線将校の不足をきたし、これが平時では考えられない無天組の規則的な進級と抜擢登用を可能にしたのである。ただし「何が戦時体制を生んだか」ではなく「戦時体制はいかなる心理構造の下で支えられたのか」という点に関して、陸軍将校の場合彼らの生活上の諸側面への関心を抜きにして語れないということである。
現在欧米の将校は、富裕層からのリクルートから次第に開発途上型のモデルへと移行している。その意味では日本の軍隊は遅れていたのではなく、先んじていたとの感想は面白い見方である。
霞が関の天下り問題も、背景は異なるが、軍縮期の軍人の姿に似ている。天下りがあり長く生活が保障されていることを前提に若年退職が当たり前になっていたが、最近の後輩は定年近くまで在職し、その後の保証も危うくなっている。そこに大量の専門職公務員が必要となれば、大いに歓迎されるであろう。アメリカも軍事衝突がなくなり、大量の将校が不要となれば状況は同じである。だからなかなか終わらないのかもしれない。
P366に少し衝撃的な記述がある。1921年生まれの憲兵である塚越正男が「自分が出世するには一人でも多くの中国人を殺害することであると思っていました。ですから拳銃の試し打ちと称して二人の子供の頭をぶち抜く訓練をしたり、新刀試し切りと称して斬首したこともあります」(1931年6月8日「読売新聞」。ただし『新聞編成昭和編年史』第6巻375pから引用)とある。今さらであるが、自虐史観ではなく、きちんと理解をしておかなければいけないことなのであろう。
関連記事
-

-
戦後70年の価値観が揺らいでいる」歴史家の加藤陽子氏、太平洋戦争からTPPとトランプ現象を紐解く 真珠湾攻撃から75年、歴史家・加藤陽子氏は語る「太平洋戦争を回避する選択肢はたくさんあった」 三国同盟の見方 歴史は後から作られる例
/https://www.huffingtonpost.jp/2016/12/0
-

-
ゲルニカ爆撃事件の評価(死者数の大幅減少)
歴史には真実がある。ただし人間にできることは、知りえた事実関係の解釈に過ぎない。もっともこれも人間
-

-
『中国はなぜ軍拡を続けるのか』阿南友亮著
第40回サントリー学芸賞(政治・経済部門)受賞!第30回アジア・太平洋賞特別賞受賞! 何
-
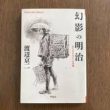
-
『幻影の明治』渡辺京二著 日本の兵士が戦場に屍をさらしたのは、国民の自覚よりも(農村)共同体への忠誠、村社会との認識で追い打ちをかけている。惣村意識である。水争いでの隣村との合戦
「第二章 旅順の城は落ちずとも-『坂の上の雲』と日露戦争」 著者は「司馬史観」に手
-

-
『戦争を読む』中川成美 「文学は戦争とともに歩む」は観光も戦争とともに歩む?
もし文学が、人間を語る容れ物だとしたら、まさしく文学は戦争とともに歩んだのである。しかし、近代以降の
-

-
田岡俊二さんの記事 陸軍は「海軍の方から対米戦争に勝ち目はない、と言ってもらえまいか」と内閣書記官長(今の官房長官)を通じて事前に働きかけた。だが、海軍は「長年、対米戦準備のためとして予算をいただいて来たのに、今さらそんなことは言えません」と断り、日本は勝算のない戦争に突入した。
昔、国際船舶制度の件でお世話になった田岡俊二さんの記事が出ていたので、面白かったところを抜き書き
-
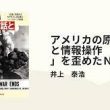
-
アメリカの原爆神話と情報操作 「広島」を歪めたNYタイムズ記者とハーヴァード学長 (朝日選書) とその書評
広島・長崎に投下された原爆について、いまなお多数のアメリカ国民が5つの神話・・・========
-

-
「戦争を拡大したのは「海軍」だった」 『日本人はなぜ戦争へと向かったのか戦中編』NHKブックス 歴史は後から作られる例
https://www.j-cast.com/bookwatch/2018/12/09008354
-

-
QUORA 第二次世界大戦 · フォロー中の関連トピック 米国は、日本の真珠湾攻撃の計画を実際には知っていて、戦争参入の口実を作るために敢えて日本の攻撃を防がなかった、というのは真実ですか?
回答 · 第二次世界大戦 · フォロー中の関連トピック米国は、日本の
- PREV
- 広田照幸著『日本人のしつけは衰退したか』を読んで
- NEXT
- 空港送迎サービスアプリの日本進出ニュース

