肥後交通グループの第2回オフサイトミーティングに参加して
公開日:
:
最終更新日:2023/05/20
路銀、為替、金融、財政、税制
チームネクストの番外の研修として、熊本県人吉市に所在する中小企業大学校研修室を使用して開催された、肥後交通グループの第2回オフサイトミーティングを傍聴させていただいた。チームネクストロンドン研修を一週間後に控えた機会だけに、ちょうど打ち合わせもかねてのいいタイミングでもあった。
研修のなかで、大畑誠也九州ルーテル大学客員教授の、定員割れし廃校の危機にあった県立高校の活性化の御苦労話を拝聴し、加賀市長時代を思い出しました。加賀市内の中学生の半数は市外の高校に進学する状況でしたから、市内県立高校三校はいずれも定員割れの状況でした。地産地学をスローガンに統合も視野に入れて検討を始めたのですが、尻切れトンボに終わり責任を感じています。この問題は全体のパイが増えないなかでの解決方策を探るものですから、矛盾があります。大畑校長先生が赴任された高校は、大畑先生の尽力で存続できるかもしれませんが、生徒の数が減少している全体としてみれば間違いなくどこかが廃校になるのですから、廃止能力のある校長先生が社会全体としては求められるのではと思って聞いていました。子どもが朝食をとらない問題解決に当たり、高校内で朝食を提供した苦労話も、私にとっては思いで深い話でした。加賀市でも「子どもの貧困」が社会問題化していました。俗にいう温泉場ですから、育児環境の劣悪な家庭の子供がそのまま成人し、そのまた子供も同じように育ってくる連鎖があります。きちんとした食事は学校でだされる給食一食だけという生活環境にある子どもに対して、地域社会で朝食を提供する運動が行われていました。温泉場以外の父兄からは、問題児を排斥して欲しい意見が出され、市長としては「子どもの社会的排斥」は絶対に認められないと述べたことがあります。
高校の定員割れ問題と同じことがタクシー業界でも起こっています。全体のパイが増えないなかで各社の競争行われますから、企業経営と交通政策は目的がずれるわけです。肥後グループの代表野々口社長から、受動喫煙防止法に先駆けて禁煙タクシーを導入した秘話をお聞かせいただきました。禁煙タクシーを導入するに当たっては、乗務員さんの売り上げ減への不安が最大の問題であったようです。給与歩合制をとるタクシーのビジネスモデルから来るものでもあります。野々口社長の判断はどうせやらざるを得ないなら先に実施したほうがいいということでした。乗務員さんへの説得は、「客は社長がつれてくる」と思わせることしかなかったようです。禁煙タクシーに好意的なマスコミの支援もあったのでしょう。乗客数はプラスマイナス零となり、成功したわけです。野々口社長のリーダーシップが発揮される結果となりました。
肥後交通グループでは乗務員さんのモチベーションをあげる工夫の一環として、この研修会を実施されています。タクシー会社の経営は、極端な自動運転車であれば、アルゴリズムの良しあしだけで決まります。現実は生身の乗務員さんが運転しますから、乗務員さんの能力に依存します。どこに人流が発生するか、乗務員さんの頭の中のアルゴリズムに左右されるわけです。流し営業の割合が高ければ高いほどその傾向がつよくなります。タクシ配車アプリは乗務員さんの頭の中のアルゴリズムより優れていないと使われませんから、優秀な乗務員の多いロンドンや東京での普及が今一つ進まないでしょう。ここでの問題も高校生の減少と同じことがあります。会社や乗務員さんにとっての問題、つまり個々の売り上げの増進と、業界全体あるいは社会全体の売り上げの増進とは、予定調和しない社会になってきているということです。人口減少社会に突入し、全体の需要は減少します。減少する中での競争ですから、全体として配車アプリの能力が上回れば、業界全体として導入したほうが効率がよいということになります。しかし、すぐれたアルゴリズムを持つ乗務員さんには不満が残ります。従って歩合制のビジネスモデルを変えないといけないということになります。
チームネクストのロンドン合宿を控え、つい、配車アプリのことを考えてしまうこのごろです。
関連記事
-

-
Quoraへの回答 コロナの感染リスクが高まることを承知でGoToキャンペーンを行っていた政府の意図は何ですか?Teramae Shuichi, 人流観光研究所長(観光学博士)
コロナの感染リスクが高まることを承知でGoToキャンペーンを行っていた政府の意図は何ですか?Ter
-

-
保護中: 『日本が太平洋戦争に総額いくらを費やしたか、知っていますか 』 国家予算の280倍の記事
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52599 毎年、この
-

-
『雇用破壊』森永卓郎著 角川新書 2016年 その他
森永卓郎氏は直接面識はないは、海外留学後日本専売公社から当時のいわゆる天上りで霞が関に出向し、その
-

-
観光資源としての「隠れキリシタン」 五体投地、カーバ神殿、アーミッシュとの比較
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産登録された。江戸時代の禁教期にひそかに信仰を続け
-

-
明治維新の評価 『経済改革としての明治維新』武田知弘著
明治時代の日本は世界史的に見て非常に稀有な存在である。19世紀後半、日本だけが欧米列強に対抗し
-

-
雲の会 露口洋介氏「人民元と中国の金融改革」
11月6日雲の会で露口氏の話を聞いた。 人民元の国際化は1994年に決定されていたが、アジア通貨危
-

-
動画で考える人流観光学帝国ホテル等に見る「住と宿の相対化」
https://youtu.be/21llSPlP5eQ https://yo
-

-
保護中: 対面型産業の物価注視を 危機後の金融政策の枠組み
対面型産業の物価注視を 危機後の金融政策の枠組み 日本経済新聞【経済教室】2020年6月29
-
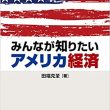
-
書評『みんなが知りたいアメリカ経済』田端克至著
高崎経済大学出身教授による経済学講義用の教科書。経済、金融に素人の私にはわかりやすく、しかも大学教


