『ミルクと日本人』武田尚子著
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
「こんな強烈な匂いと味なのに、お茶に入れて飲むなんて!」牛乳を飲む英国人を見た日本人の言葉である。だが明治二年、築地で牛乳が売り出され、日本人はその味に慣れていった。芥川龍之介の実家も牧場を経営し、渋沢栄一はそこから牛乳を取っていた。大正期には牛乳を加工したキャラメルが大流行した。関東大震災で緊急配布が行われ、敗戦後に児童の栄養を案ずる人々により学校給食への導入が進む。飲み物が語る近代史。
書評1
私は牛乳業界には属していない一般人です。歴史全般が好きでいろんな本を読むのですが、「江戸時代の日本人は牛乳を飲まなかった」というのを何かの本で読んで知っていました。ミルクホールというのがあったとか、日本人と牛乳を関係を知る断片的な情報はそこここで目にすることはあったのですが、時系列に沿って理解しやすくまとまった本はこれまで読んだことがありませんでした。
こちらの本では明治期からどのような経緯でどのような消費者を対象にして牛乳の消費が始まり、拡大していったのかが豊富な資料と共に読んで面白く解説されています。私はミルクホールというのを”外国文化に接することができる少し高級なバーのような場所”と勘違いしていたのですが、本当はどのような場所だったかもこちらの本を読んで知ることができました。
歴史全般に言えることですが、戦後の現代史をまとめるのは逆に資料に乏しく難しいことだと思います。歴史学関係者とお話しする機会があったときに「まだ、歴史になってない」という言い方を聞いて印象深かったのですが、新し過ぎる歴史は資料としてまとまらず、聞き書きをしたり、雑誌に散見される情報を拾い集めないといけず、かつその情報の信憑性の確認は難しいことだと素人ながらに思います。でも、明治乳業などで牛乳の歴史を知る古老に日本牛乳現代史について聞き書きができたらそれはとても面白いだろうと思います。
この本の副題に近代社会の”「元気の源」”と近代という言葉がついていますので、現代が語られていないからと言ってこの本の価値が下がるものとは思いません。その理由は自分の満足度通りの星5つとしました。面白く読める本ですよ。
書評2
日本で牛乳がどのように受け入れられ、広まっていったのかについて書かれた本。日本では、奈良時代に「蘇」と呼ばれる牛乳を10分の1まで煎じたものが租税のひとつとして朝廷に収められたり、江戸時代に長崎の出島にオランダから乳製品が持ち込まれたりした記録はある。江戸城には薬効の高い「酪」をつくるために白牛がいたという。しかし、そのような例外的なものを除くと、日本で乳製品が広まったのは文明開化以降のことである。
新政府きっての財政通である由利公正が牛に着目し、配下の2名に横浜居留地の外国人から搾乳と製酪技術を学ばせる。牧畜は新政府の政策に取り入れられる。雉子橋の牛馬商社に引き続き築地居留地に牧舎が設けられ「築地牛馬商社」ができた。事業が好調に推移したため、牧畜は民営化され、「牛馬会社」と改名され、福沢諭吉も後押しする。火事で施設はすべて失われたが、東京府知事になった由利の後押しもあって牧畜は広がる。前田留吉はアメリカに留学し、技術だけでなくジェルシー種(ジャージー牛)とホルスタイン種を日本に導入した。
内務省は開国によってもたらされた疫病対策にも力を入れる。明治8年には大久保利通の方針によって隣接した2つの大規模な官営試験場が作られた。この2つはその後合併して、下総種蓄場、さらには下総御料牧場になる。さらに三田育種場も作られる。各地で牧畜が奨励され、士族の受け皿にもなった。開拓によって開かれた北海道では人口が少ないため生乳より乳加工品に活路が見いだされるようになった。日本人には牛乳への抵抗感が強かったが、このような政府の後押しもあり、広く普及してゆく。渋沢栄一も牧場ビジネスに参入する。牛乳は当初は量り売りだったが、やがて瓶で配達するスタイルが確立してゆく。牛乳配達はだれでもできるビジネスとして広まった。混ぜ物対策や衛生対策も行われる。コレラ蔓延の対策として栄養豊富な牛乳が注目される。大相撲の高砂親方が牛乳屋を経営した話もある。また、ミルクホールというのがあった。関東大震災前には現在の山手線の周囲でも結構牧場があったことがわかるが、やがて郊外へ移転してゆく。
コンデンスミルクの製法が確立。アメリカでお菓子の修業をした森永太一郎が、やがてミルクキャラメルを発売してヒットさせる。牛乳は貧困層の子供への栄養提供手段としても励行され福祉的配給が行われた。平行して栄養食配給も始まる。関東大震災の被災者への提供も行われる。
国の加熱殺菌徹底の方針から大規模なミルクプラントが必要になった生乳業は、次第に集約化し、寡占化してゆく。戦争の足音が、子供たちの体力向上への関心の高さにつながって、牛乳を奨励する動きを後押しする。戦争および終戦直後の物資不足において牛乳も欠乏し、「ララ物質」と「ユニセフ」による脱脂粉乳の提供が行われる。味はまずかったが、学校給食と共に子供たちの栄養補給に大きな役割を果たした。
現代はスーパーやコンビニで牛乳を買うことが多くなったが、ミルクは飲用としてもチーズのような加工食品としても、国民に広く根を下ろしている。本書は、文明開化から終戦直後の混乱期までの記述が中心だが、EUとのEPA交渉で乳製品が大きな争点になったように、現代におけるミルクや乳加工食品も経済合理性・産業保護・消費者利益の点から揺れている。地方では、牧畜の後継者不足という大きな課題もある。真面目に書かれている本だが、戦後から現代のことについても、もう少し書かれてあればよかった。
書評3
1 明治初期に来日した英国人女性のイザベラ・バードは山形を旅していた時、久しぶりに牝牛をを見た。新鮮な牛乳を飲めると喜んだ。すると、そこにいた人々はみな笑った。「こんな強烈なにおいと味なのに、お茶に入れて飲むなんて」誰もが胸が悪くなるという。
日本人には乳は子牛が飲む以外に考えられなかった。「人間が飲むなんて」と笑い出しのである。
当時、牛乳はお茶に入れる、つまり牛乳を薄めて飲むと、バードは言ったのである。その後、日本人は牛乳はそのまま飲むよりも他の液体と混ぜて、、つまり牛乳を薄めた方が喉越しが良かったようである。
日本人の性質を現わして面白い。何事も一気に本物とぶつからず、徐々に様子をみてならす習性からだと思う。
2 明治40年代以降、都市における牛乳が需要されたのはミルクホールだった。ターゲットは学生、書生などの若い知識人層であった。
本郷、神田、牛込、芝周辺に多くあった。店はガラス戸で見通しが良く、気軽には入れた。注文すると、角砂糖一個か二個つけて出してくれる。牛乳、食パン、カステラ、ドーナツの菓子が普通だった。
さらに、新聞雑誌、官報を自由に読めた。
これは、現在の喫茶店とよく似ているが、最近、新聞や雑誌を出さないマクドなどが主流になってきた。昔は牛乳がコーヒーの代わりになっていたよだ。昔も今も勉強する場所であったのは変わりないようだ。
3 大正8年の段階で、牛乳は日常飲料にはならず、身体に不調が生じたときの補助飲料だった。しかし、牛乳販売店は身近にあり、中間層の収入があれば容易に飲めた。
4 宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』が出来た大正13年だった。ジョバンニが行った牛乳屋は「ポプラの木が幾本も幾本も、高く星空に浮かんでいるところ」であ「黒い門」があり、小岩井農場の牛舎を彷彿とさせる。銀河のミルクは、家族の病気と労苦の中で沈んでいた少年の心に、「本当の幸せ」を求める旅を歩む勇気をよみがえらせた。
この一文を読んで、ふと、宮沢賢治本人は牛乳が好きだっとのだろか、と疑問に思った。なぜなら、賢治は菜食主義者だと聞いているから。旅行で岩手に立ち寄ると、是非とも小岩井農場を尋ねて、再度想像してみたい。
5 昭和12年(1937年)の盧溝橋事件の勃発事件によって、東京市では警視庁は急に、子どもに牛乳を飲ませる方針を打ち出した。日中戦争と直結させて子供たちの体位向上が目標だと説いた。学校牛乳が進みだした。
しかし、乳幼児の死亡率を下げ、子どもが元気に育つことが目標というよりは、「お国のため」に死ねる身体作りのためだった。
お国のために死なせるための一時的体力作りの牛乳とは。僕が、中学生時代、塾の先生で戦争に行った人がいて、「一日、牛乳7本飲んだね」と自慢していたのを、今、思い出した。その先生は90歳ほどで亡くなられたが、よほど牛乳が好きらしかった。歩くのも普通の人よりかなり早かったし、いつも元気があるように見えた。何となく、牛乳と健康のイメージが重なる。
6 戦後、結核が流行った。政府は医療費より食費に投入した方が将来、財政負担が軽減できる、とGHQ方針を受け入れた。結核患者が増えるのは米食だと、非難された。改善方法として、ミルクと牛乳の摂取を重視した。そういう経緯で学校給食に牛乳を採用した。
7 現在も牛乳の宅配はあり、都市部の宅配小売店の顧客はおよそ300件前後で、配達員は一人50軒前後担当している。
独居老人が増加している現在、戸口配達が安否確認につながる。飲んだ空き瓶が出ていれば元気な証拠だ。
牛乳はコンビニでもスーパーでも簡単に買える。しかし、老人には寝たきりの人もいることだし、宅配で話もできる。これから、日本はますます老人ばかりになる。そんな時、気軽に話ができるのは、牛乳に限らず、宅配業者だと、思う。ただ、配達するだけでなく、やさしく世間話ができる業者が有望が栄える時代だ、と思う。
関連記事
-
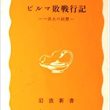
-
動画で考える人流観光学 『ビルマ敗戦行記』(岩波新書)2022年8月27日
明日2022年8月28日から9月12日までインド・パキスタン旅行を計画。ムンバイ、アウランガバード
-

-
QUORA 第二次世界大戦 · フォロー中の関連トピック 米国は、日本の真珠湾攻撃の計画を実際には知っていて、戦争参入の口実を作るために敢えて日本の攻撃を防がなかった、というのは真実ですか?
回答 · 第二次世界大戦 · フォロー中の関連トピック米国は、日本の
-

-
運輸省(航空局監理部長)VS東亜国内航空(田中勇)のエピソード等
https://www.youtube.com/watch?v=flZz_Li7om8
-

-
朝河寛一とアントニオ猪木 歴史認識は永遠ではないということ
アントニオ猪木の「訪朝」がバカにできない理由 窪田順生:ノンフィクションライター経営・戦略情
-

-
学士会報926号特集 「混迷の中東・欧州をトルコから読み解く」「EUはどこに向かうのか」読後メモ
「混迷の中東」内藤正典 化学兵器の使用はアサド政権の犯行。フセインと違い一切証拠を残さないが、イス
-

-
QUORA ゴルビーはソ連を潰したのにも関わらず、なぜ評価されているのか?
ゴルバチョフ書記長ってソ連邦を潰した人でもありますよね。人格的に優れた人だったのかもしれませんが
-

-
『シベリア出兵』広岩近広
知られざるシベリア出兵の謎1918年、ロシア革命への干渉戦争として行われたシベリア出兵。実際に起
-
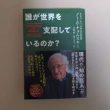
-
ノーム・チョムスキー著『誰が世界を支配しているのか』
アマゾンの書評で「太平洋戦争前に米国は自らの勝利を確信すると共に、欧州ではドイツが勝利すると予測
-

-
「若者の海外旅行離れ」という 業界人、研究者の思い込み
『「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書
