本当に日本は職人を尊ぶ国であったのか?
公開日:
:
最終更新日:2019/07/02
観光資源
司馬遼太郎氏は、韓国、中国との比較においてなのか、『この国のかたち』のなかで、「職人。実に響きがよい。日本は世界でも珍しいほど職人を尊ぶ文化を保ち続けてきた。近隣の中国や韓国では職人を必要以上にいやしめてきた事に比べれば、日本は「重職人主義」の文化だったとさえ言いたくなる」と記述している。
国民的作家が唱えると拡声器効果も伴い、ネットでもそのことが叫ばれる。 https://www.yuske.net/2018-09-22-01/
しかし、1910年ロンドンで開かれた日英博覧会では、156人という多くの芸人職人が出演し、期待通り多くの英国人の関心を引いた。これに対して長谷川如是閑は、東京朝日新聞の記事で日本人の芸人職人の余興を恥じている。国民新聞や時事新報の記者も恥じていることがことがうかがえる。
関連記事
-

-
🌍🎒シニアバックパッカーの旅 資料 ハルハ川戦争 戦跡観光資源
https://youtu.be/RijLPLzz5oU 中国とロシア
-

-
『訓読と漢語の歴史』福島直恭著 観光とツーリズム
「歴史として記述」と「歴史を記述」するの違い なぜ昔の日本人は、中国語の文章や詩を翻訳する
-

-
戦陣訓 世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例
世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例である。「もはや戦後ではない」は私の
-

-
プロテスタンティズムと現代政治 学士會会報NO.927 2017年Ⅵ 深井智朗 pp24-27
マルティン・ルターによる神聖ローマ帝国の宗教の改革は、彼の意図に反して、すぐに政治化し、彼の死後まも
-

-
『源平合戦の虚像を剥ぐ』川合康著 歴史は後から作られる
源平の合戦は全国で、観光資源として活用されている。「平家物語」の影響するところが大きい。また、文
-

-
『動物たちの悲鳴』National Geographic 2019年6月号
観光と動物とSNS https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/m
-

-
観光資源と伝統 『大阪的』井上章一著
今年も期末試験問題の一つに伝統は新しいという事例を提示せよという問題を出す予定。井上章一氏の大阪
-

-
「元号と伝統」横田耕一 学士會会報No.937pp15-19
元号の法制化に求めた人々に共通する声は元号は「日本文化の伝統である」というものだった。 一世
-
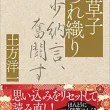
-
『枕草子つづれ織り 清少納言奮闘す』土方洋一 紙が貴重な時代は、日記ではなく公文書
団塊の世代が義務教育時代に学修したことの一部が、その後の研究により覆されている。シジュウカラが言
-

-
大衆軍隊出現の意味 三谷太一郎講演メモ 学士会報2018-Ⅳ
226事件は、天皇の統帥権の名目化 軍隊の大衆化 軍隊内の実権は将官、佐官、尉官へと下降した
