野波健蔵氏のドローンの話 2016年4月6日 サトーホルディングス講演会
サトーホールディングスの小玉昌央さんのご配慮で、ドローン問題の第一人者の野波健蔵氏の話を聞く機会を得た。
読み物としてはこれまでも接してきたが、人の話をまとめて聞くことは今回が初めてであった。昨年のモンゴル・ツータン族観光調査でドローンを飛ばしたことなどが懐かしく思えた(2015年8月ブログ掲載)。
野波氏の話を聞いて、ジオフロントを思い出した。運輸省の現役時代、同期が大深度地下鉄問題に取り組んでいた。当時はマスコミを挙げて最後のフロンティア空間として、大深度地下を取り上げており、官邸から各省に至るまでこぞってこの問題に関心を示していた。バブルがはじけ、鉄道の意味も変化し、今では大深度問題は過去のこととなってしまっている。
野波氏は、地上300メーター空間が最後の空間フロンティアであり、この活用がドローンの使命であると話されていたが、直感的には大深度空間と同じで、限られた場面に活用されるものではないかと思った。ドローンは、アフガニスタンやイラクでの米軍兵士の代わりをする遠隔操作の無人爆撃機の技術が民間転用されるようになったことから始まっている。経済性を考えなくてよい軍需だから可能であったのだろう。戦争の場面は、マスコミも観光も刺激を求めるところから大きな資源となっているが、エアコンのきいた部屋で民間人を巻き込む恐れのある爆撃をゲーム感覚でするのであるから、人間の感覚がくるってしまうのではないと思う。
ジオフロンとも高度300メーターフロントも人の管理可能性が大きくなると、必ず所有権、管理権といった法的な問題に直面する。大深度地下鉄が検討されたのも、地上権設定をなくす議論から始まったが、憲法で保障されている財産権に触れるから大問題であった。高度300メーター空間の管理も論理的には同じ問題を抱える法律問題である。そのうえでの航空法の行政問題が出てくるのであろう。ドローン技術により管理が可能となればなるほど財産権も主張されてしまう。
ドローン技術の活用に、人を運ぶSF的なTerrafugiaのはなしがあった。https://youtu.be/wHJTZ7k0BXU
水陸両用車をはじめこの種の話は夢があるのであるが、実需が少なく夢で終わってしまうことが多い。同じ夢なら観光としては宇宙観光なのであろう。いずれにしても、有人ドローンはその昔からある垂直離着陸機の発想であり、議論が拡散気味になってしまう印象を持った。
ドローン技術は、最先端の技術というより応用技術であると感じた。また、構造物の検査等への需要が考えられるが、昆虫や小形動物のロボットが開発されれば無理やり空を飛ぶこともないであろう。むしろこのような展開になってゆくような気がする。物流分野への応用も、無理に運ばなくてもよいものは3Dプリンターにとってかわられるのではないだろうか。ドローン等は、極端に言えば位置情報技術と認識技術の組合せであるから、日本も参加できる。認識技術は人工知能の進展が最先端であり、その成果をドローンも取り入れる形で進むのであろう。朝日デジタル版に囲碁を打ちまかしたAIの記事が出ていたので、最後にのせておく。
AIは人の脅威か アルファ碁の圧勝、研究者の評価は 聞き手・辻篤子、池田伸壹 聞き手・川本裕司2016年4月9日05時00分
■ソニーコンピュータサイエンス研究所社長・北野宏明さん「問われるのは人間」
――今後AIはどう進化していくのでしょうか。
「世の中の多くの課題には、碁や将棋のようなゲームとは違って、不確かで不完全な情報しかありません。たとえば車の運転の際は、ほかの車も走行し、歩行者もいる。それぞれが意図を持ち、必ずしも合理的に動かない。陰から飛び出してくることもある。雨や雪もある。ゲームが完全情報問題とすると、不完全情報問題がAIにとって今後の挑戦相手です」
――今後一番注目されるのは自動運転ですか。
「先日、ニューヨークで開かれた完全招待制の『人工知能の将来』シンポジウムに日本からただ1人参加しました。一番盛り上がったのが、自動運転の今後の展開に関する議論でした。つまり、自動運転が実用化されれば、車というものががらりと変わる可能性がある。本来的には移動手段だから安全に移動できればいい。ライドシェアも広がるなか、自分で車を持つ意欲が減り、人間が車を運転するのはぜいたくな行為になるかもしれません。そもそも車の90%は動いていないともいわれ、いわば不動産。車の概念を根本的に変えた方がいいかもしれません」
――車文明自体が変わると?
「移動という本来の役割に立ち戻り、ネットワークを介したサービス全体の文脈でとらえ直すと、車は主役ではなくなります。中心はAIやネットワーク技術で、車は通信システムにおける携帯端末のようになるかもしれない。米国のAIやIT企業は今、自ら主導権を握って自動車産業を再編し、新たなサービス体系を作ることにすごいエネルギーを注いでいます」
関連記事
-

-
🌍🎒 🚖シニアバックパッカーの旅 2018年9月12日 チームネクストモスクワ調査⑥ モスクワ市交通局等
モスクワ市の国際局の取り計らいで交通局及び観光局を訪問し、意見交換した。観光局からは最近のモスク
-
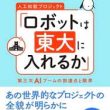
-
自動運転車の可能性『ロボットは東大に入れるか』新井紀子
自動運転車の可能性は、「自動」の定義にもよるが、まったく人間の手を借りないで運転することはかなり遠い
-

-
ロンドンのミニキャブは自家用か営業用か? Uber論争を通じて
○ロンドンのUber 事実関係は不明ですが、minicabの手配をUberは実施しており、m
-

-
旅行業法の不思議③ 「旅行業務取扱料金」と「定額タクシー料金制度」
旅行業務取扱管理者試験では、「旅行業者は料金を定め観光庁長官の認可を受けなければならないか否か」とい
-

-
東京交通新聞 2021年5月投稿原稿 タクシー運賃等とパック料金の関係を理解するには
特別寄稿 タクシー運賃等とパック料金の関係を理解するには ㈱システムオリジン 人流
-

-
ヘルシンキのKutsuplus Maasより先にあったもの
㈱システムオリジンから出版した「観光・人流概論」169ページにヘルシンキのKutsuplusを紹介
-

-
出張向け「定額航空運賃サービス」の記事
NEWSPICKSに、出張向け「定額航空運賃サービス」が米国で登場 という記事が紹介されていた。Bl
-

-
侮辱されたUber運転手の報道と欧州での訴訟報道
CNNは、NYPD警官がアメリカに来て2年のUber運転手を侮辱しているニュースを流しています。NY
-

-
「セブンタクシーが山手線で中国語広告を出したワケ」
日経ビジネス2015年4月10日に、「セブン銀行が山手線で中国語広告を出したワケ ATMのガラパゴス

