位置情報革命が生み出す黒船Uberと自動運転車 (ジャパンナウ観光情報協会2014年1月)
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
ジャパンナウ観光情報協会, ライドシェア
GPS、スマートフォンの登場により位置情報の手軽な把握が可能となった。ネット検索最大手のGOOGLE社はこの位置情報に敏感である。Uberを買収 し、自動運転技術開発にも乗り出している。2001年に東京交通新聞社から「モバイル交通革命」を出版させてもらい、それがご縁で、桑原守二氏(元NTT副社長)を中心に位置情報研究会を立ち上げ、携帯電話にはメールの次にGPSを標準装備すべきと主張した。現実はデジカメが先行した。盗撮なる言葉が生み出されたくらいであり、映画の出現時も「入浴中の奥様」を期待させていたから、現実のニーズに適合したという意味では正解だったのかもしれない。2009年システムオリジン社(タクシー無線のシステム設計会社)から「ユビキタス時代の人流」を出版し、電波のレールが鉄道と自動車の法的垣根をなくすと予言した。 スマートフォンはカーナビを席巻する勢いでマンナビを普及させ、オンデマンドタクシーのUberシステム(正確には旅行業)も日本に上陸した。これに乗り放題運賃制度(月極めパッケージツアー)が組み合わされれば、モバイル交通革命で主張した総合生活移動産業「指タク」(親指一つでいつでもどこでも呼び出せるタクシー)が実現するはずである。 2013年モーターショーでは自動運転車が展示された。高齢時代に突入し30万人は存在すると推測される認知症の運転免許保有者が問題視されているからである。自動車を人間の自由な運転に任せるより半分機械任せ、コンピュータ任せの運転にゆだねた方が、自動車はずっと安全で合理的な乗り物になるはずだという考えが世界中で強まり始めている。日産は2020年までに市場に出すと宣言している。知の巨人・立花隆氏はこの自動運転車はロボットであり人工頭脳としている(文藝春秋2014年2月号「自動運転の時代」)。 将来、位置情報とヒトを移動させる脳の働き情報の分析が進めば、科学的な人流学が成立し、古典的な観光学は終焉するであろう。
関連記事
-

-
ジャパンナウの今後の原稿 体と脳の関係の理解
心と体が一致しない人たちへの理解も進み、オバマ大統領はStonewallをアメリカ合衆国の
-

-
「ハイヤー配車サービス「UBER」、韓国ではついに法違反で関係者立件」という報道とそれに対するコメント
ネットで下記の報道が流れている。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/at
-

-
ジャパンナウ予定原稿 感情と観光行動
観光資源に対して観光客に移動という行動をおこさせるものが感情である。言葉を換えれば刺激であ
-

-
🌍👜シニアバックパッカーの旅 ジャパンナウ観光情報協会2016年3月号原稿 スマホで海外旅行の未来
二月中旬に中東・東アフリカを駆け足で旅行した。ネットで予約から決済まで行った。スマホに搭乗の注意喚起
-

-
事業所管官庁と規制官庁 グレーゾーン解消制度の運用に関する感想
若いころ、運輸省大臣官房情報管理部情報処理課に勤務した。当時から何をしているところですかと聴かれ困っ
-

-
奢侈禁止令とGOTOキャンペーン (ジャパンナウ原稿)
個性を重視するはずのものである観光は、本来権力とは無縁であり、権力を前提とする政策と結びついた観
-

-
ジャパンナウ観光情報協会機関紙138号原稿『コロナ禍に一人負けの人流観光ビジネス』
コロナ禍でも、世界経済はそれほど落ち込んでいないようだ。PAYPALによると、世界のオンライン
-
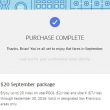
-
ウーバーが「100ドルで乗り放題」 NYでも定額サービスを開始
フォーブスジャパンに乗り放題サービスの記事が出ているのをNEWSPICKSが紹介していた。
-

-
東京交通新聞 2021年5月投稿原稿 タクシー運賃等とパック料金の関係を理解するには
特別寄稿 タクシー運賃等とパック料金の関係を理解するには ㈱システムオリジン 人流
-

-
New 3PHL(Third party human logistics) Transport app Moovit has arrived in Australia(http://mashable.com/2015/03/30/transport-app-moovit-australia/#:eyJzIjoiZiIsImkiOiJfeW80dTUya2M5cGVmdG95dSJ9)
ロンドンではタクシーの配車アプリを調査して、つくづく3PHL(サードパーティ人流)の時代が来ていると
- PREV
- 観光とタクシー論議 (執筆時 高崎経済大学地域政策学部教授)
- NEXT
- 人流・観光論議
