「今後の観光政策学の方向」 人流・観光研究所所長 観光学博士 寺前秀一
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
人口、地域、
① 旅が大衆化すると「Tourist」概念が生まれるのだとすると、日本における「Tourist」概念の誕生時期は、「お伊勢参り」が発生した18世紀の江戸時代であろう。百年単位のずれはあるだろうが、中国も欧州もほぼ同じ時期ではないかと考える。日本では、概念は誕生してもそれをあらわす字句は統一されなかった。またその社会的必要性も少なかった。その概念をあらわす字句に「「遊覧人」「遊歴人」が使用されるならば混乱はなかった。しかし日本では、特殊な字句「観光客」に収斂していった。
② 日本では、1930年前後に外貨獲得政策が重要政策として打ち出された。外客誘致をする国際観光局が設置され、次に輸出促進をする貿易局が設置された。外国人用に「国宝保存法及び国立公園法」が制定された。政府が字句「観光」を採用したことにより、概念「観光」は急速に字句「観光」に収斂していった(英文表記はTouristを使用しており、平仄はあっていない。)。朝日新聞・読売新聞記事データ分析によりそのことが実証される。鉄道省は観光の語源を易経に求めた。従来の易経の解釈はアウトバウンドであるが、鉄道省は「インバウンド」の意味に変化させて使用した。易経の観光は「国の光りを観に行く」である。この場合の国は、古代中国では都市(欧州も同じ)を意味するから「クロスボーダー」概念である。このことが影響して字句「観光」はクロスボーダー概念を伴ったものとして使用されていた。このことも、朝日新聞・読売新聞記事データ分析により実証される。
③ 鉄道省が行った国際観光政策は外貨獲得が目的であるが、外国人の財布をねらうようであるとの印象を避けるため、ことさら外国人に「帝国日本の文化を見せる」という姿勢を見せることとなった。海外における観光宣伝事業とともに、日本国内における外国人用の観光施設の整備を行った。当初は、観光施設は外国人用と日本人用は区分し易かった。しかし、次第に日本人の生活の洋風化に伴い、違いが小さくなっていった。そのうち、観光資源整備は、本音では日本人観光客用の為に実施されるようになっていった。そのため、自治体、地方観光協会の政策は「内主外従」と呼ばれた。ただし、戦時体制に移りつつあり、字句「観光」は前面に出ず、陸軍の要請で設置された厚生省を中心に、字句「レクリエーション」、「休養」が全面に出ることとなった。この政教は戦後の政策にも継続した。 終戦直後も外貨獲得が国是であり、観光道路の整備は外貨獲得のため行われた。厚生省の政策展開(旅館行政、国立公園行政、温泉行政)は字句「ソーシャルツーリズム」を使用して行われ、字句「観光」は使用されなかった。
④ 21世紀にはいり、人口減少社会を迎えた。交流人口を拡大することが自治体の存在価値となった。そのため、すべての自治体が地域観光政策を展開し始めた。外貨獲得は観光立国推進基本法の目的から消滅した。その目的は「地域の誇りを見せる」こととなった。黒部アルペンルートの開発者佐伯宗義は観光とは他の地域との違いを示すことであると主張した。しかし「政策」とは人々の間の違いをなく為の権力行為である。当然「観光」と「政策」には内部不協和な存在することとなる。
⑤ 交通法では、規制緩和により、日常交通と非日常交通の区別を廃止している。さらに政策全般にわたり、日常と非日常の相対化現象が発生している。観光の為の移動とそれ以外の移動を区分する社会的必要性がなくなってきているのである。そこで私は人流概念を提唱している。物流概念と同様、人流概念の方が、新しく発展しつつあるサードパーティビジネスに対応し易い。
⑥ スマホ等による位置情報の取得は、人流情報のビッグデータ解析を可能とさせている。しかもウェアラブルデバイスの進展は、観光資源に対する人体反応をリアルタイムで把握することを可能とさせる。今後の観光政策研究の展開は、ウェアラブルデバイスを活用した、観光文化遺伝子の発見にあるのではなかろうか。
関連記事
-

-
動画で考える人流観光学 観光活動論 訪問者数の推移
https://fb.watch/kEjmTswC1L/?fs=e&s=cl
-
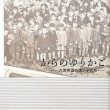
-
『からのゆりかご』マーガレット・ハンフリーズ 第2次世界大戦後英国の福祉施設から豪州に集団移住させられた子供たちの存在を記述。英国、豪州のもっと恥ずべき秘密
第2次世界大戦後英国の福祉施設から豪州に集団移住させられた子供たちの存在を記述。英国、豪州のもっ
-

-
Quora Covid-19の死亡者はアメリカが27.9万人、日本が2210人 (12/06現在) です。日本では医療崩壊の危険が差し迫っているとの報道がありますが、アメリカに比べて医療体制が貧弱なのでしょうか?
12月16日現在、アメリカでの死亡者数は約30万4千人、そして日本での死亡者数は2600名足らずで
-

-
書評『人口の中国史』上田信
中国人口史通史の新書本。入門書でもある。概要〇序章 人口史に何を聴くのかマルサスの人口論著者の「合
-

-
めも 「ドイツにおけるカジノ規制 ―ゲームセンターとの比較の観点から―」 国立国会図書館調査及び立法考査局 専門調査員国土交通調査室主任齋藤 純子 海外立法情報課渡辺 富久子
人間の射幸心に働きかける賭博には様々な形態があり、それぞれ固有の発展と規制の歴 史を有する。例えば
-

-
東京オリンピック・パラリンピック時代の医療観光(日本医療・病院管理学会講演要旨)
都市の魅力を訪問客数で競う時代になっている。ロンドン市長が世界一宣言を行ったところ、パリが早速反駁し
-

-
保護中: 米国コロナ最前線と合衆国の本質(5) ~メディアが拍車をかける「全く異なる事実認識」:アメリカのメディア統合による政治経済と大統領支持地域のディープストーリー
印刷用ページ 2020.07.08 米国コロナ最前線と合衆国の本質(5) ~メ
-

-
◎『バブル』永野健二著
GHQの直接金融主体の経済改革からすると、証券市場と証券会社の育成が不可欠であるにもかかわ
-
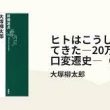
-
『ヒトはこうして増えてきた』大塚龍太郎 新潮社
p.85 定住と農耕 1万2千年前 500万人 祭祀に農耕が始まった西アジアの発掘調査で明らかにさ

