英和対訳袖珍辞書と観光
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
人流 観光 ツーリズム ツーリスト
先週は都立中央図書館が図書整理のため休館日が続き、ようやく土曜日(6月13日)に閲覧に行くことができました。我が家からは徒歩圏内にあり、都税納税者としては十分にその便益を享受しています。
6月27日に日本観光学会で字句「観光」と字句「tourist」の遭遇と題して、日本の国内観光政策の展開が特殊であったことを解説したいと思っています。そのため、字句「tourism」の訳語が当初どのような日本語であったかを再確認したいと思い、『英和対訳袖珍辞書』を閲覧に行きました。江戸時代辞書は通詞の秘本とされていたようですから、一般の人が簡単に読むことはできなかったようです。従って、統一的な訳語の誕生にも限界があったと思われますが、この英和対訳袖珍辞書(袖珍辞書とはポケット辞書)が発行されて、当時の先端をゆくインテリの使用する訳語はかなり統一されてゆくことになったのではないかと推測します。
さすがは中央図書館です。1862年の初版と1869年版が収蔵されていました。めぼしい観光関係語の対訳を下表にまとめました。
| 1862年訳(初版) | 1869年訳 | |
| Tour | 周ルコト 旅行 | 周ルコト 周行 |
| Tourist | 旅行スル人 | 周行スル人 |
| Travel | 旅 | 旅 歩行 |
| Traveller | 旅人 | 行人 旅人(リョジン) |
| Excursion | 遠ザカルコト | 遠ザカルコト ウロツキマワルコト |
| Leisure | 間隙ノ時 | 間隙(ヒマ)ノ時 |
| Recreation | 性替スルコト 楽シミ 慰ミ | 慰サメルコト 楽マスルコト |
勿論、私が最初に探したのは「Tourism」と「Sightseeing」なのですが、辞書に掲載されていませんでした。その理由は不明ですが、①英語として字句「Tourism」が確立していなかった②英語として字句「Tourism」は確立していたが、日本には紹介されていなかった③紹介されていたが、適当な訳語が確立していなかった、という理由が考えられます。Wikipediaによれば「The word tourist was used by 1772 and tourism by 1811. 」とありますから理由①は該当しないのかもしれませんが、羽生敦子さんの論文等において字句「Tourist」は明確に登場するものの、字句「Tourism」は登場しません。これからの若手観光学研究者の調査課題ではないかと思っています。明治期の主な英和辞書、国語辞典は東京都立中央図書館に収蔵されていますから、簡単に読むことができます。同時の文献と照らし合わせて分析することが可能です。また、中国語と英語の対訳辞書についても同様の研究を進めてもらい、旅游とTourism、Touristの関係を解明してもらえればと思っています。
現在は元号法に基づく政令により「平成」の世です。その語源について、内閣は『史記』、『書経』にあると説明しています。その語源に関して政府見解に異論を唱える民間人が存在するようですが、名前をつけた人の意図が語源を決定するのでしょうから、この場合は政府見解が語源だと思います。私の名前の秀一は「ひで」という母方の祖母の一番めの孫という意味だと思っていましたが、人には「秀才の一番になるように」という意味で両親がつけたのでしょうと言われました。亡き母親は「一芸に秀でるように」と付けたといっていましたから、やはり命名権者の意向が正式の語源なのでしょう。
観光の語源については、上田卓爾氏や溝口周道氏等の研究が大いに観光学の発展に寄与していますが、法令用語としての語源は明確です。1930年勅令「国際観光局官制」の制定の際の鉄道省の見解が「易経」を語源とするとしていますから、法令用語の語源は「易経」です。その易経の解釈の仕方が「アウトバウンド」ではなく「インバウンド」であっても、語源には変わりはないでしょう。語源はともかく、その後の法令上の「観光」の概念が1930年時から変化するのは、法令用語であっても、ある程度は当然です。もっとも観光基本法制定時は「世間で使われているのと同じ意味」であるとして定義付けを放棄したと伝承されていますが、定義をする必要性がなかったということで、観光に関しては規範性が求められる法令がなかったということでしょう。
従って語源論も相対的なものではないかと思っています。法令用語の語源は、その規範力には影響しませんが、易経だということになります。立法者の意図がそうだからです。世間で言う「観光」の語源論はこれからも研究が進められるでしょう。
私が日本観光学会において発表する予定の論文では、語源論ではなく「遭遇」と表現させていただきました。字句「Tourist」と字句「観光」には「ずれ」があります。「Tourist」であれば、理屈上は「観光外人」「漫遊外人」「観光客」であって、「観光」ではないからです。しかしながら国際「観光」局の訳語は「Board of Tourist Industry」とされました。明治の初期でしたら「tourism」が日本にとって新しい概念であれば、適当な漢語を用いて訳語を造語したと思いますが、概念「観光」と概念「Tourism」が同じものとして、字句「観光」と字句「Tourist」が使用されたのです。この点が面白いところです。「Tourist Industry」と対訳されたのは「インバウンド」の目的が明確であったからでしょう。「アウトバウンド」であれば政策としては当時はまだ時期尚早であったでしょう。法令用語が「観光」になりましたので、朝日新聞記事検索によれば、その後は世間でも字句「観光」の使用が他の用語に比べて多くなりました。もし、鉄道省が概念「Tourism」に字句「旅游」「遊覧」を用いていたとしたら、その後の観光政策の展開の仕方も変わっていたかもしれませんし、字句「観光」の語源論も注目されなかったかもしれません。
関連記事
-

-
二月五日チームネクスト総会講演「総合生活移動産業の今後の展望」(45分)趣旨 人流・観光研究所長 寺前秀一
二月五日チームネクスト総会講演「総合生活移動産業の今後の展望」(45分)趣旨 人流・観光研究所長
-

-
保護中: 動画で考える人流観光学(開志) 2024.2.29 まとめ テストと生成AI
地域産業研究(観光)第3・4学期/第4学期の定期試験の試験問題 問1 2040年における「観光」
-

-
「人流」概念 2021新語流行語大賞トップテン
https://twitter.com/i/broadcasts/1dRKZlpyPBMJ
-

-
フィンランドからロシアへの入国など
ィンランドからサンクトペテルブルク(サンクトペテルブルグ)への移
-

-
定住(観光の逆)と言語のことをわかりやすく説明した対談 (池谷裕二(脳科学者)×出口治明(ライフネット生命会長))
出口:動物行動学者の岡ノ谷一夫氏に、言語はコミュニケーションから始まったのではなく、考えるツールとし
-
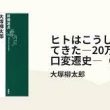
-
『ヒトはこうして増えてきた』大塚龍太郎 新潮社
p.85 定住と農耕 1万2千年前 500万人 祭祀に農耕が始まった西アジアの発掘調査で明らかにさ
-

-
Touristic problem of Jeju island richer than Okinawa and Kyushu held ~ Participation in press tour ~
It was a short time from November 2 to 4, but I pa
-

-
重慶旅行 重慶の大きさ
https://www.facebook.com/share/1G31QjFCF1/?mibexti
-

-
TravelerとTouristの違い
観光学会等関係者には興味深い記事の紹介。英米人が両者の違いをどう考えているかよくわかる。trave
-

-
福田村事件 霧社事件
https://youtu.be/s-zWKhVIBow 福田村事件(ふくだむらじけん)は、1
- PREV
- 🗾🎒シニアバックパッカーの旅 尾端国次氏と草津温泉
- NEXT
- 日本語辞書と英和辞書に見る「観光」

