by them 美しい日本、なのか?海外で気づいた「衛生」意識の違い
公開日:
:
最終更新日:2023/05/30
躾、接遇
新型コロナウイルスに対する不安は、外出禁止令や緊急事態宣言が緩和されたあとでもしばらくは拭えない。このパンダミックにおける生活習慣の変化や、ビジネスモデル、仕事のやり方など、いままでとは違ったものが、そのまま日常に定着すると思います。
日本では当たり前であったマスクの習慣は、そもそもアメリカやヨーロッパにはないものでした。しかしこれから先も、欧米のマスクの需要は当たり前に定着するでしょう。
マスク習慣がもともとあったことから見ても、日本人のほとんどが衛生観念が高く綺麗好き。国内では除菌関係の商品が多く販売されていて、潔癖な方も多いイメージがあります。土足で生活するアメリカ人の生活スタイルは、日本の人にとっては理解できないかもしれません。しかしそんなアメリカから見ても、日本の衛生に関する文化やスタイルに驚くことは多々あるのです。
たとえば、食べ物を提供する場所。アメリカの回転すし店では、必ず1皿1皿に蓋がついています。調理された料理が蓋もなく並んでいるような状態はあまり見かけません。
アメリカのストアにもデリがあります。トングでさまざま料理(サラダ)などを自由に選び、容器にいれて買うスタイルもあるし、レストランでもビュッフェスタイル(バイキング式)で食事を提供しているところも多い。しかし温かいものは温めてある状態で必ず蓋付き、冷たいものは冷たい状態を保って提供されているのです。
たとえば日本で見かけるような、大皿に盛られた料理がラップも掛けずにカウンターに並べてあったりすることなどはありません。アメリカではアウトです。
日本では自粛要請に伴って、多くの飲食店が宅配サービスを提供するようになりました。そこで疑問に思うことは、衛生的な問題と保健所への許可などの登録について。
ここで少し補足しますが、外出禁止令が発令された後の飲食店は、日本では時間短縮で営業できましたが、アメリカでは店内に誰1人として入ることはできず、テイクアウトのみとなっていました。少しずつ飲食店のオープンができるようになったものの、再度オープンするためには保健所や市の許可を貰う必要があるのです。
家のなかでも靴を脱がない土足のアメリカ生活ですが、意外と衛生においてはとにかく厳しい。各レストランには、必ず保健所の査定の証明書を客の目の届く入口に貼られていなければならず、その店の衛生状況の評価はA・B・Cで誰にでもわかるようになっています。だから、客である私たちは安心して入店することができるのです。
日本での緊急事態宣言で、人のいなくなった夜の渋谷の状況をテレビで中継していたのを見ていたら、走り回るネズミがあちこちに映し出されていてとても驚きました。土足で生活する人にはいわれたくないと思いますが、日本のゴミ事情はとても先進国とは思えません。
たしかに都会にはゴミ箱自体がなく、国民はたいていゴミを自宅に持って帰ります。よって、街はキレイに保たれている。犬の排泄には水を掛けたり、マナーは徹底しているのはさすが日本!なのですが、これも都会と田舎には文化力の格差があるのも事実…。
もちろん、マナー違反をするものは、日本もアメリカも多いです。しかし自宅に持って帰るゴミのその後の事情が、日本とアメリカでは大きく違うと私は思います。
日本のゴミは、人の手によってビニール袋で出され、人の手によってそれが回収されますよね。アメリカの家庭では、大きなゴミ出し用の容器が3種類あり、1つは生ごみ、2つ目はリサイクル用(空き缶やプラスチックなど)、3つめはグリーンオンリーといった庭の手入れなどで出る草木、芝などしか入れられない容器とわけられています。
リサイクルに関しては、やる人もいれば、やらない人もいて、粗大ごみでもこの容器に収めることができる範囲であれば、なんでも入れてしまうことができる。なおかつゴミ収集会社もそのまま持って行ってくれる。自転車やタンスなどの粗大ごみも、リサイクル用の家庭用ごみ箱に突っ込んでいれば持って行ってくれるのです。
当然、ゴミ収集車は人が出したゴミを手で触れることなく、収集していくというわけ。トラックにはまるでUFOキャッチャーのようなアームがついており、トラックの運転手の操作によってゴミ箱ごと掴み抱えて、ひっくり返す…そして、ゴミ箱をもとの位置に戻すという大胆な方法で回収しています。
一方、日本のゴミ出しに関しては、いまだ昭和時代と変わっておらず、ゴミの分別は異常なくらいに厳しい。それにも関わらず、街や歩道の1カ所にビニール袋に入れただけの状態でゴミが出されているという環境は、とても衛生的だとは思えません。
カラス除けの網などを使っているとはいえ、カラスだって馬鹿ではない。簡単にゴミをまき散らし、ネズミだってそのゴミに寄ってきます。日本のこのゴミに対するサービスは、考え直すべきときだと思うのです。
アメリカのアパート生活であっても、比較的新しい大きなアパートやマンションでは「トラッシュ・シュート」というものが設備されていて、ゴミはその各階から投げ入れるだけで、1階にある大きなゴミ箱に落ちてくれる仕組みになっています。ゴミには触る必要がないように工夫がされているのは、アメリカでは当たり前のことなのです。
衛生面だけではありません。健康面に対しても、アメリカ人と日本人では少し意識が違うような気がします。というのも、「運動=自立のため」という認識がアメリカには色濃いと最近感じるようになったからです。
日本では、体を動かすエクササイズというものが「ダイエット」に直結している印象があります。ほかにも、たとえば趣味がゴルフであればゴルフのための運動、テニスならテニスのためというように、何かしら目的意識がある人が多い。
日本でジムに通う人も、体づくりやダイエットという目的でエクササイズをする人がほとんどで「健康」のために体を動かしているのは、意外とご年配の方ばかりなのではないでしょうか
日本では運動が体にいいことは誰もがわかっているにも関わらず、特別に太っているわけではなかったり、現状維持ができている人、いまのスタイルで満足できている人の多くは、運動を自分に課す人はあまりいません。
それは、日本の医療保険制度がアメリカとは大きく違うためだと考えます。怪我をしても、体調が壊れても、すぐに病院へ行けるという日本の国民皆保険制度があるからでしょう。
以前お話しましたが、アメリカでは日本のようにすぐに医者に掛かれません。旅先であれ、近場にある医者に自由に通えるかというと、できない。怪我も病気も、金銭的に命取りになるのがアメリカなのです。アメリカではかかりつけ医を通すことが当たり前で、勝手に大きな病院に訪れたりすると莫大な請求が送られてきます(加入している保険の種類にもよります)。
だから運動が好きとか嫌いとか、そういうことではなく、「体」の「健康」のために、ジムに行く人の割合がとても多い。「普段動かない生活」は、健康を害するという認識が高いし、「病気にならないために」「免疫力を高めるために」という健康意識がアメリカ人は高いと思います。アメリカの会社では、社内にジムが設けられているところもあるんですよ。
「健康を害する=病気」になるということだから、そうなるとものすごいお金が掛かるという恐怖。つまり、アメリカ人にとってジムに通う、運動をするということは、ストレス解消だったり、不眠解消のため、病気にならないための自己投資的意識。「病気にならないため=免疫力UP」という意識。
アメリカ、とくにロスは車社会で、日本のように電車で通勤、通学がありません。つまり、日本にいるのとアメリカにいるのとでは、歩く量は圧倒的に違います。私のクライアントも「日本に行くと美味しいものがたくさんあるから太る!」と懸念して日本に帰国していますが、意外と太って戻ってくる人はいません。
そう考えると、日本人の健康意識は「食べ物」だけに偏っている節があります。たとえば「高血圧にはこれがいい!」とどこかの誰かが発信すると、それが爆発的に売れるし、売り切れる。「これで痩せる」と聞くと、皆がこぞってそれを買い占める。「手っ取り早く」主義が一気に広がる。ダイエットにおいても、できるだけ運動をせずに、楽に痩せたいと思うのではないでしょうか。
コロナ禍で、日本のテレビで外出している人へのインタビューが報道されていました。そのなかに「感染しない自信がある」という人がいた。健康に気をつけて生活をしていると自負している人も多かったです。
ある男性は、「食生活」をきちんとバランスよく気をつけているから大丈夫!といっていて、またある女性は「野菜中心の食事で、ビタミンCを多く取るようにしているから大丈夫」といっていました。
「免疫力を高める!」という食材に群がりがちな日本人は、「運動すること=必要に駆られている人だけのもの」であるかのように思われているのではないでしょうか。
歳をとるごとに、汗をかく運動はほとんどやらなくなる。正確にいえばできなくなる。生活が便利になればなるほど、人は動かなくなる。動くという行動は、動けなくなってから、その重要性に気づくものです。
酒も飲まず、たばこも吸わず、オーガニックにこだわり、野菜中心の生活をしている人は健康なのでしょうか。そう思うか思わないかは、本人の主観の問題であってその人にしか感じえないものですが…。口に入れるものから、体は作られるとはいえ、ファンクション(動かせるか)の問題は無視していいものではありません
見た目年齢にこだわるのはアメリカも日本も同じ。ですが、80歳、90歳、自力で動けるお年寄りの数は、アメリカの方が多いような気がします。それはなぜか。日本では当たり前なのかもしれませんが、年老いた両親は子どもに介護を求める傾向があります。しかしアメリカでは「子どもの自立=親の自立」という考え方が根付いているのです。
アメリカでは子どもの世話になることが当たり前ではない。まだまだ「子どもが親の面倒を見ること=親孝行」と賞賛されることの多い日本ですが、アメリカではそういう常識はありません。親は親で自立し、子どもも子どもで自立しています。「親の介護で頭を痛めている」なんて話はあまり聞きませんね。
親の介護は専門のヘルパーや、ケアギバーにゆだねるのが一般的。そうならないためにも、アメリカ人は年齢とともに自立心が高くなる傾向にあると思います。親の立場側が、子ども孝行するという考え方に近いのです。
当然、ケアギバーやヘルパーを雇うとなると、それ相応のお金が必要になる。運動を自分に課す思考の高さの根底には、自立心への意識がある。もちろん日本人にも運動を課す人は多いですが、意識の持ち方がアメリカと日本では大きく違う。アメリカ人には「誰かの世話になるものか」という考え方が、無意識に根付いているように感じます。
アメリカ人と比較すると、日本人は運動能力の低下に対する危機感の持ち方が違うように思う。「肥満大国」のアメリカだからこそ、国民の危機感が違うのでしょう。健康を害することで、財布への痛みを伴うという現実があるからでしょう。でも、根底には「自立心」への意識が違うのです。
自分の足で歩けなくなるほど肥満の方は、日本で少ないでしょう。見た目から不健康な人は、日本には多くいない印象があります。でも、見た目で健康状態は判断できない場合も多い。
ボディービルダーは、筋肉質で健康的にみえるが、果たして全員が本当にそうなのだろうか?大会前には水すら飲まず、油も一切とらないボディービルダーの食生活というものは、「健康的」ではない。ボクシング選手の試合前の極端な減量も、決して健康的ではない。実はどちらが健康的かどうかは、安易にはわからない。だって、目的や意識が違うのだから。
免疫力とは食事だけで作られるものではなく、運動だけで作られるものでもない。感染したくなければ、衛生面での意識はもちろん、食べる、寝る、動くといった動物として当たり前の習慣のバランスを崩さないこと。健康でいるには、自分を知ることが重要で、「これを食べる!」とか「これは食べない!」とか、世間の意見や流行に自分を当てはめることではないです。
ジャンクフードを食べたければ食べてもいいし、お酒もたばこも、精神的に必要であれば我慢する必要はない。ただし、体は「動かすように」できている。世のなか便利になって、指先さえ動かせば、ある程度の物は手に入れることができるいま、体は積極的に動かしてあげる必要があるでしょう。
免疫力とは、我慢をして作り上げるものではない。たまには体温をあげ、汗をかき、美味しい物を美味しく食べ、ぐっすりと眠る。健康面、衛生面、両立して「病気になってなるものか!」という気を持ち続けることが「Withコロナ時代」を生きる我々に必要なことだと思います。
人に頼らず、自分のことは自分で…歳には関係なく自立心への意識の高さが、免疫力アップに最も必要なことではないでしょうか。
関連記事
-

-
日本人が清潔好きという伝統?
ネットで見つけた情報の写真。しかし、あるブログの書き込みでは、当否は洗えば洗うほど防御のため油分が
-
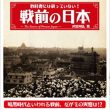
-
徴兵逃れ 『教科書には載っていない戦前の日本』p.238 政策があれば対策が生まれるのは、日中共通
合法的徴兵逃れは当初は金銭の支払いであったが、批判もあり廃止 養子縁組 あまりにも
-

-
広田照幸著『日本人のしつけは衰退したか』を読んで
日本人の車内でのマナーが良いとか、駅のトイレがきれいだと自画自賛する傾向が強い。しかし、国鉄末期の駅
-

-
名回答です。「故中国人の方はマナーが悪いで有名なのでしょうか?Kato Eiji, 空家再生、民泊経営 (2018〜現在)回答日: 日曜」
何故中国人の方はマナーが悪いで有名なのでしょうか?Kato Eiji, 空家再生、民泊経営 (20
-

-
『ビルマ商人の日本訪問記』1936年ウ・ラフ著土橋康子訳 大阪は「東洋のベニス」
1936年の日本を見たビルマ人の記述である 1936年当時の大阪市は人口三百万、町全体に大小
-

-
世界人流観光施策風土記 チベット旅行の検討から見えてきたこと
物流行政をしていたころ、港湾運送事業者が、貿易手続きが複雑なことが自分たちの仕事が存在する理由だとし
-

-
『中国人のこころ』小野秀樹
本書を読んで、率直に感じたことは、自動翻訳やAIができる前に、日本型AI、中国型自動翻訳が登場す
-
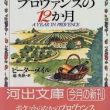
-
『プロヴァンスの村の終焉』上・下 ジャン=ピエール・ルゴフ著 2017年10月15日
市長時代にピーターメイルの「プロヴァンスの12か月」読み、観光地づくりの参考にしたいと孫を連れて南仏
-

-
意識あるロボットの出現とホスピタリティー論の終焉
かねがね、観光学研究で字句「ホスピタリティー」が使用されていることに大きな疑問を感じていた。意識
-

-
東日本震災時に問題視された略奪の限りを尽くしていた火事場泥棒
https://matome.naver.jp/odai/2150962666730148001
- PREV
- 対面型産業の物価注視を 危機後の金融政策の枠組み
- NEXT
- Quora 「汎化性能」

