観光人物列伝 中村豊『「東北のハワイ」はなぜV字回復したのか』常磐ハワイアンセンター
公開日:
:
最終更新日:2023/05/20
観光人物列伝
前身が常磐炭鉱という石炭の採掘会社で、社歴としては約130年になります。その常磐炭鉱が何故レジャーに乗り出したのかをお話します。昭和20年代、石炭産業は戦後経済の復興の基幹産業でした。昭和30年代に入ると石油に押され、経営が厳しくなりました。そして炭鉱にあった色々なセクションの分社をし、社員を移籍させました。社員の雇用を守りつつ、閉山準備に入ったのです。
常磐炭鉱というのは非常に労働条件が厳しい炭鉱で、石炭1トン掘るのに温泉40トン汲み上げなければ採掘が出来ない、という環境でした。源泉60度の温泉が地下から噴出するわけですから、まさに灼熱地獄でした。それを発想の転換で、この温泉を使って何か社員の雇用に結びつけられないかと考えました。これが「常磐ハワイアンセンター」の着想の原点であります。
当時の副社長の中村豊が、「ただホテルだけではお客様は来ない、お客様を呼ぶために何かを作ろう」と、構想に3年くらいかけました。そんな時、海外視察の帰りにハワイに立ち寄り、フラダンス、タヒチアンダンスを見ました。トエレという木を切り抜いた打楽器が非常に情熱的で、その音を聞いた時に「日本古来の民族芸能と相通ずるものがある。これだ!」とヒントを得て帰ってきました。炭鉱にあったセクションを全て分社化したので、設計、土木、建築、電気、あらゆる事業を自前でやれました。中村は人の力を借りず、炭鉱の社員、家族が力を合わせて自分達でつくる事に意義があるという考えでした。この時に外部からお呼びした方は2名のみです。1人は総料理長、もう1人は「フラガール」の映画にもなった、早川まどか先生です。今でもフラガールの先生として教えていただいています。あとは炭鉱の社員と家族だけです。常磐ハワイアンセンターに家族総出で移籍、ここでダメだったら我々家族は生きていけないという危機迫る状況からスタートしているので
石油へのエネルギー転換が進む中で産炭地域の職場確保のため常磐ハワイアンセンターができた、とか、東日本大震災でハワイアンズの施設に大きな被害があった、という程度のことは、多くの人が知っていると思う。しかし、本書を読むと、これらが並大抵の危機ではなかったことが分かる。
そして、これら以外にも、ハワイアンズは幾多の危機を乗り越えてきた。昭和41年に開設された常磐ハワイアンセンターの営業は好調だったが、昭和46年の鉱山事故で会社が巨額の借金を背負い、投資資金調達がままならなくなり、それに2度の石油ショックが追い打ちをかける。普通ならこの時点でつぶれていそうなものだ。平成バブルで活気が戻ったと思ったのも束の間、バブル崩壊。世界金融バブルと映画「フラガール」で再び盛り上がったが、リーマンショックに続く不況に頭を叩かれ、その数年後に東日本大震災で被災し、再建のため多額の借入金。これだけ多くの危機をよく乗り越えてきたものだ。本書を読んだ後、巻頭(p.17-18)のグラフ「入場者数の推移」を見ると味わい深い。
経営者の決断もさることながら、命がけの採炭現場で培われた『一山一家』の精神の下で、経営者、従業員が一体で頑張ったからだという。フーム、読者はこれまで「炭鉱=苛烈な労働争議」というイメージしかなかったが、それだけではなかったようだ。財閥系企業と異なり、経営者から従業員、その家族までもともと知り合いの地方企業だったからということか。そんな中での経営者の苦悩や従業員の頑張り、特に東日本大震災時の対応の素晴らしさには感涙であった。
石炭業界は、朝鮮戦争(1950年6月25日 – 1953年7月27日)に伴う1950年代前半の朝鮮特需期には需要増から一時好況となったものの、1950年代後半には労働運動の盛り上がりによるコスト増から低価格な輸入石炭との競合が露呈し、さらに1962年10月の原油輸入自由化によってエネルギー革命が加速して、構造的な不況に陥った[2]。常磐炭鉱(後の常磐興産)での整理解雇は1955年から始まった[3]。
そこで炭鉱労働者やその家族の雇用創出、さらに同社の新たな収入源確保のため、炭鉱以外の新規事業を立ち上げることになり、『日本人が行ってみたい外国ナンバー1』だった「ハワイ」に着目。炭鉱で厄介物扱いされていた地下から湧き出る豊富な常磐湯本の温泉水を利用して室内を暖め、「夢の島ハワイ」をイメージしたリゾート施設「常磐ハワイアンセンター」(じょうばんハワイアンセンター)の建設を計画した。しかし、社内でも先行きを疑問視する声が強く、炭鉱の最前線にいた社員たちの転身にも根強い反対があり、「10年続けば御の字」という悲観的な見方すらあった。最終的には当時の常磐湯本温泉観光社長(常磐炭鉱副社長兼務、後に社長)の中村豊が押し切る形で事業を進めた。
フラダンス、タヒチアンダンス、ポリネシアンダンスのダンサーは、自前で設立した常磐音楽舞踊学院から人材を供給した。
1964年に運営子会社として常磐湯本温泉観光株式会社を設立し、1966年にオープン。高度経済成長を遂げる日本に於いて、1964年に海外旅行が自由化されたものの、庶民には高嶺の花という時代であり、開業前の悲観論を尻目にホテルが当時破格の1泊3万円以上ながら東京方面から多くの観光客を集め、大型温水プールを中心にした高級レジャー施設として年間120万人強の入場者を集めた[4]。年間入場人員は、1968年度には140万人を突破し、1970年度には155万3千人となりピークに達した[4]。
1988年3月24日に常磐自動車道がいわき中央ICまで全線開通し、バブル景気に沸く首都圏と直結すると、1988年度に一気に年間140万人超まで入場人員が増加した[4][5]。これを機に総事業費50億円をかけてリニューアルを始めることになった。
2006年9月23日から映画『フラガール』が全国公開されたのを機に、「ワイワイ・オハナ」「アロハタウン」「フラ・ミュージアム」など次々オープンした。すると、翌2007年度には過去最高の年間161万1千人が入場し、かつ、初の年間160万人超を達成した[4]。
2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)が発生した。いわき市は震度6弱を観測し、施設に大きな被害が出た。当初早期の再開を目指したが、丁度1ヵ月後の4月11日には福島県浜通り地震が発生。市内南部の井戸沢断層と塩の平断層に加え、当館直下に存在した湯の岳断層の3つの断層が同時多発的にズレ動き、東北地方太平洋沖地震の本震よりも深刻な被害を出した。これにより、長期間の休業を余儀なくされ、2011年の年間利用者は40万人を切る事になった。
この困難を常磐炭鉱が次々と閉山していた頃の困難になぞらえ、また、震災復興への願いを込め、46年ぶりとなる全国キャラバン「フラガール全国きずなキャラバン」で日本各地で開催することになった。
2012年2月8日、約1年ぶりに全面開業。年間利用者は2012年度に140万人に回復し、翌2013年度には150万7千人となった。
関連記事
-
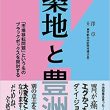
-
『築地と豊洲』澤章 都政新報社
Amazonの紹介では「平成が終わろうとしていたあの頃、東京のみならず日本中を巻き込んだ築地市場の
- PREV
- よそ者としての「tourist」の語感
- NEXT
- 西部邁『獅子たりえぬ超大国』を読んで


